※この連載はSAMEJIMA TIMESの筆者同盟に参加するハンドルネーム「憲法9条変えさせないよ」さんが執筆しています。
0.はじめに
1.「新しい階級社会」とは何か
2.5つの階級のそれぞれの世界
3.「アンダークラス」の哀しみ
4.「アンダークラス」を規定する要因
5.政治意識からみた現代日本人の5類型
6.橋本健二さんが考える処方箋は「大連立」のようだが…
7.トピックス:映画『国宝』興行収入100億円突破
0.はじめに
今日は、橋本健二(著)『新しい階級社会 最新データが明かす<格差拡大の果て>』(講談社、2025年)を読んで、「新しい階級社会」について考えていきたいと思います。
橋本健二さんは、早稲田大学人間科学学術院教授で、理論社会学を専門に研究しておられる方です。
「格差社会」について分析を進めていく中で、橋本健二さんは現代の最下層階級を「アンダークラス」と命名しています。
そのうえで、橋本健二さんは、著書の序文で次のような問題意識を披瀝しています。
格差拡大は、社会に対して多くの弊害をもたらす。格差が拡大すれば、アンダークラスを中心とする貧困層が増大し、また貧困はいままで以上に深刻なものとなる。多くの子どもたちが貧困に陥り、教育を受けるチャンスの不平等が拡大する。格差は健康状態や医療を受けるチャンスの不平等をもたらし、ここから命の格差が生まれる。若者の貧困化は、未婚化と少子化をもたらす。社会保障支出は増大し、国家は財政危機に陥る。しかも格差拡大によって増えた富裕層の所得の多くが貯蓄に回る一方で、所得の大半を消費する中下層の人々の所得が減れば、社会全体として消費が減少する。こうして景気は低迷する。
しかも格差拡大によって悪影響を被るのは、貧困層や相対的に貧しい人々だけではない。格差が拡大すると、社会から連帯感が失われ、人々は互いを信頼することができなくなり、ストレスを感じるようになる。こうして人々の社会活動への参加が減少し、社会全体の健康水準が低下し、子供のいじめが増え、また犯罪が増加する。多くの研究は、このように格差の大きな社会が病んだ社会であることを明らかにしてきた(ウィルキンソン&ビケット『格差は心を壊す』など)。
こうして階級構造という舞台装置の上で展開される人生は、多くの人にとってより厳しいものとなった。この新しい舞台装置は、協調より対立、平和より争い、幸せよりも不幸をもたらしやすく、したがって喜劇より悲劇にふさわしい。その方が面白いなどといっている場合ではない。そこで展開されるのは作り事ではなく、私たちの人生そのものなのだ。私たちの人生そのものが、悲劇となるのだ。
しかし私たちは、舞台装置に一方的に制約される無力な役者というわけではない。舞台装置の変化に自覚的であり、時には舞台装置を変化させることのできる、能動的な存在でもある。私たちに厳しく不快な人生を強いるような舞台装置は、作りかえてしまった方がいい。
しかしそのためには、この舞台装置がどんな形をしていて、どのように組み立てられているのか、どこにどのような問題があるのかについて、知る必要がある。本書はそのために書かれている。
それでは早速、本文の内容を見ていきましょう。
1.「新しい階級社会」とは何か
日本の高度経済成長が終わりを告げた1970年代半ばから1980年ごろまでの間は、経済格差に関する指標が底値を示し、国民のほとんどが豊かな暮らしを送る「一億総中流」と呼ばれる格差の小さい社会を形成していました。
実は、ジニ係数などの指標では1980年ごろから社会における経済格差が徐々に広がり始めていたのですが、人々の意識の上では「一億総中流」という考え方が常識として1990年代まで続いていました。
バブル経済が崩壊し、その後、不良債権問題などが噴出して不況が深刻化していく1990年代後半になって、「一億総中流」という常識が少しずつ崩れていくようになり、今や時代は完全に変わってしまい、従来は見られなかった「アンダークラス」という下層階級が出現して「新しい階級社会」を形成するに至っています。
この「新しい階級社会」を形成する「7つのクラス」を、橋本健二さんは次のように分類して提示しています。
現代日本の「新しい階級社会」を形成する7つのクラス
「資本家階級」:企業の経営者・役員(250万人)
「旧中間階級」:自営業者・家族従業者(658万人)
「新中間階級」:専門職・管理職・正規雇用の事務職(2051万人)
「正規労働者階級」:販売・サービス・製造・建設等、新中間階級以外の正規雇用労働者(1753万人)
「パート主婦」:有配偶の女性非正規雇用労働者(788万人)
「アンダークラス」:パート主婦以外の非正規雇用労働者(890万人)
「失業者」:59歳以下で専業主婦以外の失業者・無業者(273万人)
この分類の仕方でまず注意しておかなければならないことは、「資本家階級」が「従業員規模が5人以上の経営者・役員、自営業者・家族従業者」を意味するのに対し、「旧中間階級」が「従業員規模が5人未満の経営者・役員、自営業者・家族従業者」を意味しており、その線引きは従業員規模の差によって決められているということです。
そしてもう一つ注意しておかなければならないことは、「労働者階級」が一枚岩ではなく、「正規雇用労働者か非正規雇用労働者か」といった要素によって、「新中間階級」、「正規労働者階級」、「パート主婦」、「アンダークラス」という4つのクラスに分けられているということです。
そのうえで、橋本健二さんは、「資本家階級」、「旧中間階級」、「新中間階級」、「正規労働者階級」、「アンダークラス」の5つの階級について詳しく分析しています。
「パート主婦」に関する分析は、ジェンダー問題を考えるうえでは重要ですが、「新しい階級社会」のメカニズムを分析するうえでは、「配偶者(夫)の所属する階級に影響を受ける存在」として規定されているのだと思われます。
また、「失業者」に関しては、再び職を得た時点で「資本家階級」、「旧中間階級」、「新中間階級」、「正規労働者階級」、「アンダークラス」の5つの階級のうちのどこかに所属するようになる、ということが念頭に置かれているのだと思われます。
以上のことをふまえたうえで、橋本健二さんの分析を整理して見ていくことにしましょう。
2.5つの階級のそれぞれの世界
まず、「資本家階級」は、全般的に言えば経済的に恵まれていて、さらに経営者として仕事の裁量が大きいことから、仕事の満足度も高い階級です。親からの世襲で経営者になった人も多いですが、実際のデータ上では、「新中間階級」や「正規労働者階級」からの昇進や独立によって経営者になった人の方が多数派です。また、「アンダークラス」から「資本家階級」になった人も「資本家階級」の中に1割程度いて、飲食店や、小売店、コンビニなどの経営者が多いという特徴があるようです。「資本家階級」の中には「従業員規模が5人以上だが小規模な企業の経営者・役員、自営業者・家族従業者」という人が含まれるため、「資本家階級」に分類されながら収入が低いという人も一定数いるようです。
次に、「旧中間階級」は、自分で事業を営んでいることから、仕事の満足度は「資本家階級」の次に高く、自分のペースで仕事ができるという人の比率は「資本家階級」よりも高く、仕事にストレスを感じている人の比率は5つの階級のなかでもっとも低くなっています。消費スタイルは伝統的で、食生活の上での健康志向が強いという特徴があり、かつては自民党の強固な支持基盤でしたが、コロナ禍の影響を大きく受けて収入を減らし、「正規労働者階級」を下回る所得水準となり、自民党離れも進んでいるようです。
一方の「新中間階級」は、「資本家階級」に次ぐ豊かな階級であり、雇用は安定していて、貧困に陥るリスクは、5つの階級の中でもっとも低くなっています。「新中間階級」は、「新中間階級」の父親のもとで当たり前のように大学進学した人が多く、学歴では「資本家階級」を上回っています。しかし、あくまでも雇われ人であることから、労働疎外を免れず、自分の仕事の内容に満足している人の比率は「資本家階級」や「旧中間階級」に遠く及ばす、仕事にストレスを感じる人が多い状況です。
対して「正規労働者階級」は、資本主義社会において下層階級ではあるものの、雇用は守られていて、所得水準もそれなりに高い(コロナ禍を経た現在では「旧中間階級」よりも高い)という特徴があります。しかし、従事する労働の内容は「資本家階級」や「新中間階級」の指示によって統制されていて、仕事の内容に満足する人は少なく、仕事にストレスを感じる人の比率は5つの階級の中でもっとも高くなっています。
最後に「アンダークラス」ですが、「アンダークラス」は現代日本における最下層の階級になります。個人年収は「正規労働者階級」の4割強にとどまり、貧困率は37.2%に達しています。「アンダークラス」の大半の人が「自分は人並み以下である」と考えていて、全体の4割以上の人が「自分は貧困層である」と自覚しています。未婚率は、男性で74.5%、女性でも68.4%に上り、結婚して家庭を築くことができない人が多数を占めています。政治的には、支持政党のない人が圧倒的で、選挙での投票にも極めて消極的であり、政治から疎外された階級となっています。
3.「アンダークラス」の哀しみ
5つの階級のうち最下層の「アンダークラス」は、経済的に困窮しているということだけではなく、家庭においても、地域においても、また個人の心身の健康面においても、さまざまな困難を抱える存在として厳しい人生を歩んでいるという姿が、データから浮かび上がってきます。
「アンダークラス」の平均個人年収は216万円であり、「資本家階級」の個人年収983万円の2割程度、「正規労働者階級」の個人年収486万円の4割強にとどまっています。
また、経済的な困窮のみにとどまらず、「温かい家庭を築く」という幸せの形からほど遠い状況にあることが、「アンダークラス」の婚姻の有無に関するデータから見てとれます。
目をひくのは、アンダークラスの未婚率が他の階級に比べて大幅に高いことである。とくに男性の未婚率は、74.5%とすば抜けて高い。これには、20歳代の若い人が比較的多いということもあるのだが、年齢的にみても未婚率は、20歳代で93.0%、30歳代で83.5%、40歳代で72.8%、50歳代で54.4%と、いずれも高くなっている。正規労働者階級の未婚率は、20歳代から順番に、67.2%、29.4%、25.1%、18.3%だから、違いは明らかだろう。要するにアンダークラス男性は、結婚できないのである。
女性の場合、夫のいる非正規労働者はパート主婦として別扱いになっているので、アンダークラスは未婚か離死別のどちらかである。全体では未婚が68.4%、離死別は31.6%となっている。離死別者の比率が、他の階級に比べて極端に大きいことがわかる。しかし未婚者と離死別者の比率は、年齢によって大きく異なる。(中略)離死別者の比率は20歳代から50歳代まで順番に、2.1%、16.4%、36.4%、60.8%と、急速に大きくなっていく。これは離死別によって、専業主婦やパート主婦からアンダークラスへと流れ込んでくる女性が多数いるからである。
男性の場合は「非正規雇用労働者であるがゆえに結婚できない」というロジックで「経済的に困窮したうえに、温かい家庭という幸せも手にすることができない」という状況に陥っているという側面が強いのに対し、女性の場合には「一度は結婚して幸せな家庭を築いたが、離死別によってシングルとなり、非正規雇用労働者として生計を立てていかざるを得ないため、アンダークラス化した」という人がかなりの割合でいることが分かります。
「アンダークラス」の苦境はこれだけではありません。
アンケートに対して「近所の人とのつきあいがない」と回答した人の割合、「ふだん人と会話することがまったくない」と回答した人の割合、「日ごろ親しくし、頼りにしている家族・親族が1人もいない」と回答した人の割合、「日ごろ親しくし、頼りにしている友人・知人が1人もいない」と回答した人の割合が、5つの階級の中でいずれも「アンダークラス」が一番多く、社会の中で孤立している様子が浮かび上がってきます。
さらに、アンケートに対して「健康状態がよくない」と回答した人の割合、「身体的な理由で仕事やふだんの活動がいつもどおりにできなかった」と回答した人の割合、「心理的な理由で仕事やふだんの活動がいつもどおりにできなかった」と回答した人の割合、「うつ病やその他の心の病気で診断や治療を受けたことがある」と回答した人の割合が、5つの階級の中でいずれも「アンダークラス」が一番多く、心身の健康面においても不安を抱えながら暮らしている様子が浮かび上がってきます。
「あなたはどのくらい幸せだと思いますか」という質問に対して「非常に幸せ」または「やや幸せ」と回答した人の割合は、「資本家階級」で85.3%、「旧中間階級」で74.8%、「新中間階級」で80.2%、「正規労働者階級」で74.2%なのに対し、「アンダークラス」では59.0%にとどまり、「あまり幸せではない」または「まったく幸せではない」と回答した人の割合が実に41.0%にも上っています。
また、「あなたは将来の生活について不安を感じていますか」という質問に対して「とても不安を感じる」と回答した人の割合は、「資本家階級」で17.0%、「旧中間階級」で25.0%、「新中間階級」で20.2%、「正規労働者階級」で26.0%なのに対し、「アンダークラス」では実に42.8%にも上っています。
つまり、「アンダークラス」に位置する人々は、4割以上が「自分は不幸だ」と考えており、かつ、4割以上が「将来の生活にとても不安を感じる」ということなのです。
さらに言えば、「アンダークラス」において、「あなたは将来の生活について不安を感じていますか」という質問に対して「とても不安を感じる」または「やや不安を感じる」と回答した人の割合は、実に84.1%にのぼっており、この「将来不安」は、非常に深刻な問題であると言うことができます。
4.「アンダークラス」を規定する要因
人の所属階級を決定する要因として明らかになっているものは、次の4つです。
・出身階級:人は父親と同じ階級に所属する傾向がある。しかしこの傾向は、資本家階級と旧中間階級では強いが、新中間階級と労働者階級ではあまり強くない。
・性別:女性は男性に比べて、労働者階級になりやすく、資本家階級と旧中間階級にはなりにくい。
・学歴:学歴が高いと、資本家階級と新中間階級になりやすく、労働者階級と旧中間階級にはなりにくい。
・年齢:年齢が高いと、資本家階級と旧中間階級になりやすく、新中間階級にはなりにくい。
これらの4つの要因を基礎としたうえで、「アンダークラス」への所属を決定する要因として、橋本健二さんは次のような要因を指摘しています。
女性はオッズ比でみて男性の約2倍の確率でアンダークラスになる。大学卒以外の学歴の人は大学卒に比べてアンダークラスになりやすいが、この傾向は学歴が低いほど顕著で、高校卒の人は約3倍、中学卒の人は約4倍、アンダークラスになりやすい。そして学校を出てから就職するまでに1ヵ月以上の空白があると、すぐに就職した人に比べてアンダークラスになりやすい。(中略)
それ以外にも、さまざまな要因が人をアンダークラスに導いているようだ。まず、「父アンダークラスまたは不詳」の人、つまり父親が不在だったり、非正規雇用者や無職だったり、職業が不詳だったりした人は、アンダークラスになりやすい。
親から暴力を受けた経験のある人は、アンダークラスになりやすい。(中略)いじめにあった経験のある人、最終学校を中退した人、不登校を経験した人は、アンダークラスになりやすい。(中略)そして離死別を経験した女性は、それ以外の人に比べて、アンダークラスになる確率がオッズ比で4倍近くにも高まる。
所属階級は出身階級、つまり父親の所属階級によって決定される部分が大きい。また、学歴は、所属階級に強く影響する。しかし、出身家庭での経験や学校を出るまでの経験も、所属階級に影響しており、とくに在学中の困難な経験や、スムーズに就職できなかったことは、あとあとまで人々の所属階級に影響し、人々をアンダークラスへと導くようだ。
5.政治意識からみた現代日本人の5類型
格差の問題は政治の問題と切っても切り離すことができない関係にありますが、橋本健二さんは、日本人の政治意識について、現状を次のように整理しています。
(1)政治意識には、①格差と所得再分配に対する認識、②憲法問題や沖縄問題などの伝統的な保守―革新、③排外主義、という3つの軸があり、これらによって日本人政治意識は「リベラル」「伝統保守」「平和主義者」「無関心層」「新自由主義右翼」という5つの類型にまとめられる。
(2)人々の政治意識は、ある程度までは客観的な所属階級によって決定されるが、決定される度合いには限界があり、各階級の内部には政治意識の多様性がある。
(3)人々の政党支持は、ある程度までは客観的な所属階級によって決定されているが、それ以上に、政治意識によって決定されている。
これだけだと分かりにくいと思いますので、私の独断と偏見で「政治意識の5つの類型」を整理し直してみます。
日本人の政治意識
| 護憲派 左寄り | 改憲派 右寄り | |
| 格差是正派 所得再分配派 | リベラル (26.4%) | 伝統保守 (21.0%) |
| 格差容認派 自由放任派 | 平和主義者 (20.9%) | 新自由主義右翼 (13.2%) |
※これらに分類できない人々を「無関心層」(18.5%)とする。
5つのクラスターの「支持政党なし」の割合を見てみると、「リベラル」が59.9%、「伝統保守」が46.8%、「平和主義者」が65.6%、「無関心層」が62.1%、「新自由主義右翼」が42.7%ということで、「伝統保守」や「新自由主義右翼」の多くが自民党を支持し、「リベラル」の多くが野党を支持しているのに対して、「平和主義者」には思いを託せる政党が見当たらず、一定の政治的主義主張があるにもかかわらず「無関心層」よりも「支持政党なし」の割合が多くなっていることが非常に特徴的だと感じられます。
6.橋本健二さんが考える処方箋は「大連立」のようだが…
このような日本人の政治意識をふまえたうえで、日本社会を現在の危機から救う処方箋について、橋本健二さんは次のように述べています。
「新自由主義右翼」は、もともと少数派であるにもかかわらず自民党から、野党時代には政権奪還のため、政権を奪還したあとは政権維持のため、身の丈以上の厚遇を受けてきたといってよい。自民党が民主党から政権を奪還してから岸田文雄政権までの間、自民党が少数派に過ぎない「新自由主義右翼」の言いなりになり、連立与党の公明党がこれをみて見ぬふりをし、日本の政治を主導するという異常事態が続いてきたのである。
これらの人々の要求に応えすぎてきた自民党が、その本来の支持基盤であるはずの「伝統保守」へとスタンスを移すなら、格差の問題で自民党と野党が鋭く対立することはなくなる。このとき日本の政治システムは、日本人の政治意識の構図との対応関係を回復する。最大多数である「リベラル」、これに次ぐ規模の「伝統保守」、少数派の「新自由主義右翼」という、日本人の政治意識の構図に対応して、野党と自民党という二大勢力に、右派の少数政党が絡むという構図である。
(中略)
これまで日本の政治家たちは、伝統的な「保守―革新」の対立図式にとらわれるあまり、憲法や自衛隊、日米軍事同盟の問題だけでなく、格差や貧困の問題においても、対立が必然であるかのように考えてこなかっただろうか。とくに自民党の政治家たちには、憲法改正に反対する野党やその支持勢力の要求だからという理由で、格差縮小や貧困解消に向けた政策を拒否するきらいがあったのではないか。その結果、本来の支持基盤である「伝統保守」の人々の期待に背いてきたのではないか。そろそろ態度を改めた方がいい。これは人の幸せと命にかかわる問題であり、社会全体の存続可能性にかかわる問題なのである。
格差の縮小と貧困の解消が必要だという社会的合意のもとで、最大多数である「リベラル」の人々を支持基盤とする野党と、「伝統保守」の人々を支持基盤とする自民党を二大勢力とする政党システムが実現すれば、日本社会は大きく変わるだろう。
橋本健二さんは名指しして明示的には書いていませんが、前後関係から推測すると、石破自民と野田立憲が「大連立」を組むか、自公少数与党に立憲民主党が閣外から実質的に協力する「ステルス大連立」のような形で、自民党の旧安倍派の影響力をなくしたうえで、自民党と立憲民主党が連携しながら格差是正を進めていくことに期待しているようです。
ここからは私の個人的な感想になりますが、仮に石破自民と野田立憲の「大連立」が成立したとして、果たして本当に「格差是正」が進むのだろうか、と疑問に思っています。
おそらくは「消費税増税」という路線に進み、「現役世代から高齢世代への所得再分配」が行われる可能性は高いかもしれませんが、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の処遇格差の是正」(同一労働同一賃金)が行われる可能性は極めて低いのではないでしょうか。
また、「アンダークラス」の幸福感の低さを考えると、問題とすべきは「格差是正」のことだけなのだろうか、という気がします。
れいわ新選組が旗揚げの時に言っていた「あなたを幸せにしたいんだ」というスローガンは、実際の政治において必要とされているのではないでしょうか。
「野田立憲」には期待できないものの、「リベラル」陣営の政党は、政党再編も含めての再構築を行っていく必要があるとともに、戦線の構築のやり方をうまくすれば、「リベラルと伝統保守が提携して経済的な格差是正を進め、リベラルと平和主義者が提携して平和憲法を守る」というようなことも可能なのではないか、というようなことも夢想してしまいます。
なんといっても、「新自由主義右翼」は13.2%しかいないのに、「リベラル」は26.4%もいて、人数的には2倍のボリュームがあるわけですから、きちんと政治力を発揮していけば、より多くの政策を実現できるはずです。
そういった意味では、人数的なボリュームが少ないにも関わらず具体的な政策を次々と実現していっている「新自由主義右翼」の政策実現の手法に関しては、謙虚に学んで「リベラル」側も部分的に取り入れていく努力をしていくべきなのではないかと思います。
7.トピックス:映画『国宝』興行収入100億円突破
吉沢亮さん主演の映画『国宝』が、興行収入100億円を突破する大ヒットになっています。
私は普段めったに映画を見ないのですが、友人に誘われて見に行って、3時間アッという間でした。
まだ見ていない方は、ぜひ劇場に足を運んで、『国宝』の世界を体験してみてください!
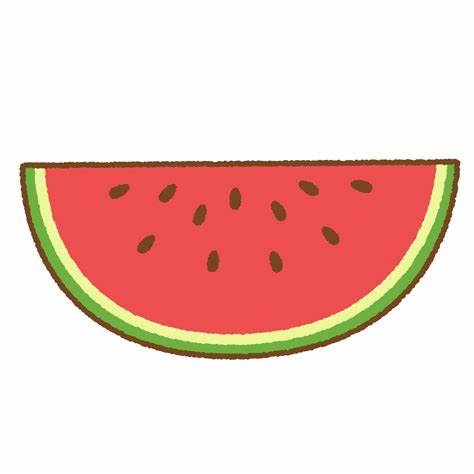
憲法9条変えさせないよ
プロ野球好きのただのオジサンが、冗談で「巨人ファーストの会」の話を「SAMEJIMA TIMES」にコメント投稿したことがきっかけで、ひょんなことから「筆者同盟」に加わることに。「憲法9条を次世代に」という一民間人の視点で、立憲野党とそれを支持するなかまたちに、叱咤激励と斬新な提案を届けます。

