※この連載はSAMEJIMA TIMESの筆者同盟に参加するハンドルネーム「憲法9条変えさせないよ」さんが執筆しています。
0.はじめに
1.「プランB」とは何か?
2.「身を切る改革」は地方経済の首を絞める
3.「プランB」が地方経済を救い、日本経済を救う
4.「予防医療教育」と「演劇」の融合
5.「プランB」は果たして成功するのか?
6.トピックス:どうなる首班指名選挙
0.はじめに
前回と今回の2回にわたって、兪炳匡(著)『日本再生のための「プランB」医療経済学による所得倍増計画』(集英社、2021年)を読んで、日本の社会・経済システムを刷新するための「日本再生プラン」について考えています。
兪炳匡さんは、早稲田大学人間科学学術院教授で、医療経済学を専門に研究しておられる方です。
日本の社会・経済システムを刷新するための「日本再生プラン」のうち、一般的に提唱される「プランA」がITやAI等を駆使したイノベーション誘導型の再生策であるのに対し、兪炳匡さんが提唱する「プランB」は、医療・教育・芸術を融合させて新たな分野での雇用を創出し、所得倍増を図っていくという斬新なアイデアです。
前回の記事では、一般的に提唱される「プランA」が日本では失敗に終わる危険性が高いというその理由について見ていきました。
今回の記事では、兪炳匡さんが提唱する「プランB」の内容と、その可能性について見ていきたいと思います。
1.「プランB」とは何か?
今回の記事で取り上げる「プランB」について、兪炳匡さんは次のように述べています。
プランBは、「日本の全住民の衣食住を充足させる」ことが最大の目的ですから、日本全国どこでも、ただちに少ない資源(予算と人員)で開始することが可能であるべきです。実施主体は、非営利組織である地方自治体や民間「非」営利団体(Non-Profit Organization=NPO)であるべきとも私は考えています。
(中略)
プランBが含むべき主要産業である、医療・介護、教育、政府機関、農林水産業は、日本ではいずれも伝統的に非政府組織が担ってきた割合が高く、ゆえに政府の規制が強い産業分野でもあります。これらの部門のGDPと雇用創出への寄与率の将来の規模は、日本の政治的リーダーシップの胸三寸で、つまり選挙民の判断次第で決まります。
2.「身を切る改革」は地方経済の首を絞める
地方自治体の支出を削減する「身を切る改革」の危険性について、兪炳匡さんは次のように述べています。
X市役所で住民票を取得する場合に窓口で担当してくれるスタッフを、公務員から、営利企業による派遣社員に変えると仮定します。X市役所の公務員一人当たりの年間給与が600万円だと仮定します。この公務員の仕事を、新たに公務員を雇用する代わりに、派遣企業に500万円で外注すれば、X市の支出は100万円削減されます。この結果、X市が「100万円得する」わけではありません。なぜなら、派遣企業が手数料100万円を抜いて、「地元の人」を派遣社員として400万円の給与で雇用するからです。
この場合、X市地元住民一人の給与が600万円から400万円に減少することを意味します。この結果、この住民がX市に納める住民税が確実に減ります。給与が600万円から400万円に下がれば、地元X市のスーパーで買い物する金額も減るので、スーパーからX市への法人税額も減ります。派遣企業がX市以外に立地するなら、この企業が手数料として抜く100万円は、X市からの「富の流出」を意味します。しかし、派遣会社が地元の人を雇用する限り、雇用統計の悪化とは認められません。
こうした場合、雇用統計だけを見て、地元の経済は安泰だと見なして本当によいのでしょうか?
X市役所が、行政コスト削減の御旗のもとに、派遣社員の数を増やせば増やすほど、X市内で循環するお金が減り、結果的にX市の税収が減ります。すると、X市は上記と同じ公務員の仕事を、500万円よりさらに低い400万円で派遣企業に外注するようになります。
契約金額が低下しても、利潤と株主配当を最重視する派遣企業は、100万円の手数料を維持し、X市の住民を300万円の給与で一年契約の派遣社員として雇用します。その結果、さらにX市で循環するお金が減少し、X市の税収はますます低下し、契約社員の給与が200万円になり、100万円になり……最後はボランティアに依存してX市の市役所は運営されるようになります。つまり、ボランティアに依存するという最終局面に至って、ようやく雇用統計の悪化が認められます。
最終的に、低給与・低生活水準に耐えられず、多くの住民がX市から逃げ出し、X市そのものが人口減で「消滅」して、隣接する自治体に吸収されます。その結果、元X市地域の住民は、生活に不可欠なサービスである住民票を取得するために、片道2時間かけて遠方の市役所に行かねばなりません。
「公的部門の支出を最小化すれば、全住民の生活水準が上がる」というレトリックに騙され続けた元X市の住民に、「自己責任として、この惨状に耐えろ」と果たして言えるでしょうか。「行政コスト削減」の御旗のもとで、自治体そのものの余命をゼロまで削減したわけです。これは日本の全ての地方自治体にとって、明日は我が身の姿ではないかと私は思います。
3.「プランB」が地方経済を救い、日本経済を救う
「プランB」によって地方経済、そして日本経済を救うという基本プランについて、兪炳匡さんは次のように述べています。
プランBの最大の目的は、「日本の全住民の衣食住の充足」です。従って、プランBの下での評価方法は、疲弊している日本の地方経済を切り捨てるものであってはなりません。またプランBの目的は「負けを減らす」ことです。「勝ち(地元外からの富の流入)を増やす」ことを目指すプランAが失敗した場合、プランBは「富の流出を減らす」ことで日本の全住民の生活水準の維持を目指します。
日本国内で地方経済が構造的に衰退している一因は、「上がらない、回らない、漏れる経済構造」に囚われているためです。すなわち、
(1)地元のいわゆる「99%」の労働者の「賃金が上がらない」
(2)地元の実体経済・潜在的成長産業に「おカネが回らない(循環しない)」
(3)地元の実体経済から「富と人材が漏れる(流出する)」
という三重苦の構造です。
この三重苦の経済構造は、日本の分断・二極化を生んでいます。富める一極には、「(大規模営利企業が集中する)東京」と「(東京と直通のパイプを持つ)一握りの地方在住者」しかいません。この日本国内の東京と地方の関係に、見覚えはありませんか?この関係は、国際社会における「(グローバル営利企業が集中する)米国など(中心)」と「日本(辺縁)」の関係と同じです。(中略)
この「上がらない、回らない、漏れる経済構造」に対する最も重要な対策は、非営利部門の拡大です。少なくともプランBに関連する医療、教育、芸術・文化、政府機関への営利企業の参入を最小化することが必要です。(中略)
非営利部門と営利部門の制度上の最も重要な違いは、非営利部門の組織は、事業収入を「組織外の株主」に配当することを禁じられていることです。例えば、非営利組織の病院が得た収入は、その病院組織内で、職員の給与や病院内への設備への投資として使い切る義務があります。営利企業が「組織外の株主」に配当することは、企業が株主から資本提供を受けた見返りとして、企業組織内から組織外の株主への「富の流出」を認めていると言えます。
地方自治体から支出されるお金の流れていく先が、非営利部門か営利部門かを峻別することで、「その地域経済圏内の非営利部門から営利部門への富の流出」を明らかにできます。結果的にこの峻別は、地方から首都圏への富の流出を減らし、日本から国外への富の流出を減らすことにもつながります。
4.「予防医療教育」と「演劇」の融合
日本再生のための「プランB」の具体的な内容について、兪炳匡さんは次のように提案しています。
IT分野の国際的巨大企業によるビッグデータ分析・AIを基礎とするビジネスに対抗できる日本の切り札を、「プランB下の芸術・人文社会科学」にすることを提案します。一例は、医療費高騰への対策が二種類あることです。一つめの対策は、将来の医療費を正確に予測することです。二つめの対策は、医療費を削減することで、当然一つめの対策より重要です。しかし、二つめの対策がより困難であることが理由で、一つめの対策のほうが注目されやすいのです。
一つめの対策に最も関心が高いのは、医療保険機関です。なぜなら、1年後の医療費を正確に予測できれば、医療保険機関は赤字にならないように、営利保険企業なら期待される利潤率を達成できるように、保険の掛け金を事前に設定できるからです。具体的には、AIはビッグデータを基に、暴飲暴食を繰り返し、スポーツクラブに行かず、年収がX円で、友人がY人以下の、ある個人の今年一年の医療費を「平均」としてかなり正確に予測できます。この予測技術において、日本企業はIT分野の国際企業に大きく遅れています。この遅れを挽回するために提案されている「技術者を増やし、規制を緩和することで様々な個人情報への企業アクセスを容易にする」と言う案は、私から見れば「追いつき追い越せ型の『古い』」発想です。先行する巨大企業とは「同じ土俵で競争しない」という発想の転換が必要です。
発想の転換の一例として、予測の精度にこだわる「古い一つめの対策」よりも、芸術・人文社会科学を「新しい方法で活用する二つめの対策」を重視すべきです。先の個人の例で、二つめの対策とは、暴飲暴食を止める契機や、スポーツクラブに一緒に行く友人を見つける契機を提供することです。この二つめの対策を成功させる確率は、AIよりも、「プランB下の芸術・人文社会科学」のほうが高いとの仮説を、私は立てています。
(中略)この仮説の正しさを今後証明できれば、「AIの予測よりも実際の医療費がはるかに低い」という、良い意味でAIの予測を外すことが可能です。予測が外れれば、AIの価値は下がります。AIの価値が低くなれば、「AIに対抗可能な、日本の切り札であるプランB下の芸術・人文社会科学」により多くの予算を配分することも正当化できます。暴飲暴食に苦しむ人にとっても社会全体にとっても、正確な1年後の医療費の予測よりもはるかに重要なことは、暴飲暴食を止めて医療費を削減することです。
(中略)
今後日本で行う医療と人文社会科学・芸術との共同研究に基づく予防医療教育が、予防効果を大幅に改善する余地は多く残されています。効果の高い予防医療教育に関しては、国際的にも大きな需要があります。
(中略)
解決策を、私は医療経済学の視点から長年探求してきました。その解決策を探す対象分野も、自然科学・経済学から、芸術・人文科学に拡がりました。(中略)私が最終的に辿り着いた解決案は、演劇でした。
(中略)
「演劇」と聞いただけで、かつての私のように、引いてしまう読者は多いかと思います。ステージの上でスポットライトを浴びて、日常生活ではおよそ使わないようなセリフを叫ぶような(かなり恥ずかしい)演劇とは対極的な演劇の一つに、ボアールの演劇があります。誰しも職場・学校・家庭内において、何らかの苦痛があるでしょう。これらの苦痛を今後少しでも減らすという実用的な目的のため、職場・学校・家庭内での経験を演劇として再現するのが、ボアールの演劇です。趣味として演劇に興味を持った10年後に、ボアールの演劇理論を含む演劇の力を借りれば、予防医療教育の分野で、巨大なブレイクスルーを起こせる可能性に気付きました。
私が在米中に開発した「Health Education Theater(健康教育劇場)」の最大の特徴は、予防医療教育プログラムの参加者全員で、オリジナルの演劇を創作し、出演することです。このプログラムの目的が食習慣の改善であれば、創作する演劇は何らかの形で食習慣を表現します。例えば、暴飲暴食の後に経験した苦痛について演劇で表現します。さらに言えば、暴飲暴食の食習慣の根本的な原因である、職場・学校・家庭内における、何らかのストレス・苦痛について表現することも可能です。
(中略)
平田氏(引用者註:劇作家、演出家の平田オリザ氏)によれば、演劇は誰でも、アマチュアからプロまでのどのレベルでも楽しめるという特性があります。演劇は総合芸術ですから、脚本に詩を含めても、ステージでダンスを取り入れてもかまいません。演劇の経験がなくとも、自分が好きであったり、または取り組んできた何かを使って貢献ができます。医療分野で応用されてきた様々な種類の芸術のうち、演劇が最も有望であることを示唆する研究もあります。
(中略)
プランBの一環として地方移住を特に薦めたいのは、大都市で金銭的な意味で綱渡り生活をしている三つのタイプの人々です。具体的には、「貯蓄ゼロ世帯」、「食料へのアクセスが保証されていない世帯」、「プランBの予防医療教育に必要な人材(文系の研究者、アーティスト)」です。
(中略)
最も基本的なアイデアは、地元で生産できる農林水産物・食料を「第二の通貨」ないし「組合加入者の特典」として、農林漁業に「何らかの形で貢献」する組合加入者に提供することです。
提供される農産物がコメのみだとしても、個人で消費しないコメを用いて「物々交換」を行えば、コメ以外の食料や生活必需品を入手できます。物々交換の利点は、消費税を払う必要がないことです(これによる地方自治体の消費税収入の減少分は、現時点では微々たるものです)。
営利企業における株主配当(金銭)に相当するのが、このアイデアにおける組合員への食料配当です。目的は、日本の農林水産業と、プランB下での地方移住者を同時に保護することです。
農林漁業に「何らかの形で貢献」することは、農林水産省が推進する「農林漁業の六次産業化」の下では困難ではありません。(中略)農作業に体力的に参加できなくても、食品加工・開発や小売販売・広報に貢献できる人は多いでしょう。
(中略)
地方自治体が(中略)プランB下の予防医療教育のコーチ(ないしコーチの教育者)として、文系の研究者を非常勤職員(週20時間勤務、年間給与150万円以上)扱いで雇用する例です。
文系の非常勤研究者にとって、常勤の研究職に就くために最も必要なものは、研究に使える時間です。しかし、生活費を稼ぐために複数の非常勤講師の仕事に忙殺されて、研究に使える時間が少なくなるケースをプランBは救うことができます。
常勤職に就くためには非常勤講師としての教育歴は必要ですが、一定期間以上の「非常勤講師としての教育歴だけ」では、むしろ否定的に評価されます。ですから、1~2年の短い期間でも、生活費の心配がなく、研究に必要な時間を確保できることを「売り」にして、文系の研究者の短期移住を地方自治体が歓迎してはどうでしょうか。同時に、これらの研究者が地元の大学に研究員として所属し、研究者コミュニティや図書館へのアクセスを支援することも重要です。
なぜなら高学歴の文系の研究者は、上記の予防医療教育プログラムの開発にも貢献できる上、塾講師も務まり、六次産業化した農林水産業に貢献できる可能性も十分あります。
移住した文系の研究者は、少なくとも上記の非常勤職員として収入150万円を地方自治体から得る以外は、塾講師などの追加労働につき、その報酬を食料として受け取ります。「報酬としての食料」は、物々交換市場において「第二の通貨」として用いることで、生活必需品の多くを調達できます。
研究者でない移住者は、子供の教育費を食料で支払うことができれば、現金支出は(中略)減少させることが可能です。同様の仕組みを用いれば、医療機関受診時に窓口負担として払う「現金」支出を減らすことも可能です。この窓口負担の一部を、地方自治体が支払う例は既に珍しくありません。
さらに言えば、食料を介在せずに、地方の「物々交換市場」において、必要なサービス・モノを直接交換することも可能です。家庭教師としてX時間のサービスを提供する対価として、家電製品の修理をしてもらえることが一例です。プランB関連の職種の技能を少なくとも一つ、できれば二つ以上持つことは、個人として生き延びる確率を上げる、すなわち個人レベルの危機管理にもなります。
(中略)
また、地方自治体がプランBの予防医療教育のコーチとして、大卒程度の研究者やアーティストの移住を、短期間であれ数多く受け入れることは可能です。多くの人々が出入りすることで、ムラ社会の閉鎖性は緩和されるでしょう。
この結果、(中略)地方には「仕事がない、特に高い給与の仕事がない」、「子供に良い教育を与える機会がない」、「最先端の文化・芸術に接する機会がない」、「個人(一家族)として移住後、地方の閉鎖的なムラ社会に馴染めるか自信がない」といった、現在都市に在住している人々の懸念は、かなりの程度まで軽減可能になります。
5.「プランB」は果たして成功するのか?
兪炳匡さんが提案する日本再生のための「プランB」について、私の感想と意見を述べたいと思います。
私の好きなプロ野球に例えると、「プランB」は1990年代の野村ヤクルト、「プランA」は第二次長嶋政権時代の長嶋巨人に似ているような気がします。
野村ヤクルトvs長嶋巨人
| 野村ヤクルト | 長嶋巨人 | |
| 1990年 | 5位 | |
| 1991年 | 3位 | |
| 1992年 | 1位(リーグ優勝のみ) | |
| 1993年 | 1位(日本一) | 3位 |
| 1994年 | 4位 | 1位(日本一) |
| 1995年 | 1位(日本一) | 3位 |
| 1996年 | 4位 | 1位(リーグ優勝のみ) |
| 1997年 | 1位(日本一) | 4位 |
| 1998年 | 4位 | 3位 |
| 1999年 | 2位 | |
| 2000年 | 1位(日本一) | |
| 2001年 | 2位 |
1994年と1996年と2000年の長嶋巨人は成功した米国の「プランA」、それ以外の年の長嶋巨人は失敗した日本の「プランA」のイメージで、野村ヤクルトが「プランB」です。
野村ヤクルトが一番上手くいったのは、1997年のシーズンです。
前年リーグ優勝した巨人が清原和博選手を西武からFAで獲得するなど「33億円補強」を行い、1994年から1996年まで3年連続で開幕試合完封勝利を続けていた巨人のエース斎藤雅樹投手が4年連続開幕試合完封勝利を目指して先発したのに対して、広島を戦力外になってヤクルトに移籍してきた小早川毅彦選手が開幕戦で3打席連続ホームランを放ち、ヤクルトがまさかの開幕戦勝利!
結果的にこの開幕戦の一試合だけで帰趨が決してしまった1997年シーズンは、他チームで戦力外になった選手を寄せ集めて「野村再生工場」と呼ばれたヤクルトが、2位を10ゲーム以上引き離してぶっちぎりのセリーグ優勝!
日本シリーズでも西武に勝って、日本一となりました。
IT分野の国際的巨大企業によるビッグデータ分析・AIを基礎とするビジネス(プランA)に対抗できる日本の切り札が「プランB」だという兪炳匡さんの主張は、上手く機能したときの可能性を考えると、確かにその通りだと思います。
しかし、野村ヤクルトの戦績を見ても分かるように、「勝つ年もあれば、負ける年もある」というか、兪炳匡さんの「プランB」は、「上手くいく地域もあれば、上手くいかない地域もある」のではないかという感じがしています。
「プランB」は、都会で金銭的に恵まれない生活を送っている人たちが地方に移住し、自分の得意な分野の能力を持ち寄って活動し、その地域を盛り上げていくというものです。
確かに、上手くハマれば、それぞれの個人が秘めた潜在能力を発揮して、巨大企業に対抗できるような実績が出せるようになるかもしれません。
一方で、その地方に集まってきたメンバーが上手くハーモニーを奏でることができなければ、大した成果をあげられずに終わってしまう可能性もあります。
また、気になるのが、「労働の報酬を食料で支払い、物々交換を行う」という考え方で、労働基準法によれば労働の対価としての給与は「通貨」で支払う必要があり、基本的に「現物支給」はできないことになっていたと思いますので、実際にそうした法令の規定に抵触しない形での運用が可能なのかどうか、ちょっと心配に思いました。
「食料」そのものを流通させるのではなく「お米券」や「食料引換券」のようなものを発行するとしても、今度は「お米券」や「食料引換券」に値段がついて、高騰したり暴落したりするなどの価格変動の影響を受けてしまう危険性もあるのではないかという気もします。
とはいえ、日本では「プランA」が成功する可能性は限りなくゼロに近いことは明らかですので、どのような形にすれば「プランB」が成功する可能性を高めていくことができるのか、いろいろな人の知恵を持ち寄ってブラッシュアップしていくなら、日本再生のための起爆剤になる非常に面白いアイデアなのではないかと感じました。
6.トピックス:どうなる首班指名選挙
自民党総裁選で高市早苗さんが新しい総裁に選ばれ、日本の政治が大きく動き出しました。
まず、立憲民主党の辻元清美さんが、テレビ番組で国民民主党代表の玉木雄一郎さんに直接詰め寄り、一種の「電波ジャック」を行い、事実上の「首班指名選挙野党統一候補選抜クライマックスシリーズ」が開幕しました。
そして、立憲民主党幹事長の安住淳さんが「立憲民主党は野田佳彦首班にこだわらない」という立場を表明したことで、一気に政権交代実現の機運が高まってきました。
国民民主党が「首班指名選挙では、1回目も2回目も玉木雄一郎の名前を書く」という立場を明らかにしているため、自公連立政権が続く状況下においては、他の政党が首班指名選挙でどのような投票行動を取ろうとも「高市早苗総理誕生」か「玉木雄一郎総理誕生」以外の結果を生み出すことができず、そのため立憲民主党と日本維新の会が連携して「玉木雄一郎」の名前を書く方向で野党間の協議が進んでいきました。
しかし、当の玉木雄一郎さん本人は、「政策が異なるので、立憲民主党とは一緒に政権を作れない」という旨の発言を繰り返し行いました。
玉木雄一郎さんの発言を論理的に読み解くなら、「立憲民主党と一緒に政権を作る気はないが、自民党が首班指名してくれるなら、自分が総理大臣になりたい。自民党が首班指名してくれないなら、首班指名の決選投票で玉木雄一郎の名前を書いて、他の野党統一候補が首班指名されるのを阻止し、高市早苗総理誕生のアシストをしたい。」と言っているとしか、私には理解できません。
そして、10月10日、そのような状況を一変させるニュースが飛び込んできます。
公明党の連立離脱です。
これにより、「高市総理」や「玉木総理」以外に、他の野党のリーダーにも首班指名を受けるチャンスが生まれてきたことから、れいわ新選組の支持者が「X」(旧twitter)上で「#じゃあ山本太郎で」や「#山本太郎を総理大臣に」といったハッシュタグで次々にツイートを行い、トレンド1位になりました。
しかし、その後、公明党は「首班指名選挙では斉藤鉄夫の名前を書き、決選投票になった場合には、斉藤鉄夫の名前を書くか、棄権する」との立場を表明したため、自民党総裁の高市早苗さんとの決選投票で勝つことができる野党側の候補は、玉木雄一郎さんと斉藤鉄夫さんの2人にほぼ絞られるような形になっています。
私個人の見立てを言いますと、次の臨時国会で政権交代が実現する可能性は極めて低いと考えています。
野党側の多数派工作が成功するのか失敗するのかは予断を許しませんが、野党側の多数派工作が失敗した場合には、石破総理は臨時国会で内閣総辞職し、首班指名選挙で自民党が勝って、高市内閣を発足させることになります。
逆に、野党側が一致結束し、首班指名選挙で野党側が一人の候補者に過半数の票を集めることができる算段がついた場合には、石破総理は臨時国会で内閣総辞職を行わず、状況を打開するために、衆議院解散を行うでしょう。
石破内閣のまま解散総選挙に突入した場合、「憲政史上初の女性総理が実現するかどうか」が選挙の争点となるため、女性総理の誕生を待ち望む無党派層の票を自民党が取り込み、自民党が圧勝してしまう可能性が高いのではないかと思います。
それを回避するには、野党側が「総選挙後の特別国会における首班指名候補」を一人選ぶ必要があり、なおかつ、「憲政史上初の女性総理が実現するかどうか」を争点化しないため、野党側も女性を首班指名候補に選ぶべきだと私は考えています。
それは「野党統一候補」であることが望ましいですが、場合によっては「立憲民主党が選んだ首班指名候補」でも構わないので、とにかく多くの有権者が「高市早苗さんよりも、こっちの方がいい」と感じるような有力な候補者を探してくる必要があります。
私の独断と偏見でリストアップさせてもらうと、こんな感じです。
次期衆院選 野党側「総理大臣」指名候補(案)
○芸能界から:吉永小百合さん(女優)
○スポーツ界から:有森裕子さん(バルセロナ五輪マラソン銀メダリスト)
○実業界から:南場智子さん(横浜DeNAベイスターズオーナー)
○学識経験者から:加藤陽子さん(歴史学者)
○政界から:小池百合子さん(東京都知事)
実際にこのようなビッグネームを連れてこれるかどうかは何とも微妙ですが、このくらいの感じで「日本初の女性総理」の候補者を野党側でも一人選んで(できれば政界の外から首相候補を選んで)、自民党総裁の高市早苗さんとガチンコ勝負をする必要があると思います。
どこかから野党側の女性総理候補を連れてこれた場合には、その人を「立憲民主党:東京ブロック比例単独1位」の比例候補に処遇して衆院選に臨んでもらい、衆院選後の特別国会の首班指名選挙で勝てれば「日本初の女性総理」として首相官邸で働いてもらって、首班指名選挙で勝てなかった場合には衆議院議員を辞職して立憲民主党に議席を返し、ご本人には元の仕事に復帰していただくような形にすれば良いと思います。
それでは、解散総選挙を誘発せずに、次の臨時国会で決着をつけようとする場合はどうか。
そのためには、「自民党は勝てると思って石破内閣が総辞職し、首班指名選挙に突入したが、想定外のことが起きて野党側の候補が高市早苗の票を上回り、政権交代が起きた」という状況を作るしかありません。
実は、それができるのは、れいわ新選組だけだと私は考えています。
その前に、れいわ新選組にとって最悪となる首班指名選挙の結果を示しておきましょう。
臨時国会首班指名選挙「決選投票」悪夢の結果
高市早苗:229票
斉藤鉄夫:227票
無効票:9票
これは、自民党の高市早苗さんと野党側の斉藤鉄夫さんが決選投票になって、れいわ新選組の9名が無効票を投じた場合に生じ得る結果です。
この場合には、れいわ新選組が決選投票で「山本太郎」と書いてしまったために、自民党政権の存続と、高市総理の誕生を許すという結果をもたらすことになります。
こうした状況が起きる時には、参政党の「3票」が高市早苗さんの方に乗っかっていますので、右派系の人々が「#神谷宗幣GJ」とか、「#参政党の3議席にはれいわの9議席の100万倍の力がある」とか、「#高市早苗総理誕生バンザイ」といったツイートで大盛り上がりになって、逆にリベラル系は意気消沈するか、れいわ新選組に怒りの矛先が向かい、「#れいわも山本太郎も茶番」とか、「#野党共闘を壊すれいわは自民党を守る補完勢力」とか、「#空気を読まないバカにはこの国は変えられない」といったツイートがれいわ新選組の議員や支持者へ次々に送られることになるでしょう。
仮にそうなったとしても、れいわ新選組のコアの支持層はれいわ新選組と山本太郎を支持し続けると思いますが、今後の国政選挙では200万票~300万票程度の票を取る小規模政党としての位置づけが固定化し、政党としての規模の拡大は全く望めなくなるでしょう。
一般の有権者の目には、「せっかく公明党が連立離脱して面白くなったと思ったのに、結局れいわが日和ったせいで、自民党政権を倒せなかった」というふうに映るはずです。
また、れいわの政党支持率が下がるくらいの話だけで済めばいいですが、高市政権が誕生したら、どこかの段階で政治的な火遊びに手を出して、自衛隊を動かして日本が戦争や紛争に巻き込まれるといった事態が発生してしまうかもしれません。
そうなってしまってから「あのとき高市政権の誕生を阻止しておけばよかった」といくら悔やんでも、後の祭りです。
それでは、れいわ新選組は今回の首班指名選挙に際してどのような姿勢で臨むつもりなのか、おしゃべり会での山本太郎さんの話を聞いてみましょう。
れいわ新選組の山本太郎さんは、「消費税5%への減税と、全国民への10万円の一律給付の二つを呑んでもらえれば、山本太郎以外の名前を書くことも有り得る」という趣旨のことを言っています。
今後の展開についての私の予想ですが、この二つの条件が両方とも受け入れられる可能性は低く、良くてどちらか一方、おそらくはどちらも受け入れてもらえないのではないかと思います。
その場合には、「高市早苗さん、玉木雄一郎さん、斉藤鉄夫さん、この3人のうち誰が総理大臣になっても大して変わらない」、だから、「首班指名選挙では、1回目も2回目も山本太郎の名前を書く」という結論に至るものと思われます。
れいわ新選組の山本太郎さんがそのような発言を繰り返していけば、自民党副総裁の麻生太郎さんは、首班指名選挙の結果をこんな感じで票読みするのではないかと思います。
臨時国会首班指名選挙「決選投票」麻生太郎自民党副総裁の目から見た票読み
高市早苗:229票
斉藤鉄夫:219票
無効票:17票
れいわ新選組以外に、日本共産党も首班指名選挙で公明党の斉藤鉄夫さんの名前を書くのは(歴史的な経緯を考えれば)とてつもなく高いハードルがあるはずで、「れいわと共産党は決選投票で斉藤鉄夫とは書かない」という見方が有力視されるのではないでしょうか。
しかし、れいわ新選組の山本太郎さんがおしゃべり会で「自民党の高市早苗さんが総理大臣になっても、野党側の玉木雄一郎さんや斉藤鉄夫さんが総理大臣になっても、全然変わらない」と言い続けるなら、共産党は「れいわとの差別化」を図る意味で、土壇場で「野党統一候補」に協力することを決断する可能性があります。
その場合には、「悪夢の結果」の実現に近づくことになります。
臨時国会首班指名選挙「決選投票」悪夢の結果
高市早苗:229票
斉藤鉄夫:227票
無効票:9票
それでもなお、れいわ新選組が「1回目も2回目も山本太郎と書く」と言い続け、麻生太郎さんの地元の福岡で、奥田芙美代さんが「野党統一候補と言っても茶番やから、首班指名選挙では1回目も2回目も山本太郎と書くけんね」と言い、大島九州男さんが「僕はここは柔軟に他の野党と協力すべきだ言ったんだけどねぇ、結局、1回目も2回目も山本太郎と書くことに決まっちゃったからねぇ」などと支持者に報告するなどすれば、麻生太郎さんは自信を持って石破総理を内閣総辞職させ、臨時国会で首班指名選挙に突入するはずです。
そうした状況を作ったうえで、このように投票するのです。
臨時国会首班指名選挙「決選投票」で政権交代のケース
斉藤鉄夫:236票
高市早苗:229票
「敵を欺くにはまず味方から」ということで、れいわ新選組が国会議員全体の話し合いでは「1回目も2回目も山本太郎と書く」という結論を出し、そのうえで山本太郎さんと9名の衆議院議員の計10名だけで極秘に会合を持って協議し、「参議院では1回目も2回目も山本太郎と書くが、衆議院では1回目は山本太郎、2回目は斉藤鉄夫と書く」と決めて、これを関係者10名だけの秘密として情報を漏らさずに首班指名選挙に臨めば、いわば「麻生太郎をハメる」ような形で政権交代を実現することができます。
共産党もれいわも首班指名選挙で「斉藤鉄夫」という名前を書くことには非常に大きなハードルがあると思いますが、まずは高市政権の誕生を阻止し、自民党政権に終止符を打つために、首班指名選挙では他の野党と協力することが重要で、実際に野党連立政権が発足することになったなら「閣外非協力」というような方針を打ち出して、「自民党政権にも協力できないが、公明党政権にも協力できない」というようなスタンスで臨めばよいのではないかと思います。
果たして、「政権交代」が私の脳内だけの妄想で終わるのか、それとも現実化するのか、来週の国会の動きから目が離せません。
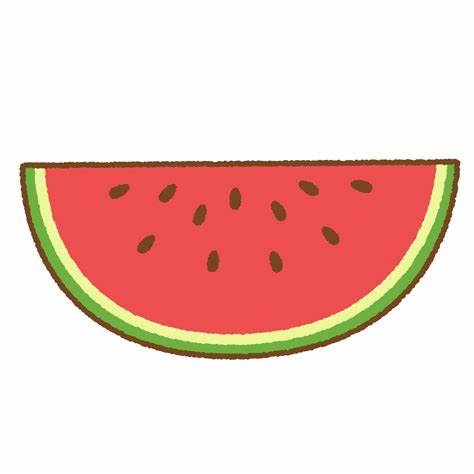
憲法9条変えさせないよ
プロ野球好きのただのオジサンが、冗談で「巨人ファーストの会」の話を「SAMEJIMA TIMES」にコメント投稿したことがきっかけで、ひょんなことから「筆者同盟」に加わることに。「憲法9条を次世代に」という一民間人の視点で、立憲野党とそれを支持するなかまたちに、叱咤激励と斬新な提案を届けます。

