◆ パレスチナは「世界の解放闘争震源地」
「今、あたたはホロコストがどのように起こったか理解できる」
そんなSNSの投稿に、ハッとさせられました。これは「どのようにホロコストが起きたか?」「なぜホロコストが起きたか?」という2つの投げかけが含まれているように思います。そして、教えられてきた歴史がどの方角に向いているのか、ということも考えさせられます。
さらに、世界がどのような方向に進むか、という分かれ道に立たされているとも感じます。言い換えると「抑圧する側」の思うようにさせるのか、させないのか、とも言えるでしょう。
ユダヤ系豪州人ジャーナリストのアントニーさんによると、イスラエルは、占領地であるパレスチナ地域を最新の兵器や監視技術の実験場として利用し、世界中の独裁国家や民主主義国家と呼ばれる国々にも輸出しています。これは、広く伝えられていない事実でしよう。そして米国を筆頭に多くの国々がイスラエルに軍事支援と援助をしています。
民主主義と呼ばれる国々も独裁的国家もさして変わらなく感じます。沈黙のうちに、世界で着々と抑圧のための準備が進められているのではないか…。イスラエルに制裁を課して、本気でパレスチナへの攻撃を止める国が無いのは、そのためではないか…と憶測します。
この連載で「最も世界で抑圧されているパレスチナの人々」について書いてきました。パレスチナは「世界の解放闘争震源地」とも呼ばれます。これは、レベルは違っても世界が少数の「抑圧する側(上)」から、多数の「抑圧される側(下)」に分けられ、「抑圧される側の解放」への連帯を呼び掛けでしょう。
繰り返し書いてきたことをまとめると…原住民として何世代もパレスチナで暮らしていたパレスチナ人は、違う種族(ユダヤ人)の外国からの大量入植で「原住民(パレスチナ人)への冷遇」、「外国からの入植者(ユダヤ人)優遇」政策により、土地を失い、多くの命を失っています。そして今パレスチナの人々の土地も人々も消えてしまいそうな状況です。
これを批判すると、「外国人差別」になるのでしょうか? イスラエルの人々はこれを「反ユダヤ」(差別)だと主張し、パレスチナの人々への差別的扱いを正当化し続けてきました。豪州、米国、カナダ、ニュージーランド、南米等の原住民にも同じことが起きました。それは現在も続いています。
日本を見ると外国勢力のために政治をしているように見える政治家が占める状況で、どんどん「国民冷遇」は強くすすめられ、日本人少子化を進め、どんどん移民を増やし、「外国人を優遇する政策」を始めた状況を見ると、「パレスチナのようにしてはいけない」という思いに駆られます。
パレスチナの状況を見ると陰謀論だと気楽には構えていられない…。レベルは違っても多くの国々で分断が起こされ、国が乱れて、監視が進み、表現の自由や人権が危惧されています。
そこで前回は「政治家ファースト→国民ファースト→みんなファースト」を書きました。
これは、外国人の人々を非難、差別するのではなく、「国民を守らず国民冷遇政策」を強化し続ける、「戦争をやめず難民を増やす」自分ファーストの政治家や官僚政治、支配層、言い換えると「抑圧する側」への非難です。
♦ シドニーでの歴史的、パレスチナへのデモ
豪州は祖国で、迫害されたり、差別されたり、危険から逃れたりした多種多様な外国人が集まり住む国です。一方で入植した外国人が原住民を迫害・差別してできた加害者の歴史も認識し背負っています。だから抑圧・差別・迫害というとこに敏感で反抗的な態度が備わっているのでしょう。
シドニーでは、8月3日日曜日、毎日流れる信じられないパレスチナの悲惨な光景を目の当たりにし、多くの人々は心を痛め、居ても立っても居られず、シドニーの象徴であるハーバー・ブリッチでパレスチナの人々のために抗議の声を上げ、行進するデモが企画され行われました。豪州史上最大のデモと言われます。(写真と詳細詳はこちら)
今、パレスチナの大惨事を、口先だけで、本気で止めようとしない政治家たちに、プレッシャーを掛け、止めさせなければ、取り返しがつかないことになる、という危機感を共有しているからでしょう。
真冬のどんよりした曇り空のシドニーで、悲しみや怒りのような激しい雨が降りしきる一日でした。危険が伴うため、周辺への外出を控える広報もありました。しかし、ひるむことなく長さ1.2㎞のハーバー・ブリッジからあふれる約30万人(主催者:パレスチナ・アクション・グループ発表)もの人々が集まり約6時間を掛けて橋をマーチしたのは、多くの驚きでした。これは豪州国内だけでなく、日本ではどうか分かりませんが、海外でも大きく取り上げられ報道されました。(その様子を伝える写真と動画)
そして、人々の目を奪ったのは、イギリスの刑務所での長い拘束から解放されたジャーナリストのアサンジさん(連載第32回)の姿でした。米国への強制送還が心配され、釈放されるかどうか、ハラハラしていた時期を考えれば、今再びアサンジさんが臆せずパレスチナ解放デモに参加している姿は、多くの人にパワーを与えました。彼はパレスチナの色、白のワイシャツ、赤いネクタイ、緑のハンカチを胸に飾り「ヒューマニティへの行進、ガザを救え」と書かれた先頭の横断幕の中心を握り、子どもたちや家族と共に行進をしました。(こちら動画)
そして、隣にはパレスチナ解放のスローガン「(ヨルダン)川から(地中)海まで、パレスチナは自由になる」をツイートしたことで、オーストラリア・シオニスト連盟から訴訟を起こされている元SBS(NHK相当)ジャーナリストのメアリーさんの姿がありました。このスローガンの意味は「パレスチナ人が祖国で他の人たちと同じように平等、自由、尊厳を持って暮らす権利」を訴えるもので、当たり前のようですが、イスラエルでは「反ユダヤ主義のスローガンだ」で不快だと捉えられます。
例えばイスラエルのネタニヤフ首相の属するるリクード党の最初の党綱領には、「地中海とヨルダン川の間にはイスラエルの主権のみが存在する」と記され、また、パレスチナ国家の樹立は「ユダヤ人の安全を脅かす」ものであり、「イスラエル国家の存在を危うくする」と明記していました。ここからも、パレスチナ全土をイスラエルにするという意思が伺えます。
メアリーさんを支持・支援する「メアリーと共に立つ StandWithMary」が、「ジャーナリズムに強さをKeep Journalism Strong」というスローガンと共に立ち上げられ、裁判の行方が注目されます。
親パレスチナのツイートをしたため、豪州ABC(NHK相当)を解雇され、不当解雇として裁判で勝利したアントネットさんの姿もありました。(メアリーさんが投稿した、アサンジさんとアントネットさんの再会の写真)
この3人の親パレスチナ豪州人ジャーナリストたちは、真実を伝えたことで、制裁を受けていますが、それに屈することなく、「ガザを救え」のマーチの先頭に立っていたことは、「抑圧される側」の人々にとって、心強いことでした。(詳しくはこちら)
◆ ガザの人々との繋がり
そして、この行進を主催したリーズさん(Josh Lees)は、ガザの人々からの連絡で「ガザの人々が『シドニーの最高のデモ行進』を見ている。応呼している」ということを発表し、ガザの人々から感謝のメッセージも寄せられて、さらに支援の勢いをさらに高めたいと強く語りました。
ガザで暮らす少女ミラさんが笑顔で、「シドニのハーバー・ブリッジでパレスチナのために抗議に参加してくれた皆さん、ありがとう」という手書きのポスターを持った写真が、父親のモハマッドさんから送られたという報道がありました。(写真と詳細はこちら)
ガザで家族を助けながら暮らすタマーさんの次のような投稿が紹介されました。
「両親に私たちの声に耳を傾け、この状況を気にかけてくれる人々がまだいるということを説明するのは大変でした。特に、世界から忘れ去られたように感じさせられる中ではなおさらです。しかし今日…何かが変わりました。シドニーで行われた大規模な抗議活動を見せました。この寒い雨の中、人々が私たちのために、正義のために、真実のためにと叫ぶ姿を、私たちは一緒に見守りました。そして、両親の目に、長い間失われていた何かが見えました…ほんの少しではありますが、希望が戻ってくるのが見えました。ありがとうございました。皆さんの尽力は無駄ではありませんでした。言葉では言い表せないものです」
強く生活していても、彼のX(ツイッター)からは、やせ細った身体の写真が厳し生活を表していました。
◆ 私たちは皆パレスチナ人だ(We are all Parestines)
このデモ行進では定番の「Free Parestineパレスチナを解放せよ」と共に「We are all Parestines 我々はみんなパレスチナ人だ」という声も響いていました。
今回の参加者の特徴は、多様性でした。ベビーカーに赤ん坊を乗せて歩く母親、小さなん子どもたちと参加する家族、孫と見られる子どもたちと歩く年配の人々、多種多様な人種。
「ガザで多くの赤ん坊や子どもたちが飢えたり、命を失っていることは耐えられません。この子たちがもしそのような目にあったら…。そのための抗議としても参加しました」という声が伝えられました。
パレスチナへのデモでは、オーストラリアの原住民アボリジナルの人々や旗もよく目にします。それは、豪州で抑圧られている人々の象徴で、忘れてはいけない、「連帯」しようというメッセージのように見えます。両方の旗を示し「偽善だ。原住民に謝罪した後に、民族浄化を繰り返している」と書かれたポスターが目を引きました。
十字架の首飾りをし、ケフィエ(Keffiyeh:パレスチナの伝統的スカーフ)を巻いた男性の「ユダヤ教・イスラム教・キリスト教どんな宗教も関係ない、人々の命が掛かっているんだ。そのためにここに来て声を上げている」という声もありました。中東での、キリストの教えに忠実な伝統的キリスト教の人々が暴力的に迫害されている報道があります。
「私は豪州人ではありません。イスラエル人だけどここに来てデモに参加してる」という女性もいました。
前述したユダヤ系豪州人ジャーナリストのアントニーさんは、「ユダヤ人=シオニストではない」ことを強調します。そしてイスラエルのシオニスト政権で、シオニストではない世界に散らばるユダヤ人の人々が反ユダヤ主義の犠牲になり、穏やかで、安全な生活を脅かされていると訴えます。
抗議のマーチでアントニーさんは「予想できいほどの聴衆を見てください。我々は今、多数派だ。私は、民族浄化や戦争犯罪を含まないユダヤの価値観を説明し、支持することを誇りに思ってきた。当たり前のことのように思えるかもしれないが、恥ずべきことに、あまりにも多くのユダヤ人が依然として日々パレスチナ人を非人間化している。これは変えなければならない。パレスチナにおけるジェノサイドと飢餓を終わらせる唯一の方法は、制裁とボイコット、そして投資撤退によってイスラエルを孤立させることだ。政府は、即刻イスラエルに制裁を!」と伝えました。
「私たちは皆、パレスチナ人だの意味は?」
これの短いフレーズは何を意味するのでしょうか?
パラナイさんのコラムを日本やオーストラリアでの状況を交えて紹介したいと思います。
「私たちは皆、パレスチナ人だ」という言葉にこれほど力強いのは、私たちは単にパレスチナに「支持する」のではなく、私たちはパレスチナ「そのもの」なのです。私たちはパレスチナ人のように、過激な暴力や食料難に置かれていませんが、世界には、少ない何兆円長者がいるのに、食べるものにも困る人々がいます。まず、これはなぜでしょう。
Nortonさん(連載第44回)は、「労働者(グローバル・マジョリティ)を低賃金で国際分業の底辺に永久に従属させ、閉じ込めておくためなのだ。彼らは、国際的な分業が西側の1000億万長者(間もなく1兆万長者になる)の寡頭政治家によって決定されることを切望している」と説明します。「抑圧する側」から弾き出された庶民・労働者は、レベルは違っても「パレスチナ人だ」と言う事でしょう。
どうやって「私たちは皆パレスチナ人だ」を実現できるのか?
パレスチナ人、詩人でジャーナリストのモハメド・エル=クルドさんは「私たちは皆パレスチナ人だ。というスローガンは、比喩を捨て、実質的に表現されなければならない」「つまり、パレスチナ人であろうとなかろうと、私たち皆が、パレスチナ人の状況、抵抗と拒絶の状況を、私たちの生活や付き合う人々の中で体現しなければならない」と伝えました。
エル=クルドさんは、帝国(世界支配を目指す勢力)の無数のシステムと理論(詳しくは連載第44回)は、「『抑圧された者』の暴力を非難し、『抑圧する側』の暴力には目をつぶる植民地主義の論理」に正面から対峙できる真の革命的政治がなければ、これらの言葉の根本的な意味は空洞化し、その重みを単なる象徴的なものにまで低下させ、最終的にはその過程でパレスチナの大義を裏切ることになる危険がある、と指摘します。
しかし、もし私たちがこの困難を乗り越え、この「連帯」を単なる象徴ではなく実質的な形で表現することができれば、つまり、エル=クルドさんが言う「パレスチナ人の抵抗と拒絶の条件」を真に体現することができれば、その意味は計り知れないものとなるでしょう。しかし、そのためには、私たち全員が、ラディカルな連帯が真に何を意味するのか、そして近年ますます広まっている、「より弱く、よりリベラルな概念」とは何が違うのかを、具体的かつ規律ある分析によって改めて認識し直すための、継続的な努力が不可欠です。
連帯VS 同盟
リベラルな社会正義論者の間で広まった、関連性はあるものの根本的に異なる「同盟関係」という枠組みと対比させるのが分かりやすいでしょう。「連帯」と「同盟関係」の重要な違いは、連帯が「闘争」を重視する点で、同盟は「アイデンティティ」を重視することです。「同盟」関係が真に急進的な政治の基盤となり得ない理由は、アイデンティティを隔てる境界を越えようと努める一方で、実は暗黙のうちに違いを強調するため、必然的にそれらの違いを強化してしまうからです。
「連帯」は、闘いを共にすることから生まれる結束を重視することで、こうした境界を完全に排除する。言い換えれば、「同盟」関係が「あなたと私は違うが、それでも私はあなたと共にいる」と言うのに対し、「連帯」は「あなたと私は一つであり、だから私たちは共にいる」という認識です。単なる比喩や空虚なレトリックではなく「集団的な認識と抵抗」に基づく「連帯」です。
日本を見ると、日本人は集団行動に優れている、と言われます。同じ目標を達成するために、協力し戦後も世界から驚かれる成果を残しました。一方で同調圧力が強く、間違っていても声を上げることが難しく、従順に従うという状況にもなります。例えば、日本では統一教会系の宗教、公明党の創価学会、政治では政党に所属していれば、「自分は違う」と思っても、その決断に従わなければいけない。そうしないと、「排除される」という圧力がかかります。そうなると、「抑圧される側」であっても「抑圧する側」の味方になってしまう。これらの、枠組みを取っ払った、「抑圧される側」の闘争という、「連帯」に変化し作られるとどうでしょう。
シドニーの歴史的ハーバー・ブリッジの抗議のマーチは、まさにそのような「連帯」でした。政権与党の労働党は、野党第一党よりもリベラルで、より親パレスチナでした。しかし、このマーチには、「危険が伴う」というまるで、帝国主義的なロジックで、否定的でした。イスラエル・シオニスト関係の力が働いているのでしょう。首相も州知事も「パレスチナの人々、私たちのことなど気に留めていない」と批判が噴出しました。開催される一日前に、裁判所が「マーチは許可されなくてはいけない」という判決を出し、党の判断に背いて、マーチに参加する労働党議員たちが注目されました。だからと言って、党から処罰されることはありませんでした。
外国勢力に従順な政治から、国の独立自尊への政治システムへ変革を起したのは、民衆の力のイラン革命を起こしたイランでした。そして、西側諸国が「悪」だと呼んでいるのを耳にします。ベトナムもアメリカとの戦争に勝ちました。
抑圧する側とは?
パレスチナ連帯運動「私たちは皆パレスチナ人だ」の広い反帝国主義分析をすると、ガザからハイチ、コンゴ、スーダン、そしてそれ以外の地域に至るまで、世界中で起きるあらゆる大量暴力と不正行為に共通する要素は、帝国主義的世界システムに内在する「暴力と不平等」であるという認識です。事実は、この帝国主義的世界システムがパレスチナにおけるシオニストの植民地化と分かちがたく結びついているということです。そして、現状は世界の国々、日本や西側諸国、非西側諸国ともに、その状況の中に縛られているようです。
1917年のバルフォア宣言において、イギリス(大英帝国)は中東における足場を維持する手段としてシオニスト運動(イスラエル建国と拡大)を公式に承認しました。シオニスト計画は常に、世界で最も熾烈な争いが繰り広げられ、地政学的に重要な地域の一つにおける帝国主義的利益の最重要拠点として機能してきました。
この計画が衰えることなく続く限り、帝国の実権を握る者たち(抑圧する側)…国家リーダーたちであれ巨大企業関連の幹部であれ、自らの帝国覇権が揺るぎないという確信のもと、安泰と安穏で過ごせるでしょう。 だから、パレスチナ解放闘争の勝利が訪れる時、それは必ずや訪れると私は確信しています。そして、世界帝国というシステムが煽る、あらゆる形態の不正と抑圧に終焉の鐘を鳴らすことになるでしょう。
世界の解放闘争震源地パレスチナ
医師であり革命指導者でもあったジョージ・ハバシュによって1967年に設立されたパレスチナ解放人民戦線(PFLP)は、その「パレスチナ解放戦略」の中で、パレスチナ解放闘争の究極の敵はイスラエル国家だけでなく、世界的なシオニスト運動でさえなく、実際は世界帝国主義のシステム全体に他ならないという重要な点を繰り返し強調しています。
PFLPは、「帝国主義はこの地域で最良の立場にあり…イスラエルは帝国主義がその存在を守り、我々の土地における権益を守るために利用する勢力および拠点となっている」ため、「パレスチナ解放闘争は、世界の他のあらゆる解放闘争と同様に、世界帝国主義に対する闘争となる」と説きます。
言い換えれば、「私たちは皆パレスチナ人だ」と言う時、真に言いたいのは、私たち皆が同じ大きな「反帝国主義闘争」の参加者であるということです。
今日、この闘争の最も目に見える戦場は「自由なパレスチナを求める闘い」かもしれませんが、その影響は実際にはパレスチナをはるかに超え、世界中のあらゆる正義と解放を求める運動に関わり、それらを結びつけています。ですから、この事実を認めることは、「連帯」の真の意味を第一に優先し尊重すること、つまり、偏狭な考え方や些細な分裂を避け、どこにいても、「連帯」された革命的な全体の一部として自らの立場を認識することです。
以上がパラナイさんのコラムの主要な紹介です。
生存や命の危機が差し迫った状況では、「抑圧される側」は、命にかかわらない事、例えば宗教やアイデンティテイ、貧富の差を超えた裕福層の人々も生き残りをかけて、団結します。生存権や人権はお金では買えないし、ガザのような食料不足では、お金は意味をうしなっています。日本では重税・年金の削減・物価高等で、また勤勉な日本人は、長時間労働や日々の生活で、多くはこのような事を見たり、考えたりする時間も余裕も無いでしょう。これらの人々に、この差し迫った世界で広がる「抑圧する側」に対峙する「連帯」の輪が広がれば、何か変化がきっと起こるはずだと、この歴史的行進デモを振り返りながら思いを巡らします。
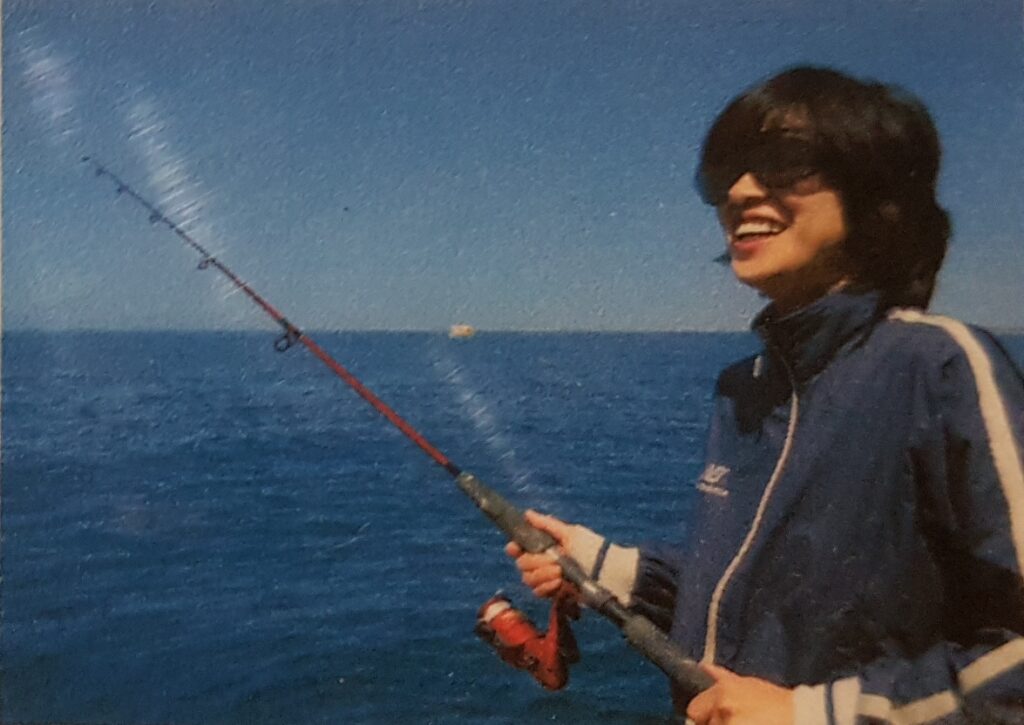
今滝 美紀(Miki Imataki) オーストラリア在住。 シドニー大学教育学修士、シドニー工科大学外国語教授過程終了。中学校保健体育教員、小学校教員、日本語教師等を経て早期退職。ジェネレーションX. 誰もがもっと楽しく生きやすい社会になるはず。オーストラリアから政治やあれこれを雑多にお届けします。写真は、ホストファミリーとグレートオーストラリアン湾の沖合で釣りをした思い出です。

