※この連載はSAMEJIMA TIMESの筆者同盟に参加するハンドルネーム「憲法9条変えさせないよ」さんが執筆しています。
<目次>
0.経済本読書のすすめ
1.高度経済成長は「単なる偶然」だった
2.所得倍増計画は「経済の成長戦略」ではなく「果実の分配計画」だった
3.バブル崩壊後は、どの政権でも「低成長」
4.日本は「製造業大国ドイツ」にはなれない
5.「1億人の国内消費」を喚起するには?
6.野党は「21世紀の所得倍増計画」を作れ
7.トピックス①:2023年10月26日「政権交代を実現する会」結成大会
8.トピックス②:「TONIKAKU」フランスへ行く
0.経済本読書のすすめ
読書の秋におすすめの「経済本」を3冊ご紹介するシリーズの第3回、今回ご紹介する本は、加谷珪一(著)『縮小ニッポンの再興戦略』(発行:マガジンハウス、印刷・製本:中央精版印刷、2022年)です。
内容に入る前に、はじめに前回と前々回の記事のURLを貼っておきます。
1. 高度経済成長は「単なる偶然」だった
加谷珪一さんは『縮小ニッポンの再興戦略』の中で、日本の高度経済成長が「朝鮮戦争による特需景気」と「中国の国共内戦・大躍進の失敗・文化大革命による混乱」という2つの外生的な要素がもたらした偶然の産物であったという見解を示しています。
本来であれば、日本も外国から巨額の借入れを行い、高い金利を支払いつつ、外国資本に金融を左右されるという不安定な状況で経済を再生させる必要がありました。ところが日本経済は偶然にもある時期からそうした状況は無縁となり、借金に頼ることなく外貨を獲得し、これを使って一気に成長を実現できたのです。その偶然というのは「朝鮮戦争」です。
(中略)
朝鮮特需の勢いはすさまじく、戦争が始まった翌月には早くもトヨタ自動車に大量のトラック注文が入りました。各社は増産に追われることになり、日本経済は一気に息を吹き返したのです。
あらためて数字で検証すると朝鮮特需の巨大さが分かります。
一連の特需では、1950年から1952年の3年間に10億ドルを上回る発注が日本企業に対して行われました。1ドル=360円とすると、3年間で3600億円、1年あたりでは1200億円となります。朝鮮戦争前年の日本のGDPは3.5兆円程度しかなく、GDPの3.4%に相当する発注が米軍から一気に出された計算になります。
企業は増産に追われましたから、設備投資が爆発的に増加し、あらゆる業界が好景気に沸きました。1951年の名目GDPは前年比で何とプラス38%となり、翌1952年はプラス12%、1953年はプラス15%となりました。この数字は高度成長期の中国をはるかに上回る水準であり、特需の影響のすさまじさを物語っています。
(中略)
朝鮮特需の効果はそれだけにとどまりません。ドルという貴重な外貨を大量に獲得することができたからです。特需のほとんどは米軍からの発注ですから、支払いは基本的にドルになります。今の日本では想像もできないことですが、経済が破綻した国にとって外貨というのはダイヤモンドよりも貴重な資産です。
(中略)
ゼロから成長する国が必ず直面する外貨の確保という大問題が、朝鮮特需によって魔法のように解決し、日本はこの資金をベースに一気に高度成長の波に乗ることができたのです。
加谷珪一さんは、「『朝鮮戦争』がもたらした特需景気による大量の外貨獲得」と「近代工業化の競争相手としての『中国』の不在」という2つの偶然が戦後日本の高度経済成長をもたらしたのだとして、中国の戦後史についても記述しています。
戦後の高度成長には、実はもうひとつの偶然が作用しています。それは中国の存在です。
中国は日中戦争に勝利したものの、その後、国民党と共産党による内戦が勃発。1949年に共産党が中華人民共和国の樹立を宣言するまで内戦は続きました。
終戦後の大事な時期に内戦に明け暮れたことで、中国は近代工業化に大きく出遅れる結果となったのです。朝鮮戦争の終結後、中国は毛沢東氏が主導して第二次5ヵ年計画(いわゆる大躍進)を立案。社会主義的な手法を駆使して工業生産力の増大を試みましたが、この計画も失敗に終わりました。
(中略)
中国は大躍進政策の失敗をきっかけに、壮絶な権力闘争である文化大革命が勃発しましたから、さらに経済を疲弊させる結果となりました。鄧小平氏による改革開放路線がスタートする1970年代後半まで、日本にとって圧倒的に有利な状況が続いたわけです。
もし国共内戦や大躍進の失敗、文化大革命がなければ、日本は中国と直接競争しなければならず、日本経済の姿はまったく違うものになっていた可能性が高いでしょう。
2.所得倍増計画は「経済の成長戦略」ではなく「果実の分配計画」だった
戦後日本が達成した高度経済成長は日本人にとって誇りであり、当時の大蔵省による財政政策、日銀による金融政策、通産省による産業政策、そしてそれらを有機的に統合した自民党の経済政策が有効に機能した結果であると一般には考えられています。
しかし、自民党の池田隼人内閣が1960年に打ち出した「所得倍増計画」の内容を加谷珪一さんが分析したところ、実際には「経済の成長戦略」として見るべきものはほとんどなかったのだというのです。
池田内閣は具体的にどのような施策でこの成長を実現したのでしょうか。実を言うと、その問いに対する明確な答えは存在していません。なぜなら、所得倍増計画というのは、実は後付けの政策に過ぎないからです。
当時の日本経済は自律的な高成長が続いており、10年間で所得が2倍になることは、計画策定時点においてほぼ確実という情勢でした。所得倍増計画の本文を見ても、大半が現状分析にとどまっており、特筆すべき施策が盛り込まれているわけではないのです。
しかも、政府が民間の邪魔をしないよう過度な介入を控え、民間の自発的な経済活動を促進させるといった提言まで行われていました。要するに、所得は勝手に倍増するのだから、政府は余計なことをしなければそれでよし、という話です。所得倍増計画で所得が2倍になったのではなく、所得が2倍になることがほぼ確実だったので、池田氏は堂々と所得倍増計画を表明することができました。
加谷珪一さんの指摘によれば、「所得倍増計画」の焦点は、「経済」というよりは「政治」という側面が強かったのだというのです。
閣議決定された所得倍増計画には、「所得倍増計画の構想」という別紙があり、実はこの別紙が非常に重要な意味を持っているのです。別紙には、所得倍増計画とは別に、農業近代化、中小企業近代化、後進地域の開発促進、公共事業の地域別分配の再検討といった項目が並んでいました。
戦後の国内政治についてある程度、知見を持っている読者の方であれば、これが何を意味しているのかピンと来たのではないでしょうか。ここで示された各項目は、予算の重点配分リストであり、自民党における権力基盤そのものと言い換えることができます。所得倍増計画には、高度成長によって生まれた豊富な財源を多くの利害関係者にバラ撒くことで、自身の政権基盤を強化するという明確な目的があったのです。
視点を変えて見ると、所得倍増計画というのは、極めて政治的かつ野心的な取り組みだったことが分かります。
この「所得倍増計画」による果実の分配と、それによって生み出された「神話」は、今に至るまで自民党の政権基盤を極めて強固に形成しており、そうした意味で「政治的かつ野心的な取り組みだった」ことは間違いありません。
3.バブル崩壊後は、どの政権でも「低成長」
バブル崩壊後の日本経済について、加谷珪一さんは、一言で「どの政権でも低成長」だと評し、わかりやすくまとめています。
各政権の経済政策の特徴
| 政権名 | 時期 | 平均成長率 | キーワード | 経済理論 |
| 橋本・小渕政権 | 1996年1月~ 2000年4月 | 0.9% | 公共事業を中心としたケインズ型の財政政策 | |
| 小泉政権 | 2001年4月~ 2006年9月 | 1.0% | 構造改革 | サプライサイドの経済政策 |
| 民主党政権 | 2009年9月~ 2012年12月 | 1.5% | コンクリートから人へ | |
| 安倍政権 | 2012年12月~ 2020年6月 | 0.9% | デフレ脱却 | 量的緩和策(金融政策) |
(出所)加谷珪一氏作成の表に本文記載の平均成長率を筆者が追記
それぞれの政権の経済政策の特徴に関して、加谷珪一さんは次のように述べています。
橋本・小渕内閣は公共事業を中心とした大規模な財政支出を実施していましたから、典型的なケインズ型の財政政策と捉えることができます。一方、結果的に量的緩和策の一本足打法となったアベノミクスは金融政策そのものであり、小泉構造改革は明確な経済理論とは言い難い面がありますが、あえて分類すれば、サプライサイドの経済政策とみなすことができるでしょう。そして民主党はマクロ経済について目立った政策を実施しませんでしたから、民間経済に任せた状態と判断できます。
(中略)
客観的に分析すれば、アベノミクスはうまくいかなかったという結論にならざるを得ないわけですが、筆者(注:加谷珪一氏)が問題視しているのはアベノミクスの成長率が低いことではありません。確かに、数字では最下位かもしれませんが、どの政権も低成長であり、十分な成長を実現できなかったという点では同じだからです。
むしろ、すべての政権において十分な成長を実現できなかったという事実こそが、経済学的に見て非常に興味深い出来事であると筆者(注:加谷珪一氏)は考えており、これが本書の主要なテーマでもあります。
4.日本は「製造業大国ドイツ」にはなれない
加谷珪一さんは『縮小ニッポンの再興戦略』の「第4章 日本は製造業大国ドイツになれるのか?」において、「第4章では、日本は製造業の輸出を復活させるべきなのか、それは可能なのか、製造業大国の地位を維持しているドイツを例に分析していきます。」として、日本企業とドイツ企業を比較し、次のような議論を展開しています。
ビジネスにおけるシンプルな理屈として、市場が伸びている分野に特化すれば、需要が供給を上回るので、価格低下を回避できます。一方で、市場が飽和している分野は、過当競争となり値引き要求が厳しくなります。マクロ的に見て、伸びている分野に特化するというのは、価格低下を回避するもっとも効果的な戦略のひとつと言えます。
ドイツ企業はこうしたビジネスにおける基本原則に忠実です。
(中略)
新興国と勝負するには、付加価値を上げ、新興国では作れない製品を販売する必要がありますが、こうした製品の単価は高く設定できます。
ドイツの単価が高いということは、日本と比較してより必要性の高い製品に特化できていることを示しています。
ドイツには、いわゆる大手メーカーに加えて、ニッチな分野において高いブランド力を持つ中堅メーカーが数多く存在しています。
日本でもよく知られているところでは、庭などの清掃に使われる高圧洗浄機を製造するケルヒャーといった企業です。
ケルヒャーは非上場の企業で売上高も3500億円程度ですが、高圧洗浄機に特化した製品戦略で大成功しています。
近年は同社の洗浄機を参考にした低価格商品もたくさん登場していますが、同社製品には高いブランド力があるため、あまり値崩れしません。ドイツはシーメンスやバイエルといったグローバルな巨大企業に加え、ケルヒャーのような高付加価値企業が多いため、効率のよいモノ作りが実現できているのです。
加えてドイツではさらに規模の小さい中小企業の経営も活発です。
日本では人口1000万人あたり28万の事業者が存在していますが、米国は24万しかありません。一方、ドイツにおける人口1000万人あたりの事業者数は42万と日本よりはるかに多い数字です。ドイツには中小企業が多いことが分かりますが、中小企業の生産性は高く、こうした企業が果敢に新しい産業に挑んでいます。
日本では中小企業のほとんどが大手企業の下請けとなっており、元請けの大手企業から厳しい値引き要求を受け、利益を上げることが難しい体質です。ドイツには重層的な下請け構造は見当たらず、中小企業は独自の製品戦略・価格戦略で勝負しますから、利益率において大手と大差はありません。
このような議論をふまえたうえで、加谷珪一さんは次のように結論しています。
日本人は交渉の場において「こちらの立場をご理解いただく」という言い回しを連発する傾向が顕著です。言葉遣いだけは丁寧ですが、主張している内容は「1ミリも妥協しない」というものにしかなっていません。これでは交渉にはなりませんし、かえって相手を怒らせる結果となりますが、当の本人にその意識はまったくないことがほとんどです。交渉というのは情報で決まるのではなく、現実的な駆け引きです。ドイツ人は言い方こそ無骨かもしれませんが、自身の言動によって相手がどのような感情を持つのか理解しており、双方が納得できるプランを積極的に提案するなど、問題(注:貿易摩擦の問題)が深刻化する前に手を打っていたのです。
安価な工業製品の大量生産時代ならいざ知らず、製造業において高度なソリューションビジネスを行うためには、こうした戦略性が極めて重要な意味を持ちます。ドイツ人が英語教育に力を入れていることの背景にはこうした事情があると考えられますから、単に語学を勉強すればよいという話ではないことがお分かりいただけるでしょう。
一連のドイツの取り組みから分かるように、製造業大国としての地位を維持するというのは、並大抵のことではありません。
ドイツは、経営者にも労働者にも厳しい社会、つまり自分に厳しく、他人にも厳しい社会をあえて作り上げ、時代の変化に対応できるよう国家をあげて取り組んできました。
多くの国民が英語やITに取り組み、会社の管理職や経営陣は常に業績を上げるようプレッシャーをかけられます。生産性の向上は絶対ですから、ドイツでは長時間残業は恥であり、短時間の労働で高い利益をあげることが強く求められます。長時間労働で私生活を犠牲にさえすれば、とりあえず許される日本とは異なり、他人から厳しく評価される社会と考えてよいでしょう。
(中略)
一度、失ってしまった技術を復活させるのは想像以上に難しく、ましてや技術を維持するだけでも過酷な道が待っています。「製造業を復活させよ!」と勇ましく主張するのは、その場では心地よいことかもしれませんが現実は違います。本当に社会全体としてドイツのような施策をやり抜く覚悟があるのか、私たちは自身について問い直す必要があるでしょう。
ちなみに、日本は2023年のGDPでドイツに抜かれて世界4位に転落する見込みだという予測が出ています。
5.「1億人の国内消費」を喚起するには?
加谷珪一さんは『縮小ニッポンの再興戦略』の最終章で、日本経済の再興に向けて、次のような提言をしています。
第4章では、製造業が高い競争力を維持し続けるのは簡単ではなく、日本においてドイツのような取り組みを継続的に実施するのは難しいという話をしました。(中略)
日本は輸出主導型経済ではありますが、一方で国内には1億人の豊かな消費市場が存在しています。そして国内に存在しているこの消費市場こそが、偶然によって日本人が獲得した、もっとも価値の高い資産です。
(中略)
以前に工業化を達成し、社会に分厚い資本蓄積がある国は、工業競争力が低下しても、国内消費を軸に成長を持続することができます。消費主導で経済を回すという行為は、まさに豊かな先進国の特権と言ってもよいものです。
日本は奇跡的にこの特権を得ることができましたから、国民がその気になれば、米国や英国と同様、国内の消費市場を活用することで、輸出に頼ることなく経済を回すことが可能です。
(中略)
一連の状況を総合的に判断すると、日本は製造業依存から脱却し、消費主導で経済成長できる体制に移行した方が合理的です。しかしながら、国内消費主導で経済を回すためには、どうしても解決しなければならない課題があります。その内容は多岐にわたりますが、大枠としては以下の3つに集約できるでしょう。
①消費低迷の原因となる将来不安を払拭すること
②生産性向上のカギを握るIT投資を強化すること
③経常収支の悪化に対応できるよう投資環境を整備すること
これらの3つの課題のうち最も重要だと思われる「将来不安の払拭」の問題について、加谷珪一さんは次のように述べています。
日本における将来不安の中でもっとも大きいのは、何度も指摘しているように年金・医療などの社会保障制度であることはほぼ明らかです。公的年金制度の持続可能性がどの程度あるのか客観性のある試算を行い、悪い結果であっても、政府は国民に正しい情報を告知する必要があるでしょう。
消費者がもっとも嫌うのは悪い将来予想ではなく、不確実性が高いことや、情報を信頼できないことです。こうした部分を払拭するだけでも、消費マインドは大きく変わります。
(中略)
年金制度に加えて、将来不安として大きいのは雇用環境です。
(中略)
多くの国民が雇用流動化を極度に恐れているのは、ひとたび会社を離れると、再就職が極めて難しくなるとイメージされているからです。こうした状況下において、転職活動をスムーズに進めるためには、社会全体として転職者の生活とスキルアップを支援する体制が必要です。
(中略)
このほか、男女間の賃金格差や非正規社員と正社員の身分格差、先進国では最低水準となっている劣悪な子育て環境の改善、隷属的な下請け体制の解消や、硬直化した流通システムに代表される非効率的な商習慣の見直しなど、早急な改善が必要と指摘された課題のほとんどが手つかずの状況です。こうした悪しき社会習慣を温存させたままでは、決して消費者の不安心理は解消しません。
ここで指摘されていることは、まさに「政治」の問題であり、これから私たちがどのような「政治」を作り出してこれを解決していくのか(あるいは、そのような「政治」が作り出せずにこのまま沈んでいくのか)が問われているのではないでしょうか。
6.野党は「21世紀の所得倍増計画」を作れ
ここからは加谷珪一さんによる議論ではなく私独自の提言になりますが、野党は一日も早く「21世紀の所得倍増計画」を作るべきなのではないかと思います。
それは、池田内閣による「10年間で所得倍増」という「昭和の『所得倍増計画』」でもなく、岸田内閣による「新しい資本主義」という「令和の『(資産)所得倍増計画』」でもない、「2100年までを見通した長期的な『21世紀の所得倍増計画』」であるべきです。
経済の問題は難しく考えられがちですが、毎年1%成長できると仮定すれば70年で所得倍増し、毎年2%成長できると仮定すれば35年で所得倍増し、毎年3%成長できると仮定すれば24年で所得倍増が達成できる計算になります。
「30年間実質経済成長ゼロ」というバブル崩壊後の日本経済は、実は相当異常で、本当に有り得ない話です。
それが現実に起きてしまっていることが大問題なのです。
そこで、思い切って、70年以上先を見通した「2100年」を目標年限とした長期計画を立てるべきなのではないでしょうか。
「21世紀の所得倍増計画」(2100年日本経済実現プラン)
達成目標①:GDP1,200兆円(2100年目標)
達成目標②:国債発行残高1,200兆円(2100年目標)
達成目標③:人口1億2,000万人(2100年目標)
達成目標④:原発ゼロ(2100年目標)
達成目標⑤:二酸化炭素排出量実質ゼロ(国際公約のため、これのみ2050年目標)
これらの目標のうち、「2100年までにGDP1,200兆円を達成する」という目標は、「平均成長率1%未満」でも達成できる極めて現実的な目標であり、「これを実際に何年程度(あるいは何十年程度)前倒しして実現できるのか」を焦点とすべき低い目標設定です。
この「実現可能な長期計画」を策定したうえで、10年ターム、あるいは20年タームの「中期計画」を立てて、経済政策を実行していけばよいのではないでしょうか。
ちなみに、これらの目標のうち「2100年までに原発ゼロ」という話は「悠長すぎる」とお怒りの方も多々おられるでしょうが、「今を生きる人々の面子やおカネの話」という側面を無視して脱原発を進めていくことは極めて難しいものと思いますので、まずは長期的な方向性を決めたうえで、「それを何十年ぐらい前倒しして実現できるか」ということに注力していくべきなのではないかと個人的には考えています。
これらの目標の中で最も達成が困難なのではないかと考えられるのが「人口1億2,000万人」という数字で、実際には少子化が進み、この半分程度の人口規模の数値に陥る可能性が高いのではないかと考えられています。
経済規模にしろ、人口規模にしろ、「西暦2100年の日本」の姿をどのようなものにすべきと考えるのか、「国家100年の大計」に思いをめぐらせることは、今後の日本の政治の方向性を検討していくにあたって、非常に重要なのではないでしょうか。
7.トピックス①:2023年10月26日「政権交代を実現する会」結成大会
10月26日(木曜日)に「政権交代を実現する会」の結成大会が行われました。
8.トピックス②:「TONIKAKU」フランスへ行く
イギリス人を沸かせた「TONIKAKU」(とにかく明るい安村)さんが、今度はフランスのゴット・タレントに出演しました。
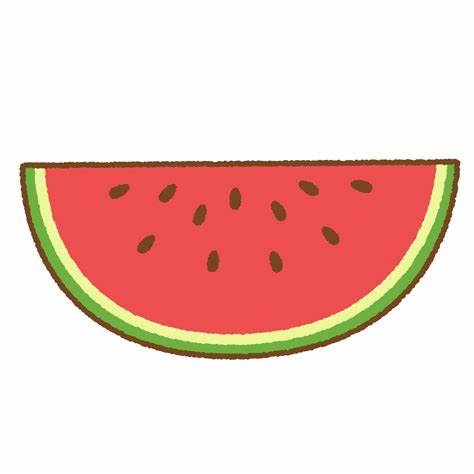
憲法9条変えさせないよ
プロ野球好きのただのオジサンが、冗談で「巨人ファーストの会」の話を「SAMEJIMA TIMES」にコメント投稿したことがきっかけで、ひょんなことから「筆者同盟」に加わることに。「憲法9条を次世代に」という一民間人の視点で、立憲野党とそれを支持するなかまたちに、叱咤激励と斬新な提案を届けます。

