※この連載はSAMEJIMA TIMESの筆者同盟に参加するハンドルネーム「憲法9条変えさせないよ」さんが執筆しています。
<目次>
1.「救民内閣構想プランB」の3人の総理候補リレー
2.政治家「山本太郎」への期待
3.「脱原発」を実現できるか
4.「ロスジェネ」を救えるか
5.「消費税廃止」を実現できるか
6.そして「メロリンQ」
7.トピックス①:「トランプ関税」の衝撃
8.トピックス②:地獄の「大阪・関西万博」開幕
1.「救民内閣構想プランB」の3人の総理候補リレー
今日は、「救民内閣構想プランB」を考える論考の4回目です。
森永卓郎さんと泉房穂さんの対談本『ザイム真理教と闘う!救民内閣構想』で泉房穂さんが「確実に今の政治状況を根本から変えるためには、総理候補は1人では足らない。最低3人いると思っています。」と語ったことに触発されて、私個人の発想として「長嶋巨人『10.8決戦』の3人の投手リレー」を彷彿とさせる「『救民内閣構想プランB』の3人の総理候補リレー」を構想しました。
長嶋巨人「10.8決戦」投手リレー
| 投手 | 投球イニング | 失点 | |
| 先発投手 | 槙原寛己 | 1回0/3 | 2 |
| 勝利投手 | 斎藤雅樹 | 5回 | 1 |
| 救援投手(セーブ) | 桑田真澄 | 3回 | 0 |
「救民内閣構想プランB」総理候補リレー
| 内閣総理大臣 | 所属 | |
| 2028年~2029年 | 泉房穂 | 泉新党(現時点では無所属) |
| 2030年~2039年 | 山本太郎 | れいわ新選組 |
| 2040年~2045年 | 三好諒 | れいわ新選組 |
これまでの3回の記事のURLはこちらです。
それでは、議論を進めていきましょう。
2.政治家「山本太郎」への期待
「山本太郎総理待望論【後編】」として、今回は、政治家個人として山本太郎さんが胸に秘める理念や理想、あるいは政党としてれいわ新選組が掲げる政策の実現性に関して論じていきます。
山本太郎さんが総理大臣になることを期待する議論としては、もともと芸能界にいた山本太郎さんが政治家を志すことになったきっかけや、山本太郎さんが今のような価値観を持つに至る背景となる生い立ちなども含めて、ハリス・ポッターさんがnoteで詳しく論じています。
ハリス・ポーター
興味のある方は是非お読みいただきたいですが、山本太郎さんが心に秘める志について、いろいろ論点がある中で、私が期待を込めて論じていきたいのは、「脱原発」と「ロスジェネ救済」と「消費税廃止」の3つです。
3.「脱原発」を実現できるか
「脱原発」は、ある意味でれいわ新選組が志す政策の一丁目一番地のような側面があります。
代表の山本太郎さん以外に、八幡愛さん、長谷川羽衣子さん、ミサオ・レッドウルフさん、奥田芙美代さんらのメンバーも、2011年3月の東日本大震災で起きた福島第一原発の事故を契機に「脱原発」の運動や活動に深く関わることとなり、その活動の流れでれいわ新選組から国政選挙の候補者として立候補するようになった、という経緯があります。
れいわ新選組の政策としては「原発即時禁止」を掲げていて、「漸進的脱原発」という路線と比べて、非常に強い主張内容となっています。
原子力発電について、世界各国がどのような立場を取っているか見てみると、ドイツが2023年に「脱原発」を実現し、台湾は2025年に「脱原発」の実現を予定、ベルギーは2035年に「脱原発」の実現を予定しているという状況ですが、アメリカ、カナダ、フランス、ロシア、インドなどの多くの大国が原発を稼働しており、そして、東アジアでも、中国、韓国、北朝鮮が原発を稼働していて、「脱原発」は、決して「世界的な潮流」とは言えない状況にあります。
私個人としては「原発再稼働に反対、脱原発に賛成」という立場なのですが、日本の世論を見てみても、男女別では男性の方に「原発を再稼働して電気料金を引き下げるべき」という考えの人が多いようで、私のような考え方は、決して多数派というわけではありません。
3月31日から放送が始まったNHK朝の連続テレビ小説「あんぱん」で主演を務める今田美桜さんが電気事業連合会のCMに出演しているのですが、出演するWebムービーのセリフで今田美桜さんは「原子力は、安全確保を大前提に、安定した電力供給が可能です。そして、発電時にCO₂を出しません。だから、電力の安定供給と、地球温暖化対策の両方に欠かせないの!」というふうに述べています。
私などがこれを見ると「なんだ、これ!原発推進のプロパガンダじゃないか!」と思ってしまうのですが、今田美桜さんが笑顔で「エネルギーミックス!」などと言っているのを先入観なしに普通に見れば、「火力発電や再生可能エネルギーだけに頼るのではなくて、原発もある程度稼働させた方がいいのかな」と感じる人が多数出てきてもおかしくないような映像の作りになっています。
原子力発電の問題点について、使用済み核燃料の最終処理をどうするのかという点を脇に置いて、原発事故の危険性のことについてのみ考えるとしても、自分だけではなく将来世代にわたる安全・安心のことを考えるならば、原発は廃止一択だと私は思いますし、れいわ新選組の構成員や多くの支持者の方々も同じ考えを持っておられることと思います。
原発の重大事故が再び起きる可能性について、「りんだろぐ」でその確率が数学的に議論されています。
1基の原子力発電所が重大事故を起こす確率について「100年に1回」と考える立場から「10万年に1回」と考える立場まで主張が様々あるわけですが、ここで私が指摘しておきたいのは、原発推進論者であっても「今後、原発が重大事故を起こす可能性は、ゼロである」と完全に言い切る形で主張するような言説は見られないということです。
原発推進論者の主張は基本的に「原発が重大事故を起こす可能性は極めて低く、ほぼゼロと考えても差し支えない」とするものであり、私に言わせれば、議論の飛躍、一種のすり替え論法であり、「原発は安全であり、事故の心配をするのは杞憂に過ぎない」と思わせる詐術的な議論であると思います。
もちろん、3年、5年、10年といった具合に期間を短く区切って考えた場合には、原発を稼働させても事故を起こすことなく正常に稼働できる確率はかなり高いので、「原発を稼働させて安い電力を供給する方が経済的だ」という考え方に一定の合理性があることは否定しません。
現に、世界の多くの国で原発が稼働しており、日本でも原発が稼働しているのは、そのようなロジックに基づくものだと考えられます。
しかし、50年、100年といった長いスパンで考えた場合、あるいは、原発の稼働台数が多くなった場合には、原発の重大事故が発生する確率は増大します。
「あなたが生きているうちに原発事故が起きる確率は極めて低い」と言われれば、確かにそうなのかもしれませんが、同時に「原発を稼働させれば、明日にも重大事故が発生してしまうかもしれないリスクがある」ということも真実なので、これをどのように捉えるのかは、人によってそれぞれ価値観や考え方が変わってくるでしょう。
現状の日本の世論を見た場合には、全体で言えば「どちらとも言えない」という感じになるのですが、男性に限って見た場合には「原発を再稼働して電気料金を引き下げるべき」という考え方が優勢で、我が国における政治や経済の意思決定の場では、ほぼ男性の意見や男性の論理が貫徹されるような構造になっていますので、現に原発の稼働が続いているということになります。
山本太郎さんが総理大臣になった暁には、この状況を打破して、ドイツや台湾のように「脱原発」の方向に舵を切ってほしいと思いますし、その際に国民の間で分断を引き起こすことなく上手く合意形成が図れることを期待したいと思います。
4.「ロスジェネ」を救えるか
ロスジェネをどのようにして救うのかというのも大問題です。
国民民主党が提出した「若者減税法案」の対象が30歳未満だったことから、「我々を見捨てるのか」と就職氷河期世代の激しい怒りを買っています。
れいわ新選組は「最低賃金1,500円」や「公務員を増やす」といった政策を掲げており、そのことを通して質の高い雇用を確保し、ロスジェネを救いたいという考えのようです。山本太郎さんが総理大臣になった暁には、是非それらの政策を実現して、ロスジェネを救ってほしいと思います。
東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授の中島岳志さんは、中島岳志・雨宮処凛・杉田俊介・斎藤環・平野啓一郎(共著)『秋葉原事件を忘れない―この国はテロの連鎖へと向かうのか』(かもがわ出版、2023年)の中で、次のように述べています。
我々3人(筆者注:中島岳志・雨宮処凛・杉田俊介)はすごく近い誕生日で、1975年の1ヵ月以内に生まれたんですよね。山本太郎さんも1974年11月で近いんですが、自分を含めてずっと考えているのが「60歳の山本太郎」という問題なんです。我々はあと10年ちょっとで60代になる。これから10年間、山本太郎さんや僕たちが、ロスジェネ世代としてどのように闘い、そして老いていき、最後にどのような形を作ることができるのか、ということです。これは、ある種の政治的シンボルとして、山本太郎という人に仮託されているところがあると思っているんですね。
(中略)
私は闘技デモクラシーや制度の不審者であることの重要性を認めたうえで、これを次の段階に進めることが必要なのではと思っています。大きな包摂というか、その敵対性を超えてみんなが幸福へと向かうことができる次元の運動とはどのようなものだろうかと考えています。僕たちの運動や批評性、あるいは政治性を、次の段階に昇華させないといけない、そうした段階がこの10年で来ると思うんですね。これが僕のいう「60歳の山本太郎」問題なのです。
今から10年後の2035年をどのような形で迎えるのかということが非常に重要ですが、①山本太郎総理を誕生させ、②れいわ新選組の政策を実現する、という2つの条件をクリアすることで、ロスジェネが救われる未来を実現できるのではないかと期待しています。
5.「消費税廃止」を実現できるか
国内の問題として一番の大きな課題、そして一番難しい問題が、「消費税」であり、「ザイム真理教」との対決です。
消費税は、表向きは「社会保障のための財源」ということになっていますが、実態としては「法人税減税のための財源」になっており、さらに言えば、「輸出企業に対する消費税の還付金」が最大の利権になっていると言っても過言ではありません。
仮に「消費税の還付金は、『預り金』を戻しているに過ぎない」という考え方に立つとしても、「還付加算金」はまるまる企業側の利益であり、やはりそこに利権が存在することに違いはありません。
逆に言えば、それゆえに「消費税減税」や「消費税廃止」といった政策の実現はハードルが高く、非常に困難を伴うのではないかと予測されます。
6.そして「メロリンQ」
山本太郎さんが公言している「公約」の中で、もう一つ触れておかなければならないのは、「メロリンQ」でしょう。
今回の私の記事では、「脱原発」と「ロスジェネ救済」と「消費税廃止」と「メロリンQ」という4つの公約について触れていきましたが、これらの公約の実現を考えるにあたっては、「脱原発」と「ロスジェネ救済」の2つを優先させたうえで、「消費税廃止」と「メロリンQ」の2つは後回しにするべきだと考えています。
ここで、国民人気が高かった小泉純一郎内閣がどのような形で政策を進めていったのか、振り返ってみましょう。
小泉純一郎内閣略年表
2001年:小泉純一郎内閣発足
2002年:日朝首脳会談
2003年:イラク特措法
2004年:有事法制
2005年:郵政民営化
2006年:8月15日終戦の日に靖国神社参拝
小泉内閣と言えば「郵政民営化」のイメージが強いですが、最初からそのことにチャレンジしたわけではなく、政権を掌握してしばらく経ってから、最後に近い段階で、言わば「総仕上げ」的な感じで「郵政民営化」を実現しています。
また、小泉純一郎さんが2001年の自民党総裁選で公約に掲げた「8月15日終戦の日に靖国神社参拝」を実現したのは、総理を退任する最後の年となる2006年のことです。
山本太郎さんもこのやり方を真似するべきで、まずは財務省とはケンカをせずに経済産業省に的を絞って「脱原発」に取り組んでいくのがよいと思います。
財務省も「定額給付金」ならば認めるという立場ですので、事あるごとに「国難」を叫んで「定額給付金」を支給し、所得の再分配を図りながら、ロスジェネを救済する施策を一つずつ進めていくとよいのではないでしょうか。
「消費税」という最大の利権に切り込むのは、政権基盤が完全に整い、霞ヶ関の官僚組織の大半を掌握した後で、最後に本丸の「財務省」(ザイム真理教)と対決する、という順番で政策を進めていくのが、最も成功する確率が高いのではないかと思います。
そして、山本太郎さんが総理大臣の退任を発表する際に、記者会見の場で「メロリンQ」をやって、支持者との約束を果たしたらよいのではないでしょうか。
7.トピックス①:「トランプ関税」の衝撃
アメリカのトランプ大統領が打ち出した「相互関税」で、世界経済は大変な混乱に陥りました。
8.トピックス②:地獄の「大阪・関西万博」開幕
4月13日に「大阪・関西万博」が始まりましたが、あいにくの大雨に見舞われ、「地獄の開幕」となりました。
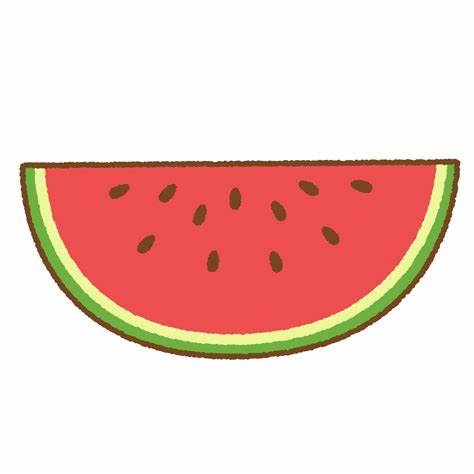
憲法9条変えさせないよ
プロ野球好きのただのオジサンが、冗談で「巨人ファーストの会」の話を「SAMEJIMA TIMES」にコメント投稿したことがきっかけで、ひょんなことから「筆者同盟」に加わることに。「憲法9条を次世代に」という一民間人の視点で、立憲野党とそれを支持するなかまたちに、叱咤激励と斬新な提案を届けます。

