※この連載はSAMEJIMA TIMESの筆者同盟に参加するハンドルネーム「憲法9条変えさせないよ」さんが執筆しています。
<目次>
1.「救民内閣構想プランB」の3人の総理候補リレー
2.厚生労働省の改革
3.国土交通省の改革
4.外務省の改革
5.最後に、本当に「ロスジェネ」は救済されるのか?
6.トピックス:仮面ライダーアマゾンとアンヌ隊員が結婚へ
1.「救民内閣構想プランB」の3人の総理候補リレー
今日は、「救民内閣構想プランB」を考える論考の5回目です。
森永卓郎さんと泉房穂さんの対談本『ザイム真理教と闘う!救民内閣構想』で泉房穂さんが「確実に今の政治状況を根本から変えるためには、総理候補は1人では足らない。最低3人いると思っています。」と語ったことに触発されて、私個人の発想として「長嶋巨人『10.8決戦』の3人の投手リレー」を彷彿とさせる「『救民内閣構想プランB』の3人の総理候補リレー」を構想しました。
長嶋巨人「10.8決戦」投手リレー
| 投手 | 投球イニング | 失点 | |
| 先発投手 | 槙原寛己 | 1回0/3 | 2 |
| 勝利投手 | 斎藤雅樹 | 5回 | 1 |
| 救援投手(セーブ) | 桑田真澄 | 3回 | 0 |
「救民内閣構想プランB」総理候補リレー
| 内閣総理大臣 | 所属 | |
| 2028年~2029年 | 泉房穂 | 泉新党(現時点では無所属) |
| 2030年~2039年 | 山本太郎 | れいわ新選組 |
| 2040年~2045年 | 三好諒 | れいわ新選組 |
これまでの4回の記事のURLはこちらです。
「救民内閣構想プランB」を考えてみる(その2)~泉房穂総理待望論~
泉房穂総理、山本太郎総理、三好諒総理にそれぞれ実現してほしいことを整理して並べて書き出すと、次のようになります。
○泉房穂総理に実現してほしいこと
●「こども家庭庁」を廃止し、「本物の子育て支援」を始動させて、「長期的な人口水準の維持が可能になる合計特殊出生率『2.07』を2070年までに実現させる」という目標を宣言する
●「文部科学省」を改革し、「宗教法人という聖域」に手をつけて「統一教会」の日本国内における影響力を一掃したうえで、「文科省と日教組が作った治外法権」を打破して本当に子どもたちのためになる「教育改革」を実現する
●「大蔵省復活」と銘打って「財務省」を「大蔵省」と「歳入庁」に分割し、「国民の負担を増やさない形での増税」と「特別定額給付金の再実施」の2つを実現する
○山本太郎総理に実現してほしいこと
●「経済産業省」と対決し、「脱原発」を実現する
●「ザイム真理教」(「財務省」→「大蔵省」)と対決し、「消費税廃止」を実現する
●「政・財・官の鉄のトライアングル」を打破し、あらゆる政策を尽くして、「ロスジェネ」(就職氷河期世代)を救済する
○三好諒総理に実現してほしいこと
●「厚生労働省」を改革し、「医療費の削減」と「国民が受けられる医療ケアの水準の向上」の両方を実現する
●「国土交通省」を改革し、「公共事業費の削減」と「日本国内のインフラ整備の水準の向上」の両方を実現する
●「外務省」を改革し、「アメリカに言われるままではない日本の自主外交」の展開を模索し、形式的なものではない本当の意味での「日本の独立」を目指す
それでは、今日は、三好諒総理に実現してほしいことについて、議論を進めていきましょう。
2.厚生労働省の改革
元国税調査官の大村大次郎さんが書いた『世界で第何位?日本の絶望ランキング集』という本に、次のような記述があります。
日本は人口1000人あたりの病床の数が世界一多い。(中略)
また病院の数も異常に多い。
日本には2018年のデータで8000以上の病院、診療所があり、断トツの世界一なのである。世界第2位はアメリカだが6000ちょっとしかない。
アメリカは日本の2倍以上の人口を持つので、日本の現状は異常値である。
(中略)
「病床数は世界一なのに集中治療室は先進国最低レベル」
このいびつさこそ、日本医療界の暗部を象徴するものなのである。
日本の医療システムには、「公立病院の割合が少なく民間病院が異常に多い」という特徴がある。
なぜ日本にICUが少ないのか、という問いの答えはここにあるのだ。
(中略)
民間病院というのは、当然のことながら儲かることしかしない傾向がある。民間病院では手間がかかる上にリスクの多い重症患者などはあまり受け入れたがらない。だから民間病院には、集中治療室などはあまり設置されていないのだ。そのため、日本では集中治療室が異常に少ないという状況に陥っている。
そして民間病院の大半は、新型コロナの患者を受け入れなかった。だから欧米よりも感染者が何十分の一、何百分の一しかいなかったコロナ禍初期の段階で、すでに医療崩壊の危機に瀕してしまったのだ。
このいびつな構造は、「国民の健康よりも、民間病院の権益を優先する」という日本の医療行政の歪んだ根本姿勢に起因するのだといいます。
日本全体の医療費の多くが開業医に流れるようになっているということだ。こういうシステムがあるので、開業医は勤務医の2倍もの収入を得られている。
にもかかわらず新型コロナ禍の際、民間病院の大半は非協力的であり、中には患者も受け入れていないのに多額の補助金だけせしめるところも少なからずあったのだ。
日本は、病床数、病院数は世界一多いにもかかわらず、医者の数は先進国の中で異常に少ない。それが、医療を脆弱にしている大きな要因の一つである。
しかも医者の数が少ない理由の一つが、開業医の既得権益を守るためなのであるから二の句が継げない。
(中略)
日本の医療がなぜ、このように開業医にばかり有利になっているのかというと、開業医は「日本医師会」という強力な圧力団体を持っているからだ。
(中略)
日本は世界的に見て医者が少ないのだから、増やすのが当然の施策である。
もし将来、医者が余れば無能な医者が淘汰されればいいだけの話である。実際に、ほかの業種ではそういう健全な競争が行われている。
しかし、そういう競争が行われた場合、金の力で医者になった開業医の子どもたちが一番に淘汰されるのは目に見えているので、日本医師会は頑強に反対しているのだろうと勘繰りたくもなる。
そして厚生労働省も日本医師会の圧力に屈している。ご存じのように役人は政治家に頭が上がらない。政治家に圧力をかける日本医師会には、厚生労働省も逆らえないわけだ。だから、医者が少ないのがわかっていながら医学部の新設がなかなか認められず、医学部の定員もなかなか増えないのだ。
もちろんツケを負わされるのは国民である。
実は、日本の国家予算の中で最も大きな割合を占めているのは「医療費」で、そのいびつな構造について、大村大次郎さんは次のように指摘しています。
定義によって若干違ってくるが、日本の財政支出のうち、最も大きいのは医療費だと言えるのだ。
正当な医療費が不足し、社会保険料だけでは賄えず、そのために税金から支出されているのであれば、国民として仕方がないと思う。
しかし、日本の医療の場合、異常なシステムがあり、一部の病院、医師だけが法外な高収入を得る仕組みになっている。そして、その一部の医療関係者のために、日本の医療費全体が引き上げられ、国民の税金を浪費しているのだ。
この「日本医師会」と「厚生労働省」が作り出している日本の医療の異常な構造こそが「改革の本丸」とでも言うべきものであり、「開業医の利権の打破による医療費の削減」を実現していく必要があります。
これは三好内閣の課題であるというだけではなく、その前の山本内閣や泉内閣でも課題とすべき内容であり、3代の「救民内閣」で継続して取り組んでいくべき課題と言えます。
しかし、単に「医療費の削減」を目標としてしまうと、「開業医の利権」が維持されたままで、「勤務医や看護師などの医療関係者の待遇改悪による医療費の削減」もしくは「国民が受けられる医療ケアの水準の低下を伴う医療費の削減」をもたらしてしまう危険性があります。
自民や維新が「医療費の削減」を進める場合には、おそらくこのタイプの「悪い『医療費の削減』」をもたらしてしまうでしょう。
「悪い『医療費の削減』」の典型例が、危うく実現しそうになった(実は、参院選後に実現されてしまうかもしれない)「高額医療費制度の改悪」です。
従って、「医療費の削減」と「国民が受けられる医療ケアの水準の向上」の両方を実現する「良い『医療費の削減』」を進めていくことが重要です。
そのためには、医療制度や業界内の力関係などについて熟知した政治家が、この問題に専心して取り組んでいく必要があると思います。
私個人の考えを述べますと、医療費に関して言えば、18歳以下の国民の医療費はすべて国が負担して、「自己負担ゼロ」(無料化)となるように改革していくべきだと思います。
そして、19歳以上の大人の医療費については、高齢者と現役世代で差をつけずに、2割負担なら2割負担、3割負担なら3割負担にするなどして、自己負担の割合を一本化していくべきなのではないかと思います。
その代わり、「高額医療費制度」に関しては、最低でも現状維持か、あるいは負担額をいま以上に軽減する方向で改革していき、「大きなケガや病気をした際の医療費の自己負担を公的保険でできるだけ軽減する」という機能に特化し、これを拡充していくような方向を探っていくべきだと思います。
3.国土交通省の改革
元国税調査官の大村大次郎さんが書いた『世界で第何位?日本の絶望ランキング集』という本に、次のような記述があります。
1990年、当時の海部俊樹首相がアメリカに対する公約として、今後10年間で430兆円の公共事業を行うと明言した。その後、村山富市内閣のときに、この公約は上方修正され630兆円にまで膨らんだ。
アメリカがなぜ、このような要求をしたのか?
同年、日本は赤字国債の発行をゼロにして、財政の健全化を達成していた。当時、先進諸国は財政赤字に苦しんでおり、とりわけアメリカは史上最悪の状況になっていた。いまとなっては信じがたいかもしれないが、日本は当時、先進諸国の中でとても財政が健全な国だったのだ。
アメリカとしては何とか危機を脱したい。そこで金回りのいい日本政府に公共事業で金をばら撒かせ内需を拡大させて、貿易収支を改善させようとしたのだ。
1年に63兆円を10年間、つまりは630兆円である。
現在の国の借金1000兆円は、間違いなくこのときの630兆円の公共事業に端を発するのである。
その630兆円の公共事業費は、一体どこへ行ったのか?
そのことについて、大村大次郎さんは次のように記述しています。
ここで大きな疑問を持たれないだろうか?
莫大な公共事業費が何に使われてきたのか、と。前述したように、日本は先進国の中で最も公共事業が多く、しかも90年代には現在の倍近くの額を投じてきた。
しかし、まるで、この莫大な額のお金がどこかへ消えたかのように、社会インフラを整えた跡が見られない。
実際、何に使われたかというと、その答えは「無駄な箱モノ」「無駄な道路」などである。
地方に行くと、人影もまばらな駅の周辺が非常に美しく整備されていたり、車がめったに通らない場所にすごく立派な道路があったり、さびれた街並みに突然、巨大な建物が現れたりすることがある。
そういう地域には有力な国会議員がおり、その議員に群がる利権関係者がいるのだ。
政治家は、自分を支持する建設土木業者のために、公共事業を地元に誘致しようとする。必然的にその業者が得意な公共事業ばかりが予算化されるのだ。道路工事が得意な事業者には道路工事を、箱モノ建設が得意な事業者には箱モノ建設を発注するという具合である。
となると、その地域には、非常に偏った公共事業ばかりが行われることになる。道路工事ばかり行っている地域、箱モノ建設ばかりを行っている地域という具合に。
そこには、国全体を見渡してインフラの不備な部分を整備しようなどという発想はまったくない。だから、莫大な公共事業費を使っていながら、日本のインフラはボロボロなのである。
日本の公共事業はこのような構造になっているため、投入した費用に見合わない乏しい効果しか生んでいないと言わざるを得ない状況にあります。
SAMEJIMA TIMES主筆の鮫島浩さんは、『政治家の収支』という本の中で、次のように記しています。
天下り官僚たちに支払われる退職金や報酬、族議員が手にする政治献金だけなら、それほどの巨額にはならないかもしれません。それ以上に問題なのは、天下り先や政治献金のシステムを作るために、不毛な巨大事業が生み出され、そこへ桁違いの税金が投入されることです。天下り官僚の数百万円・数千万円の退職金や報酬を作り出すために、数百億円・数千億円の公共事業が立案されることもあるのです。
このような現状を考えると、「①業者の受注単価が高くなりがちな公共事業の単価を抑えることで、公共事業費の削減を図る」ことと、「②公共事業の優先順位を精査して、『有力政治家の地元だから』といった理由ではなく、本来の必要度に応じた順番で公共事業を進めていき、インフラ整備の水準を引き上げる」ことの2つをそれぞれ追求していかなければならないことになります。
これは三好内閣の課題であるというだけではなく、その前の山本内閣や泉内閣でも課題とすべき内容であり、3代の「救民内閣」で継続して取り組んでいくべき課題と言えます。
また、これからの時代は、新規の公共事業というよりも、過去の公共事業で建設した建物や橋梁、整備した道路や上下水道などの計画的なメンテナンス(補修)を重視していかなければなりません。
それをやれなければ、また道路陥没のような悲劇が起きてしまいます。
4.外務省の改革
れいわ新選組の三好諒さんは、もともと外交官で、そこで行われている対米従属外交に疑問を持ち、政治家へと転身しました。
「救民内閣」の3番手総理として「三好諒内閣」が実現した暁には、次のような外交・防衛案件の課題に取り組んでいく必要があります。
○「救民内閣」で取り組むべき外交・防衛上の課題
①「安保法制」の廃止
②沖縄「辺野古基地」の建設中止と、「普天間基地」の返還
③「日米地位協定」の改定
④「横田空域」の返還
⑤国連憲章「旧敵国条項」の廃止もしくは死文化
①は日本国内の政治の問題と言えるかもしれませんが、②~④はアメリカを相手に交渉が必要になる案件であり、⑤に至っては、アメリカだけではなく全世界を相手に話を進めていかなければならない案件になります。
いずれも難問ばかりですが、これらの問題を解決していくためには、まず国内の状況が安定している必要がありますので、3代にわたる「救民内閣」全体で考えた場合には、山本内閣で国内の問題に決着を付け、三好内閣で対外的な交渉を本格化させる、という方向で考えていくしかないのではないでしょうか。
悠長に待っているわけにはいかない沖縄の「辺野古基地」の問題については、「建設工事を一旦中断し、工事の計画全体を見直す」ということで「ペンディング」の状態に持ち込み、そのうえで、一番良いタイミングで「辺野古基地建設中止」をいう結論を出すような形にするしかないと思います。
今から20年後の西暦2045年は「戦後100年」の年にあたり、「日米地位協定」や「横田空域」や「旧敵国条項」の問題に道筋をつけるには、良いタイミングを迎えるのではないかと思います。
逆に言えば、このチャンスを逃してしまうと、「形式的には独立国、実質上はアメリカの属国」という日本の状況が未来永劫続いてしまう恐れがありますので、その意味で、三好諒さんが活躍して大きな役割を果たすことに期待したいところです。
5.最後に、本当に「ロスジェネ」は救済されるのか?
自民党の石破内閣は、氷河期世代支援のあり方を検討する閣僚会議を開催しました。
自民党政権では、「氷河期世代支援」は「『氷河期世代支援』を名目にした中抜き事業」に堕してしまうであろうことは確実です。
一日も早く自民党を下野させて、「政権交代」を実現させる必要があります。
問題は、自民党が下野して、いざ「政権交代」となった場合に、どのような人物が総理大臣の座に就くのかということです。
「自己責任」を金科玉条とする「勝ち組ロスジェネ」のような人物が政権の座に就いた場合には、「『氷河期世代支援』は税金の無駄」として、「『ロスジェネ』は、仕事ができる限り働け!働けなくなったら、人生終わりと思え!」といった具合に突き放される可能性が非常に高いでしょう。
「ロスジェネ」(就職氷河期世代)が生き残るためには、「救民内閣」を作って「山本太郎政権」を誕生させ、「生活を大胆に底上げする」ような政策を実現させるしかないのではないかと思います。
この件に関しては、稿を改めて論考を行いたいと思います。
6.トピックス:仮面ライダーアマゾンとアンヌ隊員が結婚へ
「仮面ライダーアマゾン」で主役の仮面ライダーアマゾンを演じた岡崎徹さん(76歳)と、「ウルトラセブン」でアンヌ隊員の役を演じたひし美ゆり子さん(77歳)が、年内に結婚することとなったことが分かりました。
岡崎徹さんとひし美ゆり子さんの末長いお幸せを心よりお祈りいたします。
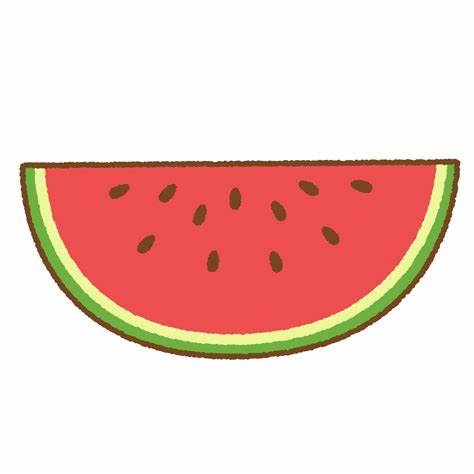
憲法9条変えさせないよ
プロ野球好きのただのオジサンが、冗談で「巨人ファーストの会」の話を「SAMEJIMA TIMES」にコメント投稿したことがきっかけで、ひょんなことから「筆者同盟」に加わることに。「憲法9条を次世代に」という一民間人の視点で、立憲野党とそれを支持するなかまたちに、叱咤激励と斬新な提案を届けます。

