※この連載はSAMEJIMA TIMESの筆者同盟に参加するハンドルネーム「憲法9条変えさせないよ」さんが執筆しています。
<目次>
1.「救民内閣構想プランB」の3人の総理候補リレー
2.ロスジェネ受難の歴史
3.目先の救済策をどうするか
4.ロスジェネ救済のための長期ビジョン「持続可能なシニア天国」を作る
5.長期的な財源をどうするか
6.トピックス①:共産党推薦の是枝綾子さん忠岡町長初当選
7.トピックス②:朝日新聞の偏向報道に共産党のジャイアン激おこ
8.トピックス③:私は米を買ったことがない江藤農水大臣辞任からの小泉進次郎まつり
1.「救民内閣構想プランB」の3人の総理候補リレー
今日は、「救民内閣構想プランB」を考える論考の6回目です。
森永卓郎さんと泉房穂さんの対談本『ザイム真理教と闘う!救民内閣構想』で泉房穂さんが「確実に今の政治状況を根本から変えるためには、総理候補は1人では足らない。最低3人いると思っています。」と語ったことに触発されて、私個人の発想として「長嶋巨人『10.8決戦』の3人の投手リレー」を彷彿とさせる「『救民内閣構想プランB』の3人の総理候補リレー」を構想しました。
長嶋巨人「10.8決戦」投手リレー
| 投手 | 投球イニング | 失点 | |
| 先発投手 | 槙原寛己 | 1回0/3 | 2 |
| 勝利投手 | 斎藤雅樹 | 5回 | 1 |
| 救援投手(セーブ) | 桑田真澄 | 3回 | 0 |
「救民内閣構想プランB」総理候補リレー
| 内閣総理大臣 | 所属 | |
| 2028年~2029年 | 泉房穂 | 泉新党(現時点では無所属) |
| 2030年~2039年 | 山本太郎 | れいわ新選組 |
| 2040年~2045年 | 三好諒 | れいわ新選組 |
これまでの5回の記事のURLはこちらです。
「救民内閣構想プランB」を考えてみる(その2)~泉房穂総理待望論~
「救民内閣構想プランB」を考えてみる(その3)~山本太郎総理待望論【前編】~
泉房穂総理、山本太郎総理、三好諒総理にそれぞれ実現してほしいことを整理して並べて書き出すと、次のようになります。
○泉房穂総理に実現してほしいこと
●「こども家庭庁」を廃止し、「本物の子育て支援」を始動させて、「長期的な人口水準の維持が可能になる合計特殊出生率『2.07』を2070年までに実現させる」という目標を宣言する
●「文部科学省」を改革し、「宗教法人という聖域」に手をつけて「統一教会」の日本国内における影響力を一掃したうえで、「文科省と日教組が作った治外法権」を打破して本当に子どもたちのためになる「教育改革」を実現する
●「大蔵省復活」と銘打って「財務省」を「大蔵省」と「歳入庁」に分割し、「国民の負担を増やさない形での増税」と「特別定額給付金の再実施」の2つを実現する
○山本太郎総理に実現してほしいこと
●「経済産業省」と対決し、「脱原発」を実現する
●「ザイム真理教」(「財務省」→「大蔵省」)と対決し、「消費税廃止」を実現する
●「政・財・官の鉄のトライアングル」を打破し、あらゆる政策を尽くして、「ロスジェネ」(就職氷河期世代)を救済する
○三好諒総理に実現してほしいこと
●「厚生労働省」を改革し、「医療費の削減」と「国民が受けられる医療ケアの水準の向上」の両方を実現する
●「国土交通省」を改革し、「公共事業費の削減」と「日本国内のインフラ整備の水準の向上」の両方を実現する
●「外務省」を改革し、「アメリカに言われるままではない日本の自主外交」の展開を模索し、形式的なものではない本当の意味での「日本の独立」を目指す
今日は、山本太郎総理に実現してほしい「ロスジェネ(就職氷河期世代)の救済」ことについて、議論を深堀りしていきたいと思います。
2.ロスジェネ受難の歴史
ロスジェネ(就職氷河期世代)は、1993年から2004年ごろに学校を卒業して社会に出た層で、年齢的には40代前半から50代前半までの世代、人数規模は1,700万人にのぼるとされています。
私は1974年生まれで、ちょうどこの世代にあたるわけですが、私の記憶を遡りながら、ロスジェネ(就職氷河期世代)の受難の歴史を振り返っていきたいと思います。
1990年にバブル経済が崩壊し、1993年ごろから新卒の採用人数が非常に絞られるようになり、企業によっては「採用ゼロ」といったところもザラにありました。
当時の採用面接は「圧迫面接」なども数多くあり、女子学生であれば就活に際して「セクハラ」的な行為を受ける事例も少なくありませんでした。
まず入口の就職活動の問題として、最終的な統計数値として正規社員になった者が7割、非正規社員になった者が3割ということなのですが、この「正規社員7割」というのが当事者の実感とは非常に異なる数値で、多くの者が自らの学歴との比較であまり納得がいかない小さな規模の会社に就職することとなり、単に企業規模が小さい(いわゆる銘柄企業ではない)というだけではなく、そこにはブラックな企業も多数存在しており、(統計的に実証することはできませんが、あくまでも体感的に言えば)「不本意入社が8割~9割」というぐらいの感覚でした。
まぁ、就職活動のお約束として、「御社第一志望」というのが建前ですので、形式的に言えば「不本意入社はゼロ」なはずで、さらに就職氷河期が長引くにつれて「正社員として内定がもらえるならどこでもいい」という意識が学生の間に広がり、(こういう言い方をすると業界関係者には失礼ですが、)平時の景況感なら不人気業種となるはずの飲食業界やパチンコ業界にも銘柄大学を卒業した新卒の人たちが「喜んで」就職していくような時代状況になっていきました。
私はバブル崩壊からあまり年数が経過していない時期に大学を卒業した初期ロスジェネですので、当時の大卒者の就職活動においては、わざと留年したり、あるいは大学院に進学したり、人によっては大学卒業後にわざわざ専門学校に通うなどとして、新卒としての就職活動を1年~2年程度先延ばしして景気の回復を待とうとする動きも一定程度ありました。(それは結果として全く功を奏さなかったのですが。)
一方の公務員試験や教員採用試験の競争率も鬼のように高く、「狭き門」とは正にこのことか、という感じでした。
辛うじて学生側に選択権があるとすれば、「銘柄企業で派遣社員や契約社員として働くか、あるいは、中小企業で正規社員として働くか」という選択肢があって、現在の目から見ると「中小企業であっても正規社員として新卒採用される方が長期的に見て有利」だと結論づけることができるわけですが、当時は非正規社員(派遣社員や契約社員)の身分上の過酷さが今のように一般的に知られてはおらず、「派遣社員や契約社員という身分であっても、銘柄企業で働けるなら、近い将来そこで正規社員として本採用される可能性があるので、それなら銘柄企業を選んだ方がいい」と考える者も少なくありませんでした。
これが後にさらなる悲劇を生むことになります。
社会人になったロスジェネのうち、正規社員として就職した者について見ていくと、当時は「年功序列」や「体育会系」的な会社組織や企業文化が牢固として抜きがたく、会社の中では普通に「パワハラ」も横行していました。
多くの会社で「お前らの代わりはいくらでもいる」といった粗雑な扱いを受け、少ない人数の同期と共に「過酷な営業活動」や「雑巾がけ」的な業務に携わらざるを得ない人がほとんどでした。
さらに悲惨だったのは、採用人数が少ない、あるいはゼロという状況が何年も続き、組織の中で一番下っ端の仕事を長年にわたって引き受けざるを得なかったことです。
年を取って「中堅」と呼ばれるようになってきても、経験年数に見合った難易度の高い仕事と共に、下っ端的な仕事も全部かぶらざるを得ない状況が長く続き、あまり高くない給料のまま、難しい仕事から簡単な仕事まで莫大な分量の業務を一人で回さざるを得ないロスジェネ世代サラリーマンは数多くいました。
それからさらに年齢を重ねて、管理職になったときには、今度は「新卒に優しい、パワハラのない労働環境を」という下からの圧力(ある意味で、下からの「逆パワハラ」)にさらされることとなり、近年の新卒社員の初任給が上昇するにつれて、あまり上がっていない自分の給与との不公平感を感じる状況が生まれてきました。
それでも、正規社員として就職できた者はまだマシなほうで、派遣社員や契約社員として働くロスジェネは、もう「悲惨」と言うほかはありません。
多くの日本企業の内部組織は、建前上はともかく、実態としては一種の「カースト制」のようになっており、派遣社員や契約社員として働く場合には、そのカーストの「最下層」として位置づけられ、ほとんど人権侵害に近いのではないかと思えるようなひどい扱いをうけることとなります。
給料は安く、身分も不安定。製造業であれば、2008年のリーマンショックの際に「派遣切り」された者も少なくありません。
「同じ企業で3年以上働く場合には、正社員としての雇用を義務づける」という法改正も結果的には悪手で、「3年になる前に契約を打ち切る」という事態が横行して、身分の不安定さをかえって加速させることとなってしまいました。
正社員としての職を探そうにも、非正規雇用の形態で働いている期間の仕事内容は、転職活動の際には「職歴」とはみなされず、「正社員としての経験が全くないですね。」とか、「正社員になろうとしたことはありますか?」とか、「望んで非正規の仕事を続けてこられたわけですよね?」といった冷たい言葉を投げかけられて、転職先が見つからないか、見つかったとしてもまた非正規の仕事という「負のスパイラル」を延々と続けざるを得ない状況が今も続いています。
新卒の際に非正規雇用でキャリアをスタートせざるを得なかった女性たちのうち、一部の女性は、「婚活」で素敵なパートナーにめぐり会うことで、結婚して家族を作り、幸せをつかんだ人たちもいました。
ただ、その「幸せ」というのは、例えば団塊世代などの古い世代の人々のそれと比較すると、その「幸せ」の度合いが非常に薄まったもので、ヨーロッパ諸国と比べて子育てに対する社会の支援の態勢が整っていない日本においては、「子育て罰」を食らうこととなり、「1人子どもを育てるのも大変」とか、「経済的なことも考えると、子どもは2人で精一杯」といった悲鳴があちこちから聞こえてきました。
そして、彼女らの子育てが一段落した今になって、遅まきながら国や一部の自治体は「子育て支援」ということを言い出しているのですが、「アラフィフ」のロスジェネは、そうした支援の恩恵を全く受ける機会がないまま年を取ってしまいました。
ロスジェネの「勝ち組サラリーマン」の家庭も、団塊世代のそれと比較すると非常に大変で、耐久消費財と言われる家電製品や車、マイホームなど、大きな買い物をするたびに「消費税」という高い罰金を取られ、資産の形成を邪魔され続けてきました。
さらに、金融資産という観点で見ても、団塊世代であれば銀行や郵便貯金に預貯金を預けていれば、放っておいても自動的に利息がついてどんどん資産が増えていったのですが、ロスジェネ世代は銀行にお金を預けても、利息は雀の涙です。
預金金利があまりに低いということで、株式投資などを行う「勝ち組サラリーマン」は少なくなく、彼らは「アベノミクス」の際には大いに儲けたようですが、中にはタイミング悪く「株式暴落」の局面に遭遇して、「子どもの教育資金にするはずのお金が溶けてしまった」と顔面蒼白になる者もいるなど、人によって運・不運があるのが株式投資の問題点です。
私は、個人にこのようなリスクを負わせることになる今の風潮は、非常に良くないと思っています。
3.目先の救済策をどうするか
ロスジェネに限らず、困窮する人々を救う方策として、何が一番手っ取り早くて効果的なのかを、ここで考えてみます。
よく語られるアイデアとしては、「所得税減税」と「消費税減税」と「定額給付金」があると思いますが、これらの3つの方法について、その効果をそれぞれ数値化して検証してみましょう。
給与等の収入金額が①220万円の個人、②660万円の個人、③1,100万円の個人、④1,540万円の個人の4人について、減税額の合計または給付額の合計が同額になるようにして比較した表が、次のものです。(四捨五入の関係で、誤差があります。)
所得税減税(一律に基礎控除の金額を30万円増額した場合)
| 給与等の収入金額 | 2,200,000円 | 6,600,000円 | 11,000,000円 | 15,400,000円 |
| 所得税額(減税前) | 49,000円 | 444,500円 | 1,335,100円 | 2,744,100円 |
| 所得税額(減税後) | 34,000円 | 384,500円 | 1,266,100円 | 2,645,100円 |
| 減税額 | 15,000円 | 60,000円 | 69,000円 | 99,000円 |
| 減税額/収入額 | 0.682% | 0.909% | 0.627% | 0.643% |
※令和6年の所得税率を基に、復興特別所得税は無視したうえで、基礎控除と給与所得控除のみで税額を計算。
消費税減税(消費税率を0.76%引き下げた場合)
| 消費金額 | 2,200,000円 | 6,600,000円 | 11,000,000円 | 15,400,000円 |
| 消費税額(減税前) | 200,000円 | 600,000円 | 1,000,000円 | 1,400,000円 |
| 消費税額(減税後) | 184,813円 | 554,438円 | 924,063円 | 1,293,688円 |
| 減税額 | 15,187円 | 45,562円 | 75,937円 | 106,312円 |
| 減税額/収入額 | 0.690% | 0.690% | 0.690% | 0.690% |
※収入の全てを消費税率10%の財・サービスの購入に充てたものと仮定して税額を計算。
定額給付金(一人あたり60,750円を給付した場合)
| 収入金額 | 2,200,000円 | 6,600,000円 | 11,000,000円 | 15,400,000円 |
| 給付額 | 60,750円 | 60,750円 | 60,750円 | 60,750円 |
| 給付額/収入額 | 2.761% | 0.920% | 0.552% | 0.394% |
※全て一人世帯と仮定して給付額を計算。
「所得税減税」の減税額合計が243,000円、「消費税減税」の減税額合計が242,998円、「定額給付金」の給付額合計が243,000円になっていますので、それぞれの個人の収入に対する比率で計算してどの方式が一番お得なのかを見てみますと、①収入金額220万円の個人と②収入金額660万円の個人にとっては「定額給付金」が一番お得で、③収入金額1,100万円の個人と④収入金額1,540万円の個人にとっては「消費税減税」が一番お得という計算結果になります。
減税額や給付額の合計を同じにして比較するために、「消費税率0.76%引き下げ」とか「一人60,750円の定額給付金」といった半端な額に設定して比較していますが、「消費税率5%引き下げ」の効果を考える場合にはこの表の金額を6.58倍にし、「一人10万円の定額給付金」の効果を考える場合にはこの表の金額を1.65倍にして計算すると、実際の額に近い金額を算出することができます。
私がこの計算を行った当初の意図は、「所得税減税」を(玉木雄一郎さんの名前からとって)<玉木方式>、「消費税減税」を(山本太郎さんの名前からとって)<山本方式>、「定額給付金」を(安倍晋三さんの名前からとって)<安倍方式>と呼んで、「<玉木方式>の所得税減税は高額所得者優遇だ!」と言って非難しようという考えだったのですが、実際に計算してみると、①収入金額220万円の個人と③収入金額1,100万円の個人と④収入金額1,540万円の個人にとって「所得税減税」も「消費税減税」もそんなに効果は変わらないという意外な計算結果が出てきました。
また、特徴的な計算結果が出たのは②収入金額660万円の個人で、「所得税減税」と「定額給付金」でどちらもそんなに効果が変わらないという結論になりました。
このような特徴が出てくるのは、所得税の税率が次のような形の累進課税制度になっているためです。
平成27年分以降の所得税の税率
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
課税所得金額1,950,000円から3,299,000円までの税率が10%であるのに対し、課税所得金額が3,300,000円から6,949,000円までに達すると税率がポンと20%にまで跳ね上がってしまうため、この範囲に当てはまる収入金額のサラリーマンにとって、体感的な重税感が非常に増大してしまう状況になっています。
従って、私が計算した②収入金額660万円の個人の「所得税減税」の効果が、「定額給付金」の効果とあまり変わらない高い数値で出てくるという計算結果になっているのです。
2024年の衆院選で「手取りを増やす」という国民民主党のスローガンが一番心に響いたのは、このあたりのサラリーマン層なのではないでしょうか。
心理的な効果はさておき、実際の「所得再分配」の効果を考えた場合に一番優秀なのは、「定額給付金」の<安倍方式>という結論になります。
そういう意味では、2020年に当時の安倍総理が実施した国民一人あたり一律10万円の「特別定額給付金」は、非常に良い政策だったというふうに言うことができます。
「救民内閣」が政権を獲った暁には、泉房穂さんも、山本太郎さんも、安倍支持層の歓心を買うように「安倍さんが行った経済政策は素晴らしかった!私も安倍さんを見習って、国民一人あたり一律10万円の『特別定額給付金』を実施します!」と言って回るべきです。
このやり方であれば、財務省も形式的には「特別定額給付金」に反対することができません。
「国難に際しては国民一人あたり一律10万円の現金給付を行うことができる」というのは安倍政権時代に「前例」として確立されており、2020年の際には「コロナ禍」がその「国難」にあたったわけですが、例えば今の政治状況であれば、「トランプ関税」を「国難」として、「国民一人あたり一律10万円の現金給付を行う」という政策を実施する論拠とすることができます。
さらに有難いことに、安倍晋三総理は、2017年に衆議院を解散する際に「少子化が国難」だとはっきり明言されています。
従って、日本の少子化の問題が解消しない間は、「少子化が国難となっている今、国民一人あたり一律10万円の現金給付を行うべきだ」と言い続けることができます。
もし、この「特別定額給付金」を年4回実施するなら、れいわ新選組が掲げる「季節ごと10万円のインフレ対策給付金」と同じ内容の政策を実現することができます。
10万円の現金給付に対して反対意見が出た場合には、「我が国の合計特殊出生率が2.07を超えない限りは、長期的に見て、日本人の数は減少していき、やがて民族として滅亡してしまう。そのような存亡の危機を脱するために、『特別定額給付金』の政策を実施しなければならない。」と言い切ってしまえば、理屈の上では問題ないはずです。
そのような形で「安倍総理のレガシー」を最大限活用しながら、財務省に「特別定額給付金」の実施を何度も何度も繰り返し認めさせ、当面の国民生活の底上げを図っていくべきだと思います。
4.ロスジェネ救済のための長期ビジョン「持続可能なシニア天国」を作る
一律10万円給付の「特別定額給付金」を何度も繰り返し実施して当面の国民全体の生活の底上げを図っていったうえで、長期的にロスジェネ(就職氷河期世代)を救うために、「持続可能なシニア天国を作る」というビジョンを掲げることを私は提唱したいと思います。
「持続可能なシニア天国」とは私が勝手に作った新しい概念で、「長期的に人口規模や経済規模、生活環境を維持できる状態を保ちながら、シニア世代が安心して自分らしく心豊かに暮らせる社会」を構築することを目指すものです。
恨み辛みも込めて厳しい言い方をすれば、今の日本社会というのは「人口規模の持続可能性も、経済規模の持続可能性も、生活環境の持続可能性も全部無視して、団塊世代が自分たちだけ豊かな暮らしができるような仕組みにした社会」だと思います。
まさに、「団塊世代が自分たちの子どもや孫の世代(あるいは、さらにその先の世代)にツケ回しをした」と私は言いたいのですが、とはいえ、「団塊世代に復讐を!」みたいなことを言っても誰も幸せになれるわけではありませんので、別な考え方で日本社会の立て直しを図っていくべきだと考えます。
まずは①子どもたちを救い、次に②若者世代を救い、そして最後に③シニア世代を救うという順番で日本社会の立て直しを行い、ロスジェネ(就職氷河期世代)が「シニア世代」と呼ばれる年齢になったときに、「生きてて良かったと思える社会」(by 山本太郎)や「みんなが笑って暮らせる社会」(by 奥田芙美代)が実現できるようにする、というのが基本的な戦略です。
それは、今のような「高齢者が若者を搾取して少子化が進む」という社会ではなく、「少子化が止まり、子どもたちも、若者世代も、シニア世代も、みんなが笑って暮らせる」という社会の実現を目指すものです。
ですから、「ロスジェネ(就職氷河期世代)に、今までの苦難のお詫びとして、何らかの特権を与える」という考え方には立っていません。
「みんなが笑って暮らせる社会を作ったら、結果的に、シニア世代になったロスジェネ(就職氷河期世代)も救われていました」という状況を生み出すことを狙っています。
昔は日本の人口ピラミッドは「富士山型」でしたので、高齢者の割合は低かったのですが、現在は「つぼ型」になり、近い将来は年少世代の数が細って高齢世代のみの数が多い逆三角形の「独楽」(こま)みたいな形になろうとしています。
昔の「富士山型」の時代には、高齢者を優遇しても社会全体でそんなに大きな負担にはならなかったと思いますが、「つぼ型」から「独楽」(こま)のような形になろうとしている今は、高齢者に対して必要以上に優遇をしてしまうと、社会全体が持たなくなる危険があります。
かといって、高齢者を冷遇する世の中になってしまうと、将来年を取って自分が高齢者になったときに悲惨な生活をしなければならなくなり、自分で自分の首を絞める結果となってしまいます。
従って、高齢者に対する基本的なスタンスは、「優遇もしないが、冷遇もしない」というスタンスでいくべきだと思います。
今後、優遇していくべきは、子どもたちです。
子どもたちには日本の未来がかかっていますし、人数が少ないことを考えれば、子どもたちを優遇しても、社会全体にそれほど大きな負担がかからないことになります。
このスタンスに立って考えると、医療費の自己負担は、例えば「18歳以下の子どもたちは医療費無料、19歳以上の大人は全員2割自己負担」というような形に組み変えて、現役世代の自己負担を減らして、高齢世代の自己負担を増やす形で、現役世代と高齢世代の負担の差をなくすようにしていくべきです。
さらに、子どもたちに対しては、医療費の無償化だけではなく、給食費の無償化、教育費の無償化など、必要なサービスを「ベーシックサービス」として無償で提供していくべきです。
その代わり、子どもの親に対して「子育て世代への現金給付」という形で支援を行うのは、基本的にやめるべきだと思います。
現在の日本のような「格差社会」で貧富の差がある状態で、特定の階層だけが現金給付を受けるような施策は、嫉妬や不公平感を醸成するだけですので、私はやめるべきだと思います。
「格差社会」の今は、現金給付を行う場合には、国民全員に一律に給付すべきです。
若者世代に対しては、「若者を含む労働者全員が働きやすい世の中を作る」施策を進めていくことが重要だと思います。
若者を含めて、働いている現役世代にとって、働く環境や待遇がどの程度整っているのかは非常に重要な事柄です。
これに関しては、これまでに進んできた少子化の影響もあって、若者世代の労働力には「希少価値」が生まれてきており、一般的に言えば、以前に比べて労働条件が飛躍的に改善されてきているという状況があります。
しかし、一方では劣悪な待遇や労働環境から若者に敬遠される業種もあり、そうした業種も含めて、社会にとって必要な仕事を提供している業界の労働環境を、政府の介入を通して改善していく必要があります。
今話題になっている教員の過重労働であるとか、保育、介護、医療、運輸、建設、農業など、様々な業界で労働環境や待遇の改善を図っていく必要があります。
一言で言えば、「人間らしい働き方ができる職場」を数多く作っていく必要があるのです。
さて、いよいよロスジェネ(就職氷河期世代)をどうやって救済するのかという核心の議論になります。
それは、「日本経済が再び成長軌道に乗ったあと、『特別定額給付金』の支給を徐々に減らして『ゼロ』へと近づけていき、そのうえで2045年までに『シニアベーシックインカム』(仮称)を導入して、75歳以上の後期高齢者全員に毎月13万円の現金給付を行う」という、とっておきの施策です。
仮に日本国民1億2,000万人全員に年4回一律10万円の現金給付(全体で年間48兆円)を行っても財政破綻しないのだとすれば、後期高齢者の割合が国民全体の25%を占めることになったとしても、75歳以上の後期高齢者全員に毎月一律13万円の現金給付(全体で年間46兆8,000億円)を行うことは可能だという計算になります。
そうすれば、仮に「無年金」の人であったとしても、75歳以上の後期高齢者は、みんな安心して暮らすことができます。
年金に関して言えば、国民年金のみの人もいれば、厚生年金まで受給できる人や、さらには企業年金までもらえる人もいて、その格差はいかんともしがたいところがあるわけですが、「シニアベーシックインカム」で「健康で文化的な最低限度の生活」を全員に保障することによって、年金の格差を「人それぞれの老後のゆとりの違い」として、なんとか許容範囲内に収められるようになるのではないでしょうか。
「シニアベーシックインカム」の実施が2045年までに間に合えば、1993年に新卒の社会人として23歳だった人が75歳の年齢に達する年に間に合うこととなり、その後のロスジェネ(就職氷河期世代)や、それより若い世代の人も、全員が安心して老後を過ごすことができるようになります。
5.長期的な財源をどうするか
10万円の「特別定額給付金」の年4回実施にしろ、13万円の「シニアベーシックインカム」の年12回実施にしろ、莫大な予算が必要になるわけですが、その予算の財源をどのようにして賄うのか。
考え方は、大きく言って二つあります。一つは税。一つは新規国債の発行。
今回は、税で説明していきたいと思います。
ここからはまた私独自の考え方になりますが、税の取り方を考えるときに、「生きている人間から税金を取るのは遠慮がちに行うべきだ」という考え方を提唱したいと思います。
「無税国家」を構想するのは無理だと思いますが、「重税国家を避ける」ということを基本思想としながら、かといって「税金は安ければ安いほどいい」というわけではなく、「社会を維持していくのに最適な課税」を模索していくべきだと思います。
いわゆる「リベラル派」の方々は、「所得再分配」を重視して「累進課税」という考え方に期待をかけがちですが、生きている人間から税金を取る場合には、過度な「累進課税」に期待しない方がいいと個人的には考えています。
ただし、今の日本のように「1億円の壁」があって、「1億円を超えると高額所得者ほど実効税率が下がる」というおかしな状況は改善すべきで、税率は「比例的な税率」または「なだらかな累進税率」を保つようにすべきなのではないかと思います。
それでは、どの場面で「所得再分配」を図るべきかと言えば、私は、「人が死んだときに、相続税を思いっきり高く取る」べきだと考えています。
厳密に言えば、相続税は財産を相続した人にかかる税金ですので、「生きている人にかかる税金」なのですが、ここでは「死んだ人にかかる税金」として捉えて、議論を進めていきたいと思います。
どんなにお金持ちだったとしても、浮き世で稼いだ財産を、あの世まで持って行くことはできません。
古代では「班田収受」といって、人が亡くなったら口分田を国に返す仕組みになっていました。
それと同じ発想で、亡くなった人の財産は、「相続税」でもって、基本的に国に納めるような方式にしていったらよいのではないでしょうか。
「親ガチャ」と言われるような状況をできるだけなくしていくためにも、「相続税」の課税を強化して、所得再分配を進めていくことは極めて重要です。
もちろん、残された遺族の生活のこともありますので、「相続税率100%」みたいなことはできないとは思いますが、社会に十分なセーフティネットが張られていることを前提としたうえで、相続税率の高い社会への移行を進めていくことは、「公平な社会」を構想するうえで、必要不可欠なのではないかと思います。
また、一般の人々にかかる相続税の税率を引き上げる前に、政治家が政治団体に政治資金をプールすることで実質的に相続税逃れを図ることができる現状のスキームは、できる限り早く法改正を行い、そのような法の穴をふさいでいく必要があります。
相続税率の引き上げは、政治家の「政治団体を使った相続税逃れ」を許さないようにしたうえで、それから後の話になると思います。
次に、財源として重視したいのが、法人税です。
人にやさしい税制を志向していくうえでは、「生きている人間(自然人)ではなく、法人から税金を取る」という方向性を考えていくべきです。
れいわ新選組代表の山本太郎さんは「法人税の累進税化」という構想を考えておられるようですが、累進化まではしなくてもよいので、「租税特別措置法」という仰天ルールによって大企業の実効税率が中小企業の実効税率よりも低くなってしまっている逆立ちした状況を正し、少なくとも同じ実効税率になるように改革を行っていくことが必要です。
また、企業の内部留保に関して、れいわ新選組代表の山本太郎さんは「法人税という税金が一度かかったもの(内部留保)に対してさらに課税を行うことは考えていない」という見解のようですが、私は企業の内部留保に課税を行うべきだと考えています。
実は、今の法人税の制度にも「留保金課税」というものが存在しているのですが、その対象となるのが「特定同族会社」に限られるため、一般の企業には全く関係のないものになっています。
しかし、これを全ての会社に適用できるように法改正すれば、企業の内部留保に課税を行うことが可能になります。
もちろん、このような法改正には経団連が猛反対するでしょうが、「あるところから取る」という意味では、私はこれが一番良いのではないかと思います。
正規社員にせよ、非正規社員にせよ、ロスジェネ世代はおしなべて給与水準が低く抑えられており、ロスジェネが血と汗と涙で生み出した収益をかすめとって企業の利益として付け替えていったのが、経団連に加盟する大企業が抱える資産として貯まりに貯まった内部留保です。
今話題の年金制度改革(厚生年金の積立金を基礎年金の底上げに使うかどうか)の議論は、「正規社員ロスジェネvs非正規社員ロスジェネ」あるいは「若手を中心とする現役世代vsロスジェネ」という対立図式で語られていますが、私はこの対立図式自体が茶番だと思います。
本当の対立軸は、「自然人vs法人」あるいは「ロスジェネvs経団連」なのであって、本来であればロスジェネ(就職氷河期世代)が自らの手で財産を築くことができていたはずのお金をかすめとって企業の内部留保にしてしまっているのですから、これを吐き出させて、社会全体のために使うことが絶対に必要であると私は考えます。
「人以外のものに課税する」という意味で、もう一つ考えたいのは、宗教法人への課税強化です。
一般の事業会社の場合、法人税の負担を重くすることで企業が日本から海外へ流出してしまい、国内の空洞化をもたらしてしまうのではないかという懸念も一定程度考えられますので、あまり思い切った増税を行うことはためらわれます。
しかし、宗教法人であれば、最悪、海外に移転してしまったとしても、それで日本の経済力が弱まるとは到底考えられませんので、思い切った増税を行うことが可能です。
自民党と公明党が下野した暁には、その間隙をぬって、ぜひ宗教法人への課税強化を実現してほしいと思います。
6.トピックス①:共産党推薦の是枝綾子さん忠岡町長初当選
5月18日に投開票が行われた大阪府忠岡町長選挙で、無所属新人で共産党推薦の是枝綾子さんが激戦を制して初当選し、維新町政に終止符を打ちました!
7.トピックス②:朝日新聞の偏向報道に共産党のジャイアン激おこ
都議選を間近に控えた東京都政に関する記事で、朝日新聞が共産党の存在を意図的に無視する偏向報道を行ったことに対して、「共産党のジャイアン」こと香西克介さんが「X」(旧:twitter)で激しい怒りをあらわにしました。
8.トピックス③:私は米を買ったことがない江藤農水大臣辞任からの小泉進次郎まつり
「私は米を買ったことがない」という失言で江藤拓農林水産大臣が辞任し、後任の農林水産大臣には小泉進次郎さんが任命されました。
SNSは「進次郎まつり」になっています。
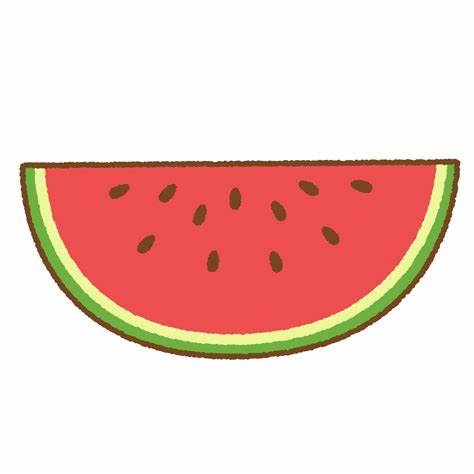
憲法9条変えさせないよ
プロ野球好きのただのオジサンが、冗談で「巨人ファーストの会」の話を「SAMEJIMA TIMES」にコメント投稿したことがきっかけで、ひょんなことから「筆者同盟」に加わることに。「憲法9条を次世代に」という一民間人の視点で、立憲野党とそれを支持するなかまたちに、叱咤激励と斬新な提案を届けます。

