※この連載はSAMEJIMA TIMESの筆者同盟に参加するハンドルネーム「憲法9条変えさせないよ」さんが執筆しています。
<目次>
1.はじめに
2.「石破政権」が終わっても「自民党政権」は続くのか?
3.泉房穂プロデュース「救民内閣」で伊勢崎賢治総理を誕生させよう!
4.限定1年の「選挙管理内閣」で30年前に細川護熙内閣がやり残した宿題を終わらせる!
1.はじめに
今回の記事は参院選期間中に執筆していて、参院選の選挙結果はまだ分からない状態なのですが、「自公与党過半数割れの公算」ということを前提に、与党が過半数割れした後の政局に関して、私たち有権者がどのような展開を望み得るのかということについて論考していきたいと思います。
2.「石破政権」が終わっても「自民党政権」は続くのか?
トランプ関税の発動の期日が8月1日に迫っているため、選挙に負けても石破首相はそれを理由に当面続投するかもしれませんが、それでも臨時国会が開かれる秋には(自発的な辞任か、内閣不信任によるものかは別として)石破内閣は総辞職せざるを得なくなるでしょう。
そうなると、また自民党総裁選が行われ、マスコミは「果たして『ポスト石破』は誰になるのか?」ということに話題を集中させるでしょう。
「ポスト石破」のシナリオは、大まかに言って次の4つに分けられるものと思われます。
「ポスト石破」4つのシナリオ
| シナリオ | 政権枠組み | 枠組みの変化 | 主観的確率 |
| A | 自公立(大連立) | 立憲が与党入り | 44% |
| B | 自公維(+参?) | 維新(+参政?)が与党入り | 33% |
| C | 自公国 | 国民が与党入り | 22% |
| D | 野党連立政権 | 自民と公明が下野 | 1% |
※「主観的確率」の数値に根拠はなく、もっぱら筆者の主観によるものです。
自民党と公明党が衆議院で過半数を取り戻すためには、立憲民主党か、日本維新の会か、国民民主党のうち、少なくとも一つを連立に引き込んで、新たな政権の枠組みを作る必要があります。
一方で、自民党と公明党を下野させるためには、それ以外の野党が軒並み手を握って「野党連立政権」を樹立する必要があり、「野党がバラバラの今の状況では、政権交代が起きる可能性はほとんどない」というふうにマスコミは結論づけています。
しかし、自公与党が衆議院でも参議院でも過半数割れして、それでもなお自民党と公明党を与党とする政権が続くというのは、そこに本当に民意が反映されていると言えるのでしょうか。
そこで私は、「確率1%」しかないと思われる「野党連立政権」の誕生、そして自民党と公明党の下野の可能性を探っていきたいと思います。
3.泉房穂プロデュース「救民内閣」で伊勢崎賢治総理を誕生させよう!
前明石市長の泉房穂さんが掲げている「救民内閣構想」は、首班候補が誰なのかという点に関して、今まで全く触れられてきませんでした。
そこで、私の独断と偏見で、「野党連立政権」の首班候補にふさわしい国会議員は、今回の選挙で新しく参議院議員に選ばれた伊勢崎賢治さんである、と訴えたいと思います。
まず、各野党の党首は、全て昨年10月の衆院選後の首班指名選挙で自民党の石破総理に敗れています。
そういう意味でも、今回の参院選で新たに国会議員に選ばれた人の中から選ぶというのは、自然な発想として出てくるのではないかと思います。
また、伊勢崎賢治さんは、「国際連合東ティモール暫定行政機構上級民政官」を務めた経験があり、外交・防衛・行政に関する知見を持つスペシャリストです。
政情不安の国において、政党が内閣を組閣できないような事態に陥った場合、政治家ではなく学者が首班の役を担って「選挙管理内閣」を組織するようなケースがあります。
今の日本も、それに近いような感じで「学者の方にお願いして選挙管理内閣を組織してもらう」ということが必要な場面に遭遇しているのではないかと思います。
伊勢崎賢治さんを首班とする「選挙管理内閣」は来年の夏までの概ね1年間限定の「暫定政権」として考え、来年の夏に「新たな政権の枠組み」について問う衆議院解散総選挙を実施して、そこで新たに首班を選び直して、「本格政権」に移行するのです。
具体的には次のような構想になります。
伊勢崎賢治首班「選挙管理内閣」構想
○伊勢崎賢治さんにはれいわ新選組から離党してもらい、無所属の身分になったうえで、国会の首班指名選挙で自民党と公明党以外の「オール野党」で「伊勢崎賢治」の名前を書いて、「野党連立政権」を誕生させる。
○閣僚は、自民党・公明党・共産党・れいわ新選組の4党を除く全ての国政政党から1名ずつ人員を出してもらうようにし、誰をどの大臣ポストに任命するかについては、首班の伊勢崎賢治さんが専権事項として判断して決める。
○各国政政党から1名ずつ人員を出してもらって足りない大臣ポストに関しては、学識経験者などを中心に民間から人材を起用して充てることとし、人選は首班の伊勢崎賢治の専権事項で決める。
○国会議員および民間から採用された大臣が問題発言や問題行動を行った場合には、伊勢崎総理の判断で即座に大臣罷免し、当該ポストは補充せずに伊勢崎総理が兼務することを、組閣する時点で予め宣言しておく。
○伊勢崎賢治さんを首班とする「野党連立政権」は、来年の通常国会が終わるまでの約1年間政権を担うこととし、夏を目途に衆議院解散総選挙を実施して、民意によって新たな政権の枠組みを選び直す。
閣僚の人選が「自民党・公明党・共産党・れいわ新選組の4党を除く全ての国政政党から」となっているのは、自民党と公明党は今回下野させる必要があること、共産党は一党だけ基本政策が他の政党と大きく異なること、れいわ新選組は形式的には離党しても実質的には「伊勢崎賢治首班」で総理大臣を出すことになること、がそれぞれ理由になります。
ちなみに、2025年の通常国会における各党の法案賛成率は次のようになっています。
法案賛成率が4割を下回っているのは共産党とれいわ新選組の2党だけで、それ以外の政党は概ね7割以上の法案賛成率となっています。
従って、「自民党と公明党を下野させ、共産党とれいわは閣内に入らず首班指名などで協力するだけの『閣外協力』」という「野党連立政権」を組織した場合には、「自公政権から少しだけ変わるが、ドラスティックな劇的変化が起きるわけではない」ことが想定され、国民全体から受け入れられやすくなるのではないかと思います。
ところで、前明石市長の泉房穂さんは、『政治はケンカだ!』の本の中で次のように述べていました。
当面の見立てとしては、次の総選挙でがらりと変わると期待しています。2025年7月に衆参ダブル選挙になると睨んでいまして、兵庫県の場合は知事選も重なってトリプル選挙になる。ここが一つの山場でしょう。何度も言ってますが、変わる時は一気に変わるから。それこそ、ずずずっと地球の地盤が動くようなイメージかな。
衆参同日選挙にならなかったという意味ではこの見立ては外れましたが、昨年の秋の衆院選と今年の夏の参院選で自公与党が過半数割れし、「山が動いた」という意味では、泉房穂さんの見立てはその通りになったというふうに解釈することもできます。
やはりここは、有権者が示した民意を「連立与党の組み替え(拡大)」に終わらせるのではなく、「野党連立政権誕生」にまで持っていくべきだと思います。
参院選の投開票が終わった後、トランプ関税が発動予定の8月1日までは、一種の「政治休戦」的な状態になると思いますが、この間に「野党連立政権誕生」の機運を高めていくことが極めて重要だと思います。
それができる「発信力」がある政治家は、前明石市長の泉房穂さんをおいて他にないのではないでしょうか。
4.限定1年の「選挙管理内閣」で30年前に細川護熙内閣がやり残した宿題を終わらせる!
それでは、限定1年の「選挙管理内閣」で一体何をするのか?
具体的な政策案を提示していきます。
伊勢崎賢治首班「選挙管理内閣」政策案
○まず、とにかく自民党と公明党を下野させる
○辺野古の基地建設は「工法の再検討を要するため工事を当面休止」する
○「ガソリンの暫定税率を廃止」する
○「紙の健康保険証を復活」させる
○補正予算を組んで、年内に「特別定額給付金」の現金10万円給付を実施する
○「消費税を廃止」したうえで、税率7%の「国民福祉税」を創設する
○「こども家庭庁を廃止」し、いわゆる「独身税」の徴収を中止する
○「赤字国債を出さない」形で来年3月に「救民予算」を成立させる
○「政治改革」を実現するため、「企業献金の禁止」を行う
○これらの政策を実現したうえで、来年の夏に「衆議院解散総選挙」を実施する
○「選択的夫婦別姓」については、内閣からの法案提出は行わず、国会での審議(議員立法)に委ねる
これらの政策のうち、「企業献金の廃止」は、本来、30年前(正確に言えば32年前)に細川護熙内閣(非自民連立政権)の手で実現しておくべきことでした。「政治改革」に失敗し、結果として30年以上に亘って「企業献金と政党助成金の二重取り」を許す結果になりました。「野党連立政権」を誕生させた暁には、何としてもこのことに手をつけるべきです。
「消費税廃止」と「国民福祉税創設」、そして「赤字国債を出さない『救民予算』」に関しても、詳しく説明する必要があると思います。
「消費税廃止」と「国民福祉税創設」は、これも細川護熙内閣が実現できずに終わった政策です。今こそ、この政策を実現すべき時です。
「国民福祉税」は、今の「消費税」とほぼ同じですが、税率7%の単一税率になっており、「軽減税率」や「インボイス」といった制度はありません。従って、「インボイス廃止」はこれで実現できることになります。
また、消費税の「免税事業者」の枠は、現在の制度では「売上高1,000万円以下」になっていますが、細川内閣の頃の制度であれば「売上高3,000万円以下」になっていました。この「免税事業者」の枠を「売上高3,000万円以下」に戻すことで、多くの中小事業者が一息つくことができるようになると思います。
「税率7%」に関して、私は「国税5%・都道府県税1%・市町村税1%」という割り振りにしたらいいと思っていますが、いわゆる「積極財政派」の方々は、「最低でも税率は5%以下に引き下げるべきだ」と考えておられるのではないかと思います。
気持ちは分からなくありませんが、しかし、今の衆議院の議席配分で「野党連立政権」を作るとなると、「緊縮財政派」(健全財政派)の方々の割合が少なくありませんので、税率5%への引き下げは、実際問題として実現困難なのではないかと考えています。
また、「緊縮財政派」(健全財政派)の方々は突如として「食料品のみ税率0%」みたいなことを言い出したりするわけですが、今の日本の状況でこれをやれば、外食産業(特に個人経営のお店)がバタバタ潰れていくことになるであろうことは必定ですので、そうした愚策を避ける意味でも、あくまでも単一税率で「税率7%」というやり方を採用するほうがよいのではないかと思います。
税率が10%から7%へ「3%引き下げ」になるのは、「ショボイ」と思われるかもしれませんが、現在の物価上昇率は「+2.3%」~「+2.5%」というぐらいの水準ですので、実は、ちょうど物価上昇率に対応できる程度の税率引き下げになっています。
従って、「消費税を廃止」したうえで「税率7%の単一税率の国民福祉税を創設(免税事業者枠:売上高3,000万円以下)」することで、インボイスの廃止と免税事業者枠拡大による中小事業者の救済と、物価上昇率に見合った3%の税率引き下げによる消費者の負担軽減が図れるようになるわけです。
「所得再分配」という点に関しては、「10万円の特別定額給付金」のほうに期待をして、年内に補正予算で1回、そして、新年度の本予算でもう1回、というような流れにできるとよいのではないかと思います。
「赤字国債を出さない『救民予算』」について説明しますと、誰が財務大臣を務めるとしても、「財務省とガチンコで戦って『積極財政』に転換させる」などというのは今の力関係では非常に難しいものと思われます。
従って、「赤字国債を出さない」ことを敢えて宣言して、「緊縮財政派」(健全財政派)の政治家・官僚・学者などを黙らせてしまうのが得策なのではないかと考えます。
そのうえで、農業や教育や福祉などの分野は予算を増額し、一方で、こども家庭庁の廃止や防衛予算の大幅削減などで財源を捻出していきます。
大正時代には「師団の削減と兵器の近代化」を行った「宇垣軍縮」というのがありましたが、この令和時代には「アメリカ製兵器の購入の先延ばしと自衛隊員の待遇改善」を行って「伊勢崎軍縮」をやればいいのではないかと思います。
これによってどの程度財源を確保できるようになるのかは分かりませんが、どうしても歳入と歳出の辻褄が合わないようなら、(こどもが成長すれば納税者になり、その収める税金で国債を償還できるという考え方で)子育てや教育の分野に特化した「こども国債」を発行できるように制度を変えて、「赤字国債を出さない」という建前を維持するようにすればよいのではないかと考えています。
あるいは、高齢者向けの予算の捻出がどうしても難しそうなら、「しあわせ国債」(仮称)のようなものを発行できるようにして、その分の国債の償還は、近い将来に相続税を増税してその分の税収を充てる(高齢者が亡くなった時に、財産の一部を国庫に返納してもらうようなイメージ)という方法も考えられるのではないでしょうか。
いずれにしても、今回の提言は、ある程度学術的な議論の裏付けがあるものから、私が個人的な素人の思い付きを述べたものまで、いろいろ玉石混交の内容ですが、私だけではなくいろいろな立場の人々が「政権交代」(自民党と公明党の下野)に向けてアイデアを出していって、「野党連立政権」を実現できるようになることを、心から祈っています。
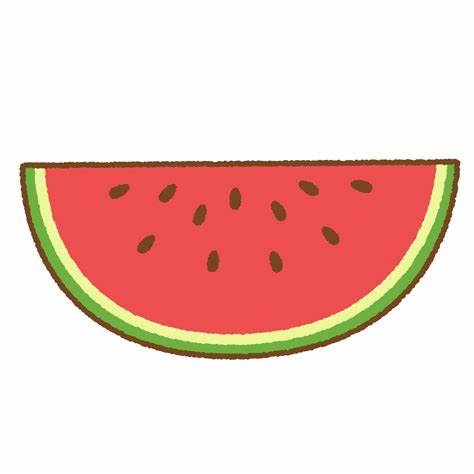
憲法9条変えさせないよ
プロ野球好きのただのオジサンが、冗談で「巨人ファーストの会」の話を「SAMEJIMA TIMES」にコメント投稿したことがきっかけで、ひょんなことから「筆者同盟」に加わることに。「憲法9条を次世代に」という一民間人の視点で、立憲野党とそれを支持するなかまたちに、叱咤激励と斬新な提案を届けます。

