全体主義とは「全体(または支配層・権力層)を優先し、全体のために個人は存在する。そのため個人の自由は制限される社会」と定義できるでしょう。共産主義とは「財は国のものとして共有し、階級は無く、能力に応じた社会貢献をし、必要なものがあたえられる社会」と言えるでしょう。
しかし英語圏で「全体主義」を検索すると、一般的な説明に加えて興味深い説明に出会います。ブリタニカではおおむね以下のように解説されています。
全体主義は、立憲民主主義国と外観上ほとんど変わらない制度(議会や集会、選挙や政党、裁判所や法)を持っていることが一般的だ。ただし、全体主義ではそれらの制度が法的に機能せず、支配者層にコントロールされ、あるいは支配者層に忖度して運用され、権力に対する有効なチェックとして機能していない。
全体主義は、すべての政治制度を新しく置き換え、すべての法的・社会的・政治的伝統を一掃することを目指している。社会全体への同調を求める空気がつくられ、支配者層はなんでもやれるようになる。
支配者層の目標を妨げる可能性のあるものはすべて拒否され、あらゆる反対意見は悪の烙印を押され、最終的に反対勢力を抑圧するために警察など実力部隊を投入する。警察は法律や規制の制約外で活動しており、その行動は意図的で予測不可能だ。
「安全保障」の名のもとに憲法や法律を凍結し、政権が国民の基本的人権を大幅に制限することを可能とする緊急事態条項を盛り込んだ憲法改悪は、まさに全体主義の象徴です。与党のみならず、ゆ党(自民党支援の党)や野党にもそれを支持する議員が少なからずいるようです。
最近では、国民の監視を強める重要経済安保情報保護法案(セキュリティー・クリアランス制度)が与野党多数の賛成で可決されました。
「民主主義・自由」の名のもとにマイナンバーカードによる個人情報の管理が進んでいます。欧米諸国では “グレート・リセット” という「より良い社会」という名目で “社会と経済のあらゆる側面を見直して刷新する” 計画が謳われています。岸田政権も推進しています。このような動きをグローバリズムという人々もいます。
全体主義と言えば、中国で1966年から約10年続いた、文化大革命(毛沢東と中国共産党が起こした中国国内の革命)が今なお語り継がれます。その複雑さから歴史の専門家も理解に苦しむ出来事でした。(現在の共産党は名前を引き継いでいますが、目指すものや性質は違ってきているので、それを指すものではありません)
“文化大革命”を経験したシュー・ヴァン・フリート(Xi Van Fleet)さんとその著書「毛沢東のアメリカ・Mao’s America」が注目を集めました。フリートさんは、革命のほんの数日間で、全く違う日常と世界になったことを伝えています。
フリートさんとタッカー・カールソン(Tucker Carlson)さんとのインタビュー 「文化大革命はここにある。フリートさんにきいてみた。彼女はそれを中国と米国で2度経験した」も話題となり、またガーディアン・Guardianは「中国の文化大革命:政治的混乱について知っておくべきこと」という説明記事(証言・動画も含む)を発行しました。これらから特徴的なこと、現在につながる物語を見ていきたいと思います。
“文化大革命”で大動員が始められた時、中国共産党の新聞は「新たな命を吹き込む画期的な闘争」とし、社説は「東から昇る赤い太陽のように、見たこともないプロレタリア大革命がその輝かしい光でこの地を照らしている」と描写したそうです。しかし、実際はその希望に輝くような言葉は、人々を暴力を伴う激しい対立と闘争、社会の破壊へと向かわせるものでした。
これは現代にも通じると感じます。ほとんどの政治家・経済界など支配層の言葉は、表向きは未来の明るい展望・耳障りの良い内容・人々を安心させる数々の言葉が、まるでAIのように無機質に、ただ発せられているようです。現実は、ここ30年の日本の政治の結果は、“衰退”という言葉で象徴され、意味が分かりにくい、カタカナ英語の法律・制度が乱発され、何が真実で、何が嘘なのか頭を混乱させられる感覚が起きます。多くの国民もそうでしょう。
“文化大革命”で、経済は麻痺し、社会活動は停滞・混乱し、飢餓が起こり、国民同士が敵対させられ、200万人もの命が無駄に失われたと言われます。
フリートさんは、1986年20代後半にアメリカに渡り、それ以来、中国系アメリカ人として米国で生活しています。そして、当時は中国で何が起こっているか分からなかったことが、米国での数十年の経験から、徐々に気づくようになります。そして、ここ数年、米国が置かれている状況は、文化や環境は違っても“文化大革命”の頃と似ているのではないか、すなわち全体・共産主義化が起こっている、と警鐘を鳴らしています。
1 何が “文化大革命” を起こしたのか?
毛沢東は、党内や国での “権力の確立と維持” のためには、全体主義によりイデオロギーを強化し、反対派を排除するという政局観から “文化大革命” を思いつきました。この動機は、米国が世界の警察・リーダーとして覇権を握るために、約160ヶ国に米兵が派遣され、世界各地に750以上の米軍を置いていることと重なります。その半数以上は、日本と韓国だとされています。国務長官は、戦争を続けるのは、自国の雇用と経済にとって有効だと公で発言もしています(こちら参照)。
日本国内でも日々、岸田首相、キングメーカーの麻生副総裁、公明党の権力争い、それに付随する野党の政局で、政治が動いていることが日々のSamejima Timesの報道で分かります。「国民みんなのために政治をする」という政治家が少なく、主導権を握ることができていないことが歯がゆく感じます。
2 分断・対立させられる人々
“文化大革命” 中は、“黒い階級”(財産と知識を持つ人々)が悪とされ、”赤い階級”(その他の国民)と敵対関係に置かれました。毛沢東は“黒い階級”を弾圧する「紅衛兵」の活動に干渉しないよう治安部隊に命令し、 1966 年の 8 月と 9 月だけで北京では 1,800 人近くが犠牲になりました。
現在は、米国では、保守派と革新派・人種間・貧富の差・国民と移民(大量の不法移民を含む)の間で分断や対立がみられます。日本では、低中所得者に厳しい税制や政策と大企業・外国優遇政策が進み、貧富の差がどんどん広がっています。
世界を見ると、他国からの過度の干渉を嫌う保守派VS米国と西側につく革新派の対立も見られます。そのため、国(地域)や民族が今も分断されています。例えばパレスチナ・ロシアとウクライナ・朝鮮半島・コソボとセルビアなどです。
3 誰が “文化大革命” をすすめたのか?
実際に“文化大革命”を進めたのは、毛沢東や党の言葉を信じて扇動された「紅衛兵」と呼ばれる学生や労働者たちでした。全国の教室やキャンパスに紅衛兵部門が設置されました。「紅衛兵」を表す赤い腕章と揃いの軍服を着た十代の男女の若者たちの集団が教授・教員・知識人を標的にし、公の場で屈辱し、弾圧しました。また「紅衛兵」は、ブルジョワ的な服装や髪型をした若者を取り締まるために、都市の通りを徘徊し、悪質な“闘争”を繰り広げました。
特に激しかった「紅衛兵」は、中国でトップ中のトップと言われる北京や上海での大学生たちで、活動がエスカレートしていったと言われています。
日本で気になるのは、第二自民党と見られる“ゆ党”や自公政権を援助する野党の議員が多いことです。JNN世論調査では、政権交代を望む数は増えていますが、まだ34%の国民が、自公政権の継続を望んでいます。
4 何が人々を変えたのか?
“文化大革命”で人々は「教化」されたと言われます。英語ではindoctrinateと訳され、日英辞書では「教え込む・吹き込む」とありますが、英英辞書ではさらに踏み込んで「誰かが批判や疑問を抱かずに受け入れるまで、その考えや信念を頻繁に繰り返すこと」とあります。
“文化大革命”が始まると小学校から大学、多くの施設も2年間閉じられました。そして、毛沢東の名言を集めた「赤い本」というポケットサイズの公式ハンドブックが配られ、至る所で読書会が開かれました。街の“帝国主義的” 看板やポスターは、“文化大革命”を支持するものに変わりました。現代ではマスコミ・SNS・インフルエンサーと呼ばれる人々がその役割を果たしていると指摘されます。
フリートさんは、情報が封鎖され、何が起こっているか分からず、考えることができず、思考停止していたと言います。
こう考えてくると、日々の教育の影響は大きいと再認識するほかありません。私の経験では、豪州では教師個人が教材を選ぶことやプログラムを組むことができ、テストも長文を含む筆記が主流でした。私の知る限り日本は、高校まで教科書は検定で定められたものしか使えず、テストも教科書の範囲の中で出る選択式が主流でした。
言語統制も行われ、政府を非難したり、特定の言葉を使ったりすると、過剰な攻撃を受けたそうです。現在は自称、自由の国である西側諸国や米国でも、イスラエル非難や薬害(ワクチン)非難をすると公的に罰せられることが起こっています。
日本でも、タブー視される言葉はあるのでしょうか。
5 歴史や伝統・文化の破棄は、何を意味するのか?
「歴史・文化・伝統が消えれば、初春に残雪が溶けてなくなるように、その国や人々は消えてしまう」という言葉を読んだことがあります。「人々を破壊する最も効果的な方法は、彼ら自身の歴史の理解を否定し、消してしまうことだ」という言葉も目にしたことがあります。
1966年6月1日、党の新聞は大衆に対し、「怪物と悪魔」に対する総攻撃を開始し「古い社会の邪悪な習慣を一掃する」よう訴えます。党は 「紅衛兵」 に、古い思想、古い慣習、古い習慣、古い文化・芸術を破壊するよう促しました。各家庭の中まで踏み込んで古いものを取り除き、騒乱は本格化しました。
日本では、大阪万博で何兆円も使う維新に関連し、“大阪フィルハーモニー交響楽団や文楽協会への助成金の25%削減” や“大阪府が美術品を「粗大ゴミ扱い」地下駐車場で作品保管” というニュースがありました。
維新の東参院議員は「そもそも文化や芸術に対して国が補助金を出すのは馴染まないのではないだろうか。余程の公共性というものがないかぎり補助金は馴染まない。補助金を頼らず、寄付などで賄う努力が本来必要」と、芸術文化軽視を感じる投稿をしています。
欧州の国々は、文化芸術に多くの予算を割くようです。豪州でも新政権は、芸術文化は自己を表現し国のアイデンティティーを確立するために重要であるとして予算が組まれ、特に経営の大変な中小団体に支援がされるようになりました。
去年12月にローマでのイタリアのメローニ首相の政治祭典「アトレジュ」の主賓として出席した、イーロン・マスクさんはイタリアの移民問題と人口動態について問われ「新しい世代を築くために、少子化対策で自国の子供を増やすことだ。(移民に頼るのではなく)そうしないと、イタリア・日本・フランスの文化が消滅するだろう。これらの国々がなくなる危険にさらされている。出生率の低下による人口崩壊が危険だ」というように訴えました。(こちら参照)
日本では、独自の文化や伝統をもつ、多くの地方の町が消滅すると予想されます。しかし、何の対策もされず、それは計画的に行われているように感じます。土地を持っていても税金が‘高く、維持が困難で遺産放棄が増えているとききます。誰も住まなくなった町々や土地は誰が所有し、どのように使われるのでしょうか。外国に売られる土地や企業は、どうなるのでしょうか。
6 “文化大革命”とその後…
1966年に始まった革命は1968年後半には深刻な被害者が急増する事態に陥りました。毛沢東は自分の革命が制御不能になったことに気づきます。彼は軍に秩序を回復するよう命令しましたが、大衆の闘いと混乱は収拾がつかず、軍事独裁政権になった後も1971年頃まで続きました。暴力を抑制するために、彼は何百万人もの都市部の若者を「再教育」のために未開地に送り、厳しい開拓労働に従事させました。1976年、党内で非毛沢東化に尽力した周恩来が亡くなり、これを悼む中国民衆の街頭行動が起こり、鎮圧が図られましたが、そうした動きはのちに天安門事件へと発展し、毛沢東政治からの転換点となりました。
欧米諸国の“帝国主義”の争いに巻き込まれたアジアの悲劇である “世界大戦”、そしてその後の中国の“文化大革命” が語り継がれるのは、後世に同じ不幸を繰り返さないためでしょう。
7 新たな始まりは…
私は、中国やロシアに全て賛同するわけではありません。しかし、隣国とは争いを避け、お互いに利益を得るために友好関係を築くことが穏やかな幸せにつながると思います。
現在の中国のリーダーである習近平さんは、“文化大革命”が起こったとき13歳で、多感な青年期でした。自身の家族もその犠牲者となりました。その後、中国は資本主義を取り入れ、外国からの “帝国主義” 支配と内政干渉を防ぐシステム(制度)を進めました。西側諸国に“独裁政治だ”と非難を受け続けても、一党制を貫いてきました。どちらが良いかは別にして、日本とは違う道を選びました。
日本で暮らしてきた私は、西側諸国により親しみをもち、あまり報道されない中国やロシアにはネガティブなイメージをもっていました。中国やロシアは “一党独裁だ” とマスコミは繰り返し報じます。
豪州のメディアは、中国やロシアの人々の声も紹介し、「西側の民主主義は、短期契約社員のような首相(リーダー)が取っ替え引っ替え現れる」「自分たちと違う世界も認めるべきだ」という主張もしています。
2009年にせっかく政権交代が起こったのに、民主党内の紛争が起こり、たった8ヶ月で総理大臣が辞任して全く別の総理大臣と政治になってしまったことを振り返ると、「未来のビジョン・そのための計画・短期の戦略をもち、国を守り繁栄させるリーダーなら、長期間任せる」という、まとまりのある政治をなぜ非難しないといけないのか、という思いがよぎります。
豪州SBS(NHK相当で無料)は、ロシアで5月9日は“勝利の日”であることを伝えました。ロシアが第二次世界大戦で、他国より突出した2700万人の死者を出しながら、ナチス・ドイツ軍に侵略を許さなかったことを祝う日です。モスクワの赤の広場での式典の様子が報道され、プーチン大統領の「ロシアは、再び他国の侵略を許さない」という言葉が紹介されました。
私は、ナチスがユダヤ教の人々を弾圧したことを、学校で学び、マスコミやSNSからも知りました。しかし恥ずかしいことに、“勝利の日”とロシアの悲しい歴史は、豪州の報道で初めて知りました。下の写真は、その報道の様子です。


豪州メディアでは、プーチン大統領は「ソ連崩壊後も、外国から国を守り、200を超える少数民の伝統や文化も維持し、ゆっくりではあっても国を繁栄させてきた」、習近平国家主席は「世界大戦で受けた侵略・文化大革命・後進国という時を経て、経済・科学技術も世界のトップを築いた」と紹介されることもあります。(こちら参照)。
その二人が先週、中国北京で会談しました。プーチン氏は天安門広場で献花し、黙とうを捧げ、習氏がプーチン氏を引き寄せ抱擁する場面が報道されました。
この会談を、豪州ABC(NHK相当で無料)は “温かく同志的”だったと伝えました。中国政府は「ロシアとの関係を縮小しないと制裁する」という米国の圧力に動じず、「中国政府とロシア政府が、食料供給、エネルギー、軍事、ウクライナ、アジア等に関する一連の重要問題で団結し、今後も協力するだろう」と発表しました。
習氏は「今日の中ロ関係は苦労して築き上げたものであり、両国はそれを大切にし、育む必要がある。中国は両国の発展と活性化を共同で達成し、世界の公平性と正義を守るために協力する」、プーチン氏は「我々は共に正義の原則と、多極化の現実を反映し、これからも国際法に基づいた民主的な世界秩序を守っていく」と述べたと伝えられました。(詳しくはこちら)
過去には日本にも素晴らしいリーダーがいたかもしれません。アンラッキーだったのは、私たちがそれに気づかず、よきリーダーを守り、国の主権を守り、民主主義が反映されるシステムを確立しなかったことでしょう。その結果として生まれたのは、私利私欲のための政局と裏金パーティーに明け暮れる政治家たちでした。それもうやむやのまま終わらせ、政権と議員を続けようとしています。
政治の世界の構図は、“外国から干渉されない政治の自由(保守・主権を守る)” VS “他国からの干渉を許す自由(統一された世界)” に分かれ、対立しているようです。
日本は、どうするのか?
日本らしい民主政治は、実現できないのか?
それを国民が、政治家(候補者)と話し合う場をつくって欲しいという思いが募ります。
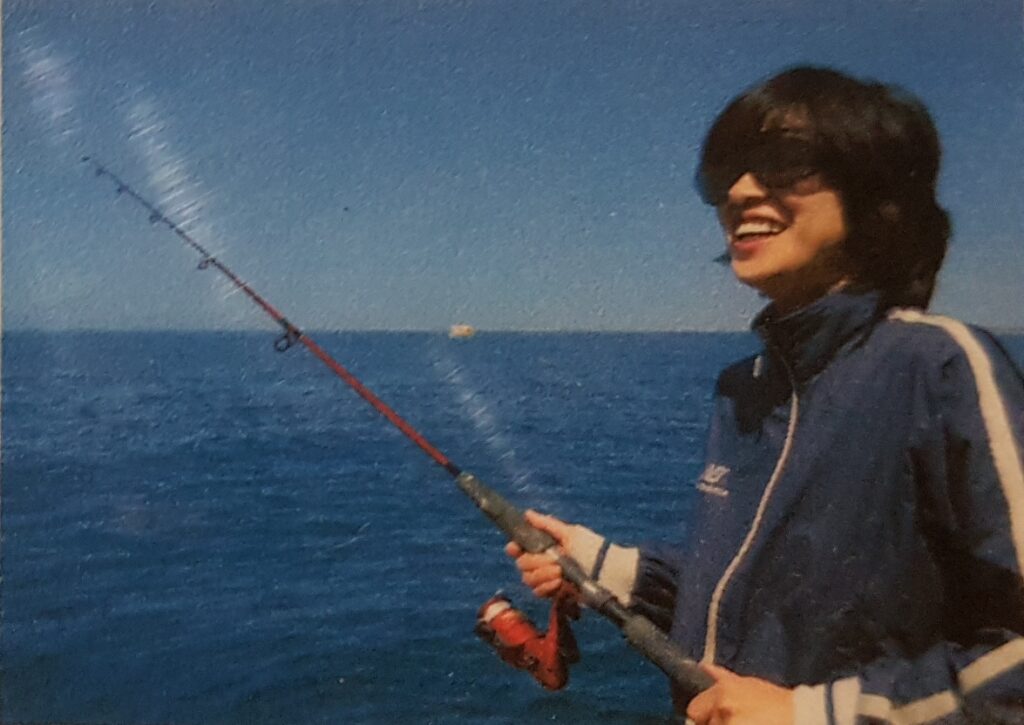
今滝 美紀(Miki Imataki) オーストラリア在住。 シドニー大学教育学修士、シドニー工科大学外国語教授過程終了。中学校保健体育教員、小学校教員、日本語教師等を経て早期退職。ジェネレーションX. 誰もがもっと楽しく生きやすい社会になるはず。オーストラリアから政治やあれこれを雑多にお届けします。写真は、ホームステイ先のグレート オーストラリアン湾の沖合で釣りをした思い出です。
