※この連載はSAMEJIMA TIMESの筆者同盟に参加するハンドルネーム「憲法9条変えさせないよ」さんが執筆しています。
<目次>
1.れいわ新選組と日本共産党が選挙協力を行う場合のメリット
2.「選挙区バーター+参院版コスタリカ方式」という考え方
3.れいわ新選組と日本共産党の間にあるしこり
4.おそらく「貨幣観の違い」を埋めることはできない
5.れいわ新選組が旗揚げ時のスタンスに立ち戻れば日本共産党と協力することは可能
6.日本共産党が「戦争法(安保法制)廃止の国民連合政府」を実現したいと今でも考えているなら山本太郎を首班候補にすることを本気で考えるべき
7.トピックス:森永卓郎さん逝去
1.れいわ新選組と日本共産党が選挙協力を行う場合のメリット
今回は、れいわ新選組と日本共産党の間の選挙協力の可能性について検討していきたいと思います。
まずは、三春充希さんが算出されている「リアルタイム得票数推定」の数字から見てみましょう。
各党の党名を正式なものに書き直すと、次のようになります。
自由民主党 1393万票
国民民主党 948万票
立憲民主党 835万票
公明党 569万票
日本維新の会 460万票
れいわ新選組 410万票
日本共産党 339万票
日本保守党 159万票
参政党 150万票
社会民主党 72万票
みんなでつくる党 20万票
もし、れいわ新選組の得票数推定値と日本共産党の得票数推定値を単純に合算すると749万票となり、公明党や日本維新の会の得票数を越えて、野党第一党の立憲民主党の得票数に迫る数値となります。
これだけの規模の得票数を持って、参院選の複数区で選挙協力を行うならば、選挙区での議席獲得の可能性がかなり上がってくるのではないでしょうか。
れいわ新選組は、2019年参院選で2議席(選挙区0議席、比例区2議席)、2022年参院選で3議席(選挙区1議席、比例区2議席)ということで、2025年参院選における改選議席は2議席ですので、参院選を単独で戦おうが、どこかの党と選挙協力して戦おうが、改選議席を越える議席を獲得できる可能性は濃厚であると言うことができます。
これに対して、日本共産党は、2019年参院選で7議席(選挙区3議席、比例区4議席)、2022年参院選で4議席(選挙区1議席、比例区3議席)ということで、2025年参院選における改選議席は7議席ですので、この改選議席をどれだけ守れるかが極めて重要です。
仮に1つ議席を減らしたとしても6議席取れれば「参議院10議席」の確保をが可能になりますが、それを下回った場合には、田村智子委員長を国会の「党首討論」の場に送り出すことができなくなります。
具体的に言えば、埼玉選挙区の伊藤岳さん、そして京都選挙区の倉林明子さんの議席を死守できるかどうかが、共産党の今後の党勢を占う意味でも、極めて重要になります。
2.「選挙区バーター+参院版コスタリカ方式」という考え方
こうした状況の下で、京都で活動している西郷南海子さんが「西郷応援団」を募集する動きを行っています。
これは、「参院選にチャレンジする」などと言及すると、「事前運動」となって公職選挙法に抵触してしまうおそれがあるため、漠然と「西郷応援団」を募集するという形になっていますが、実質的には、れいわ新選組の公認候補として夏の参院選に京都選挙区から出馬することを念頭に置いた動きであると考えることができます。
そうした状況をふまえたうえで、私からの提案として、「選挙区バーター+参院版コスタリカ方式」によるれいわ新選組と日本共産党の選挙協力という考え方を提示してみたいと思います。
れ共統一候補擁立プラン(関西編)
| 大阪選挙区 | 京都選挙区 | |
| 2025年参院選 | 大石晃子or八幡愛(れいわ) | 倉林明子(共産) |
| 2028年参院選 | 共産新人 | 西郷南海子(れいわ) |
れ共統一候補擁立プラン(関東編)
| 神奈川選挙区 | 埼玉選挙区 | |
| 2025年参院選 | 三好諒(れいわ) | 伊藤岳(共産) |
| 2028年参院選 | 浅賀由香(共産) | れいわ新人 |
近隣の選挙区でバーターを行ったうえで、3年後の参院選ではお互いに相手の党の候補者を推すという「選挙区バーター」と「参院版コスタリカ方式」を駆使した選挙協力のプランとなっています。
3.れいわ新選組と日本共産党の間にあるしこり
私としては積極的に提案したい「れいわ新選組と日本共産党の選挙協力」ですが、実際の状況としては、両党の間には大きなしこりが残っています。
両党の支持者の間では感情的なやり取りも多く見受けられ、「選挙協力」を進めていくことができそうな雰囲気は、ほとんど漂ってきません。
4.おそらく「貨幣観の違い」を埋めることはできない
それでも、れいわ新選組の支持者の中で、「共産党の人たちが『貨幣観』さえアップデートできれば、政策的には非常に近いところにいるので、一緒に(選挙協力などを)やっていくことができるのではないか」という声は少なくありません。
ところが、そうした声に水を差すように、しんぶん赤旗がNHK日曜討論における長谷川羽衣子さんの発言を「無責任な財源論」として批判しています。
れいわ新選組の支持者の中には、「共産党の人たちが『貨幣観』さえアップデートできれば」と考える人がかなりいるのですが、私個人の意見を言わせてもらえば、その可能性は限りなくゼロに近いのだろうと思います。
その理由は、共産党の議員や支持者の多くは「マルクス主義」を信奉していると考えられ、その思想的根幹をなすマルクス経済学において、「貨幣」は次のように認識されているからです。
商品の交換によって自分の欲望を満たそうと考える人が、自分の欲望を満たすこととは関係なく、ひとまず「売却力の大きな商品」を手に入れるようにする。人々がそのように行動していく過程で最終的に残った商品が「貨幣」(金)であり、「貨幣」とは端的に言えば「金」(Gold)である。
「共産党の人たちの貨幣観は、金本位制の時代からアップデートされていないのか」と思う人もいるかもしれませんが、決してそのようなことはなく、「管理通貨制度」の機能については知識としてしっかり頭に入れているはずですし、最近の「MMT」(現代貨幣理論)のことについても、中身を知っている人は少なくないと思います。
それでは、なぜれいわ新選組と共産党で貨幣観がこんなにも違うのかと言えば、共産党的な物の見方で言えば、「『貨幣』とは本質的には『金』(Gold)であり、管理通貨制度やMMT(現代貨幣理論)というものは、その本質を覆い隠し、資本主義の根本的な矛盾を隠蔽する、いわば詐術的な金融技法に過ぎない」といった感じで否定的に捉えているのだと思います。
それゆえに、「積極財政」という政策的な考え方に対しても、批判的な物の見方になるのです。
このように、「貨幣観」についての議論は、かなりイデオロギーの根幹に立ち入る本質的な議論になってしまうため、カジュアルに「共産党の人たちが『貨幣観』さえアップデートできれば」と期待できるような軽い話ではない、というのが私の見方です。
5.れいわ新選組が旗揚げ時のスタンスに立ち戻れば日本共産党と協力することは可能
れいわ新選組と日本共産党の間で「貨幣観の違い」を埋めることができないということを前提としたうえで、それでも私は両党の協力を模索することは可能なのではないかと考えています。
具体的な方法として、れいわ新選組が「消費税廃止に必要な財源」についての説明の仕方を、2019年の旗揚げ時の内容に戻せばよいのではないかと思うのです。
れいわ新選組旗揚げ時の最初の参院選では、山本太郎さんは消費税廃止に必要な財源の問題について、「財源は大きく分けて2つ。ひとつ、税、税金で取る。もうひとつ、新規国債の発行。」という言い方をしています。
消費税廃止に必要な財源の問題を「税金で取る」と言う場合には、日本共産党の主張と全く齟齬をきたすことはありません。
ですから、れいわ新選組と日本共産党が選挙協力を行う場合には、山本太郎さんは共産党の候補者の応援演説に立つ時には「税金で取る」という考え方で財源の話をし、れいわの候補者の応援演説に立つ時には「新規国債の発行」という考え方で財源の話をすればよいわけです。
そうすることで、れいわ新選組と日本共産党の間で政策的な面での対立はなくなります。
れいわ新選組はロスジェネと国民の生活を救うために、日本共産党は労働者と人民の暮らしを守るために、選挙において、共に協力していくべきです。
6.日本共産党が「戦争法(安保法制)廃止の国民連合政府」を実現したいと今でも考えているなら山本太郎を首班候補にすることを本気で考えるべき
政策的な対立要素がなくなったとすれば、れいわ新選組と日本共産党の間の選挙協力を阻む要素として残るのは、もっぱら「感情的な問題」ということになります。
共産党の支持者の立場からすれば「2021年の衆院選の滋賀県の選挙区で、1区は国民民主・2区は立憲民主・3区は共産・4区は立憲民主という住み分けを行って野党共闘の体制が成立していたのに、れいわが後からやってきて勝手に共産党の候補者がいる3区に候補者を立ててぶち壊しにした。」ということを恨みに思っているでしょうし、れいわの支持者からすれば「2024の衆院選では、れいわの現職候補がいる3つの選挙区(東京14区・千葉11区・大阪5区)で、立憲民主は候補者を出さずに選挙区を譲ってくれたのに、共産党は3つ全てに候補者を立ててきた。れいわの側は共産党の現職候補がいる沖縄1区からは候補者を降ろしたのに。」ということを恨みに思っているでしょう。
確かにそれはそうなのですが、今後、れいわ新選組と日本共産党がそれぞれ党勢の拡大を目指していくなら、そうした過去の経緯のことはグッと呑みこんで、お互いにとってメリットのある「選挙協力」の形を模索していくべきなのではないかと思います。
れいわ新選組にしても、日本共産党にしても、立憲民主党とはそれぞれ部分的な選挙協力ないしは選挙区の住み分けを行いながら選挙を戦ってきているわけですから、れいわ新選組と日本共産党との間の選挙協力も、同じように検討していくことは可能なはずです。
今年の夏に行われる参議院選挙では、複数区の選挙区があります。
6人区の東京選挙区は「自由競争」として考えるとして、4人区の埼玉・神奈川・愛知・大阪、3人区の北海道・千葉・兵庫・福岡、2人区の茨城・静岡・京都・広島は、もしれいわ新選組と日本共産党との間で選挙協力が実現するとするならば、いくつかの選挙区で議席の獲得が有望になってくるでしょう。
単純にれいわ新選組と日本共産党の得票数を足せば、公明党の得票数を越えられるような水準になってきていますので、公明党の現職議員がいる選挙区で、公明党に取って代わって議席を獲得できるチャンスが生まれてきます。
今の政治状況に風穴を開けていくためには、選挙区当選の公明党議員を選挙で落選させることが一番の近道です。
れいわ新選組と日本共産党が今回の参院選の2人区~4人区で選挙協力を行って成果を上げることができたなら、近い将来には、参院選の1人区や衆院選の小選挙区で「れ共統一候補が自民党や立憲民主党の現職から議席を奪う」といったことが実現できるようになるかもしれません。
5年後~10年後といった長いタイムスパンで考えた場合には、れいわ新選組は自民党に取って代わるつもりで、そして共産党は公明党に取って代わるつもりで、今後の党勢拡大を目指していくとよいのではないかと思います。
もしそれが実現するなら、例えば「衆院選でれいわ新選組と日本共産党が共に120議席をそれぞれ獲得し、両党が首班指名選挙で一致協力することで、衆議院で過半数を超えて、新たな政権を誕生させる」といったことさえ期待できるようになります。
安倍政権による2015年の安保法制強行採決から、早いもので10年近い歳月が流れようとしています。
10年前の強行採決のその時に、一人で牛歩して最後まで抵抗しようとしていたのが、当時「生活の党と山本太郎となかまたち」の共同代表だった山本太郎さんでした。
もし日本共産党が「戦争法(安保法制)廃止の国民連合政府」を実現したいと今でも考えているのであれば、国会の首班指名選挙では、立憲民主党の野田佳彦代表ではなく、れいわ新選組の山本太郎代表を首班候補にすることを本気で考えるべきなのではないでしょうか。
もちろんそれは、今すぐ実現できるような話ではありませんが、「選挙区バーター+参院版コスタリカ方式」という選挙協力のやり方を本気で実践していくなら、その先に見えてくる未来があるのではないかと思います。
7.トピックス:森永卓郎さん逝去
獨協大学経済学部教授の森永卓郎さんが、原発不明がんのため、1月28日(火曜日)に67歳でお亡くなりになりました。
森永卓郎さんは、亡くなられるその前日まで、自身の知見を少しでも世に広めようと、命の灯を燃やして、テレビ・ラジオ・ネット番組に精力的に出演されていました。
森永卓郎さんが火をつけた「ザイム真理教」に対する庶民の怒りの炎は、燎原の火のごとく燃え広がっています。
釈迦に説法で余計な話かなとも思いますが、元朝日新聞記者でNEWS23キャスターの筑紫哲也さんがお亡くなりになられた時には、国税庁が遺族に相続税の追徴課税をかけてきましたので、ご子息の経済アナリスト森永康平さんにおかれましては、これから行うことになる相続税の申告と納税の際には万全の対応を期すよう、くれぐれもご注意いただきたいと思います。
森永卓郎さんのご冥福を心よりお祈りいたします。
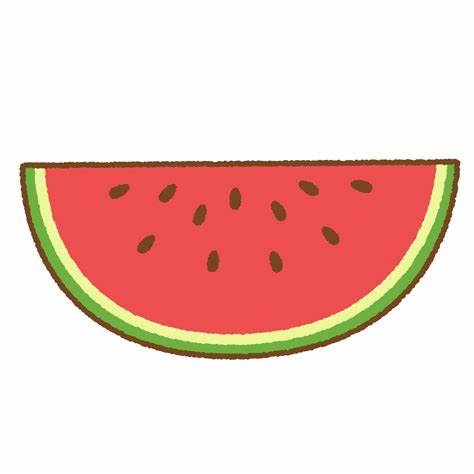
憲法9条変えさせないよ
プロ野球好きのただのオジサンが、冗談で「巨人ファーストの会」の話を「SAMEJIMA TIMES」にコメント投稿したことがきっかけで、ひょんなことから「筆者同盟」に加わることに。「憲法9条を次世代に」という一民間人の視点で、立憲野党とそれを支持するなかまたちに、叱咤激励と斬新な提案を届けます。

