※この連載はSAMEJIMA TIMESの筆者同盟に参加するハンドルネーム「憲法9条変えさせないよ」さんが執筆しています。
<目次>
0.はじめに
1.日本再生のための3つのプランA・B・Cの定義と相互関係
2.「プランA」のグローバル市場で、敗北が続く日本企業
3.日本でプランAを成功させる「前提条件の整備」だけで、最低10年は必要
4.前提条件を整備した後も、日本でプランAが成功する確率は非常に低い
5.トピックス:自民党総裁選あれこれ
0.はじめに
今回と次回の2回にわたって、兪炳匡(著)『日本再生のための「プランB」医療経済学による所得倍増計画』(集英社、2021年)を読んで、日本の社会・経済システムを刷新するための「日本再生プラン」について考えていきたいと思います。
兪炳匡さんは、早稲田大学人間科学学術院教授で、医療経済学を専門に研究しておられる方です。
日本の社会・経済システムを刷新するための「日本再生プラン」のうち、一般的に提唱される「プランA」がITやAI等を駆使したイノベーション誘導型の再生策であるのに対し、兪炳匡さんが提唱する「プランB」は、医療・教育・芸術を融合させて新たな分野での雇用を創出し、所得倍増を図っていくという斬新なアイデアです。
今回の記事では、一般的に提唱される「プランA」が日本では失敗に終わる危険性が高いというその理由について見ていきます。
次回の記事では、兪炳匡さんが提唱する「プランB」の内容と、その可能性について見ていきたいと思います。
1.日本再生のための3つのプランA・B・Cの定義と相互関係
最初に、「プランA」と「プランB」と「プランC」の定義と相互関係について見ていきましょう。
3つのプランの定義と相互関係
| 内容 | 実施主体 | 準備期間 | 失敗時の損失 | プラン間の相互関係 | |
| プランA | 米国(IT、バイオ、金融産業)を模倣するモデル | 首都圏と限られた地方都市のみ | 準備だけでグローバル水準まで10年以上(過去30年以上サボったツケ) | 甚大(例:薬1つ開発するのに1兆円) | プランBが準備・前提条件を支援 |
| プランB | 米国の成功と失敗を踏まえた、医療・教育・芸術を融合した新たな産業 | 全国の地方自治体、「非」営利組織 | 直ちに小規模から開始可能 | 小規模の損失ごとに軌道修正可能 | プランAが失敗した時の保険、プランCが出てくるまでの時間稼ぎ |
| プランC | 誰も知らない新たな社会・経済モデル | 全国の地方自治体、「非」営利組織 | 3世代(100年)?かかるかもしれない | 小規模の損失ごとに軌道修正可能 | プランBが種をまく、インキュベーター(孵卵器)として機能 |
出典:兪炳匡(著)『日本再生のための「プランB」医療経済学による所得倍増計画』(集英社、2021年)
今回の記事で取り上げる「プランA」について、兪炳匡さんは次のように述べています。
「プランA」と本書では呼ぶ、既存の日本の再生論の大筋は、過去30年間ほとんど変化していません。プランAは、米国や諸外国の成功例(特に情報・通信技術[IT]産業、バイオ技術産業、金融産業分野の大企業)を「つまみ食い」的に模倣すれば、日本で第二のグーグルやアップルのような企業が続出し、日本の経済成長率が大幅に改善するとの青写真を描いています。
(中略)
日本の指導者層は、特定の産業を選択した上で、限られた国内の財政・人的資源を集中させることによって、結果的にプランAが大成功することに賭けているようです。例えば、プランAに関連するITやバイオ企業を支援するために、補助金を含む様々な税制上の優遇策を設けています。また、プランA関連企業と大学の共同研究にも、政府は資金的・制度的に多大な支援を行ってきました。
残念ながら、過去30年にわたり、日本のプランAは失敗し続けました。米国のアップルやグーグルのような革新的なIT企業は生まれず、製薬企業では世界市場での占有率低下は止まりません。日本の金融系企業は、1989年に、時価総額にも基づく世界のトップ10企業の最上位4社を独占しました。しかし、2019年には、トップ10どころか、トップ100に残った金融系企業はゼロでした。
プランAの成功により、ふたたび1980年代、つまり「ジャパン・アズ・ナンバーワンの時代」が訪れるでしょうか?私は、日本の指導者層が採用しているプランAが、いままでの失敗を反転させ、今後10年以内に大成功するとは思えません。
ここからは私の感想になりますが、自民党総裁選で各候補者が語っている「日本再生プラン」も、基本的にはこの「プランA」ばかりであり、誰が新しい自民党総裁に選ばれたとしても、これまでの30年と同じように「プランA」に財政・人的資源を集中させる政策を進め、その挙句に惨めな失敗に終わるのだろうなぁ、という予感がしています。
2.「プランA」のグローバル市場で、敗北が続く日本企業
バブル崩壊後の30年間にわたって「プランA」のグローバル市場で敗北が続いている日本企業の様子について、兪炳匡さんは次のように述べています。
日経平均株価が史上最高値3万8957円を記録し、日本経済のピークとも言える1989年には、世界企業ランキングの上位20企業のうち、日本企業は14社を占めました。これら14社の内訳は、金融系(銀行、証券会社)が7社、製造業が5社、電力会社が1社、情報・通信業が1社でした。
1990年からの日本企業数の落ち込みは、コラムニストの小田嶋隆氏による「墜落」という表現が的確です(日経ビジネス電子版、2019年12月13日)。上位20企業にランクインした日本企業は、1997年に3社、2010年以降はゼロです。上位50企業にランクインした数は、1989年に32社、1997年に4社、2010年以降は、わずか1社(トヨタ自動車)のみ。上位100企業の数は、1989年、1997年、2010年、2019年にそれぞれ53社、13社、5社、2社(46位のトヨタ自動車と、83位のソフトバンクのみ)という数字を辿っています。わずか30年で、日本の企業レベルの国際競争力は、大幅に低下しました。
また、兪炳匡さんは、ハーバード大学ビジネス・スクール教授のクレイトン・クリステンセンさんの分析を次のように紹介しています。
日本の存在感が低下した理由の一つは、世界中からヒト・カネを集められる魅力的な企業またはビジネスモデルが、1990年代以降の日本で生まれなかったからです。
ハーバードビジネス・スクール教授のクレイトン・クリステンセン氏は、過去の日本の企業戦略におけるイノベーション戦略を分析しました。その分析手法として、利益増大の視点から、イノベーションを、(1)「市場開拓型(破壊的)イノベーション」、(2)「持続的イノベーション」、(3)「効率化のためのイノベーション」の3つのタイプに分類したものを用いました。
この分類の一つめは、過去になかった製品・サービスを開発し、新しい市場を開拓するイノベーションです。近年の成功例は、「iTunes」などを開発したアップルです。日本経済がピークだった1990年以降、このタイプのイノベーションで成功した日本のケースは、任天堂のゲーム「Wii」の一例だけであると、同教授は指摘しています。
世界的に売れているトヨタ自動車のハイブリッド車の評価は、あまり高くありません。なぜなら、ハイブリッド車が売れる台数だけ、ガソリン車の販売台数が減少するため、自動車全体の市場のサイズそのものは変わらないからです。ですから、ハイブリッド車の開発は、同氏のイノベーションの二つめのタイプ、「持続的イノベーション」に含まれます。
この二つめのタイプのイノベーションは、既存の製品を改善するだけで、企業の成長につながらないと同氏は厳しい評価をしています。
三つめの「効率化のためのイノベーション」は、成熟した製品の低価格版を既存顧客層に売るタイプのイノベーションです。成功例は、格安販売モデルを定着させた世界最大の小売業、米国のウォルマート・ストアーズです。このタイプのイノベーションの負の側面は、雇用の減少を招くことです。低価格な商品を購入できることは、消費者としては望ましいことかも知れません。しかし、それが「雇用減少と賃金低下」を伴う場合、手放しでは歓迎できません。
なぜなら、この「効率化のためのイノベーション」の中身のほとんどは、「コスト・カット」だからです。」もちろん、何らかの技術革新やマーケティングを含むマネージメントの革新による「コスト・カット」も可能です。しかし、日本の多くの企業はこれまで、雇用者の賃金カットないし雇用者数のカット(つまり、クビ)という最も安易なイノベーションに頼ってきました。日本の企業が一斉に賃金抑制に走り、その結果、日本国内需要が冷え込み、需要低下にもかかわらず、企業利益を確保するため、さらに賃金抑制を行うという悪循環に陥っています。
さらに、兪炳匡さんは、一橋大学名誉教授の野口悠紀雄さんの分析を次のように紹介しています。
政府の政策は、「プランA関連の日本企業支援」を掲げながら、明らかに失敗し続けました。一橋大学名誉教授の野口悠紀雄氏は近著において、以下のように述べています。
最も重要な点として、経済回復の政策が、戦後の高度成長期以来現在まで、輸出主導型経済を堅持していることを挙げています。政府は、ただひたすら企業の輸出を増やすため、大規模な為替介入を行い、円安誘導してきました。
円安下では、企業努力がなくても、海外に輸出する日本製品の価格が低下します。その結果、価格競争力が上がるため、短期的には輸出を増大させます。しかし、為替介入が長期化すれば、企業は政府の為替介入に依存し、技術革新や産業転換への動機が低下し、競争力の低下が加速します。
リーマン・ショック前の円安の時期に、日本企業の経営者は産業衰退の本当の理由を追求せず、円安にさえなれば日本の過去の繁栄が再現できると誤解しました。このことから、野口氏は、企業経営において「円安は麻薬」とまで述べています。
ここからは私の感想になりますが、小泉内閣時代の2004年に行われた「製造業の派遣解禁」こそがバブル崩壊後の最大の「効率化のためのイノベーション」であり、そのことと「為替の円安誘導」の2つがバブル崩壊後の自民党政権における経済政策分野の目玉政策(そのどちらも麻薬)だったのではないかという気がしています。
そのことがもたらした結果は、非正規雇用の拡大による賃金の低下と企業利益の増大、そして、円安による輸入品の物価高と輸出企業の円貨換算利益の増大(ドル建てで輸出した商品の売上を円に換算した場合の利益金額の増大)ということになります。
典型的な形で言えば、海外輸出を行う製造業にとって有利な環境を整えたことは間違いないわけで、そのことによって企業利益は増大し、日経平均株価もバブルの時期を上回るようになりましたので、そうした一部の大企業にとっては自民党の経済政策は「一定の果実をもらたした」と言えるものなのだと思います。
しかし、そうした恩恵を受けた一部の大企業でさえ、「世界におけるプレゼンス(影響力)」という点ではバブル期と比較して見る影もない惨憺たる有様となっています。
さらに、庶民にとっては、派遣労働などの非正規労働者として働かなければならなくなった者は低賃金に苦しみ、それ以外を含む国民全体としても円安による輸入物価の高騰で生活水準の低下に見舞われたわけで、全体として見てみれば、バブル崩壊後の自民党の経済政策は「大失敗だった」と結論づけることができると思います。
3.日本でプランAを成功させる「前提条件の整備」だけで、最低10年は必要
日本で「プランA」を成功させるための「前提条件の整備」の問題について、兪炳匡さんは次のように述べています。
日本政府がプランAを継続するならば、そのための環境整備が必要ではないか、そして、それはすぐに始めることができるのか、という点を吟味してみたいと思います。
私の理解では、前提条件にたどり着くまで、つまり、環境が整備されるまでに最低10年はかかると思われます。
前提条件を考える際の二つのキーワードは、「人材不足」と「エリート層の間での競争不足」です。これらの二つのキーワードは、密接に関連しています。むしろ、意図的な「競争の回避」の結果、国際社会と比較した時の決定的な「人材不足」という惨状を招いているとも言えます。
意図的な「競争の回避」の一例は、エリート層の間で行われている競争から、女性が構造的に排除されていることです。この排除の構造は、国際比較を行うと容易に可視化できます。その一例が、「男女平等ランキング」として日本のメディアにもよく取り上げられる「世界ジェンダー・ギャップ報告書」です。
(中略)
なぜ日本国外のプランAの成功者たちは、男女平等に興味があるのでしょうか?
それは、「男女平等ランキング」と「経済的な国際競争力のランキング」には、強い相関関係があるからです。すなわち、前者のランキングの上位国と後者のランキングの上位国は重複しています。北欧諸国がその代表例です。もちろん、相関関係は必ずしも因果関係を意味しません。しかし、日本が近年、これらの二つのランキングにおいて、同時に低下していることは、因果関係を示唆します。
可能性のある因果関係の一つは、「能力にふさわしい社会的地位を女性に与えない社会は、人的資源の有効活用に失敗している。ひいては、社会全体の経済的競争力が低下する」という説明です。日本の女性差別が、競争力低下の一因であることの説明でもあります。
「利用可能な人的資源を最大限に活用するという経済戦略的思考」または「男女平等を含む、基本的人権の尊重という価値観」の、少なくとも一方を持つ個人・社会なら、「男女平等を実現する政策・制度」に賛成できます。
従って、「男女平等ランキング」で逆走している国は、これら二つを同時に否定する方向に舵を切ったと国際社会から判断されるでしょう。別な言い方をすれば、男女平等の実現に消極的でありながら、資源の有効活用や経済効率の向上を主張するならば、それは自己矛盾だと言えます。
(中略)
プランAが想定するタイプのイノベーションを創出する人材を、これまでどおり、日本国内の男性のみで供給することが絶望的であることは明らかです。
日本国内で研究者を教育・供給することが絶望的に困難な上、海外留学も円安などが理由で減少傾向にあります。この状況の、根本的かつ即効性がある対処方法は、外国人研究者を日本の大学・企業内研究所で雇用することです。この提案は、事前科学分野のノーベル賞研究の多くが掲載された学術誌「ネイチャー」の編集長のインタビューや、外交分野で国際的に評価の高い雑誌「フォーリン・アフェアーズ」の日本特集記事、先述の「タイムズ・ハイヤー・エデュケーションズ」の記事でも、異口同音に薦められています。
つまり、日本は諸外国に比べ、外国人研究者の割合も極端に低いことを、これらの雑誌は問題視しているのです。米国を含めた諸外国は、大学教員・学生の多様性を確保する(性別、人種・民族、社会階層などによる偏在・差別をなくす)ために、様々な研究費・奨学金を設けています。その理由は、「平等な社会の実現を目指す」だけではありません。「ネイチャー」の編集長が述べているように、「多様な視点を持つことは、研究分野に限らず、生産性や創造性が増し、よりよい成果を得られることがわかっている」ためです。
(中略)
日本の大学が、主要先進国レベルに追いつくためには、研究費と研究人員を少なくとも1.5~2倍に増加させる必要があります。この目標を達成する際には、新たに雇用する研究者(特に教授クラス)に女性・外国人をできる限り多く含めるべきでしょう。
(中略)
日本の大学・企業・政府が、外国からの人材の招聘を真剣に考えているのか、私には疑問です。日本は、女性だけでなく、外国からの人材も「できる限り」意図的に排除しているように見えます。そうすれば、日本のエリート層の男性は、さらにぬるい競争を享受するでしょう。果たして、それで良いのでしょうか?
ここからは私の感想になりますが、一部のオジサンたちが享受する「ぬるい競争」の裏側で「酷い競争」が起きているという表裏一体の構造を問題視する必要があるのではないかと感じています。
つまり、一部のオジサンたちが「ぬるい競争」を享受しているせいで、女性の側には少ないポジションを多くの人々で奪い合う「酷い競争」が発生してしまっているわけであり、このことの不公正さは、もっと問題視されるべきだと思います。
また、「男女間の不公平」だけではなく「世代間の不公平」という問題に関しても、同じような構造の問題が発生しているのではないかと思いました。
例えば、「バブル世代」の人々は新卒の就職活動の際に楽勝な「ぬるい競争」で志望企業に就職内定し、我が世の春を謳歌したわけですが、バブル崩壊後の「就職氷河期世代」は新卒の就職活動の際に絶望的な「酷い競争」にさらされ、その後、社会に出てからも、正規雇用者、非正規雇用者ともに、辛い労働環境を甘受させられ続けています。
一周回って、今の若者の「Z世代」の人々は新卒の就職活動で「売り手市場」の「ぬるい競争」が復活し、初任給も大幅に上昇していますが、そのことで、その上の世代の人々との間に不公平感が生じ、一つの社会問題になっています。
さらに言えば、不公平な競争条件による「ぬるい競争」の弊害が最も顕著に出ているのは、政治の世界なのではないかという気がします。
選挙の際の「政党要件」や「供託金」など様々な制度上の不公平により、政治の世界では「現職」や「世襲政治家」が圧倒的に有利で、「新規参入組」には様々な参入障壁が大きな壁として立ちはだかっています。
結果的にこのことが日本の政治の質を決定的に劣化させてしまっていると言っても過言ではありません。
問題の解決策として兪炳匡さんが挙げている「外国からの人材の招聘」は、ビジネスの世界や学問の世界ではソリューションとなる可能性が期待できますが、政治の世界に関して言うなら、この分野だけはどうしても「外国からの人材の招聘」に頼ることができませんので、別な方法で「人材不足」を解決していくしかありません。
また、「女性人材の登用」という処方箋も、長期的に見れば着実に進めていく必要があると思いますが、短期的に見た場合にソリューションになると言えるのかどうか、私は懐疑的にならざるを得ません。
というのも、東京都知事の小池百合子さん、連合会長の芳野友子さん、検事総長の畝本直美さんといった「女性初の○○」という人たちを見るにつけ、「これなら男性の前任者の方がだいぶマシだった」という感想を持たざるを得ないからです。
いま行われている自民党総裁選で高市早苗さんが新しい自民党総裁に選ばれて、さらに国会の首班指名選挙でも勝って「女性初の総理大臣」に就任したとしても、やはり同じように「これなら男性の前任者の方がだいぶマシだった」という感想を持つことになるでしょう。
人種や性別といった属性の問題を軽視するというわけではありませんが、そうした属性の問題以前の根本的な考え方として「競争の健全性と公平性の確保」に努めていくようにしなければ、日本の各分野での「人材不足」(人材需要と人材供給の偏り)の問題は解決することができないのではないかと思います。
4.前提条件を整備した後も、日本でプランAが成功する確率は非常に低い
日本で「プランA」を成功させるための「前提条件の整備」が仮に上手くいったとしても、それでもなお日本で「プランA」が成功する確率は非常に低いとして、兪炳匡さんは次のように述べています。
十分な数の人材だけでは、日本国内のプランAが成功する確率は依然として非常に低いと考えられます。(中略)
最も深刻な理由は、(中略)日本の「国家主権(自己決定権)」の不足です。日本の総合的な経済力・国力が現在よりもはるかに強かった1980年代から1990年代ですら、日本政府は米国政府に要請されるまま、自国の産業を衰退させる政策を採りました。
代表されるのが、米国政府の要請を受け入れた「日米半導体協定(1986~96年)」と「時価会計の導入(1997年)」です。これらの日本政府の譲歩が原因で、日本の半導体産業と金融産業は、1980年代に世界最強と呼ばれた地位を、1990年代以降、米国に譲りました。
日本政府が、今後も自国の国家主権(自己決定権)の回復を目指さない限り、米国政府の胸三寸で、日本で新たに成功した産業・企業が、「日本」政府により再度衰退させられる可能性は高いままです。
短期間で日本の国家主権の回復が期待できないなら、米国政府の干渉を受ける確率が「低そうな」新産業分野を慎重に選び、その開発のために、日本の資源を集中させたほうが良いと考えます。
それにはまず、米国政府の干渉を受ける確率が「高そう」な分野を考えることです。
ここで過去の歴史を見てみましょう。
(中略)
例えば、大型航空機や人工衛星の開発は、民間部門でも需要がありますが、ただちに軍事部門に転用可能ですので、強い規制がかかりました。具体的には、日本は航空機の開発・製造・修理を戦後7年間禁じられ、その影響は後々まで長く尾を引き、現在も欧米先進国から立ち遅れていると、日本航空宇宙工業会は報告しています。
半導体産業を含むIT産業も軍事技術と関連が高いため、米国政府は日本の半導体産業が優位となるのを懸念しました。米国政府が、日米半導体協定を冷戦時代の1986年に開始したのは、戦後の対日政策の一環だったとも言えます。(中略)
現在の日本のプランAは、IT産業、とりわけ軍事・安全保障分野と高い関連を持つ人工知能(AI)産業で高い競争力を持つことを目指しています。しかし、米国の懸念が続く限り、その成功は期待できないでしょう。仮に、近い将来、日本企業がAI分野で華々しく成功したとしても、「日米半導体協定(1986~96年)」の改訂版である「日米AI協定」が結ばれ、日本のAI産業が失速する可能性が濃厚だからです。
「外圧」ゆえにIT産業の先行きが不確実なら、日本のプランAのもう一つの柱であるバイオ産業はどうでしょう。
バイオ産業の技術の中には、生物兵器に用いることが可能なものもあり、軍事・安全保障分野と無関係ではありません。しかし、抗がん剤などの新薬開発や再生医療は、IT・AIに比べれば軍事・安全保障分野とは関連が低いので、米国政府の干渉を受ける可能性は低いかも知れません。
しかしながら、日本のバイオ産業が、現在の自動車産業や過去の電機産業のように長期間にわたり安定した雇用と利潤を生む産業になる確率は、極めて低いと私は考えます。(中略)
新薬として成功する条件の一つは、米国市場で販売するため、米国食品医薬品局(FDA)の厳しい審査を受けて承認されることです。(中略)
米国FDAが承認する新薬をたった一つ生むために必要な投資額は、1950年の「確率的に約20億円」に比べると、2020年にはなんと約500倍の「確率的に約1兆円」になります。
この「確率的に約1兆円」とは、仮に1兆円を投資しても、「成功する新薬がゼロ」になる可能性があることを意味します。コインを投げて表の出る確率が2分の1なら、コインを2回投げれば確率的に一度は表が出ます。しかし、コインを2回投げても、表が一度も出ない可能性があるのと同じです。
日本政府の一般会計の総支出の10パーセントに近い10兆円投資すれば、成功する新薬が10程度期待できます。しかし、このような巨額な資金を集めることは、民間でも極めて困難です。そもそも、ハイリターンであってもハイリスクである薬開発事業は、民間で資金に余裕のある投資家(投資にリターンがなくても生活が困窮しない人々)に任せるべきだと、私は考えます。それを「民間から巨額な資金が集めにくい」という理由で、リスクが高い新薬開発に直接税金を投入することは、正当化が極めて困難です。
また、新薬開発のために特定の企業に補助金として直接公的資金を投入することは、汚職の温床にもなります。
さらに、純粋に科学的エビデンスだけを根拠に補助金の給付先を決めることは、新薬開発の性質上、困難です。投資した公的資金が回収できなくても、新薬開発はハイリスクであることを盾に、容易に責任を逃れることができます。従って、このような公的資金の投入は、十分な透明性を確保できない限り、すべきではありません。
さらに、兪炳匡さんは、慶応大学名誉教授の金子勝さんの分析を次のように紹介しています。
日本政府は日米半導体協定以降、イノベーションに関しては、先端技術を含む産業戦略を立てるのに失敗してきたというより、放棄してきたと言ってよいだろうと、金子勝氏(立教大学特任教授、慶応大学名誉教授、経済学者)は述べています。このような日本の国家戦略の不在・放棄の理由は、「どうせ新産業を育成しても、過去の半導体産業のように米国政府の胸三寸で『お取り潰し』にあうかも知れない」という諦めが、日本のエリート層に根強いためかも知れません。
ここからは私の感想になりますが、「仮に日本のIT産業(とくにAI産業)が今後大成功を収めたとしても、『日米AI協定』のようなものが結ばれて、強制的に失速させられてしまうだろう」とか、「新薬開発のリスクの高さを冷静に考えれば、日本のバイオ産業に現在の自動車産業や過去の電機産業のような役割を果たすことを期待するのは無理がある」という趣旨の兪炳匡さんの主張は、非常に説得力があると感じました。
つまり、「プランA」に期待するのは、全くの無理筋だということです。
そこで、「医療・教育・芸術を融合させて新たな分野での雇用を創出し、所得倍増を図っていく」という「プランB」が登場することになるわけですが、それについては、次回の記事でじっくり見ていくことにしたいと思います。
5.トピックス:自民党総裁選あれこれ
投開票日が3日後に迫る自民党総裁選ですが、内容的には低調な選挙戦が続いています。
どの候補が新総裁に選ばれたとしても、日本維新の会を連立政権内に引き込んで「自公維」の枠組みで「ポスト石破」の新政権を誕生させることが既定路線のようで、野党側が結束して「政権交代」を実現する可能性については誰も真剣に考えておらず、新聞やテレビだけではなく、ネットメディアもみんな「自民党総裁選」の話題に首ったけの様子です。
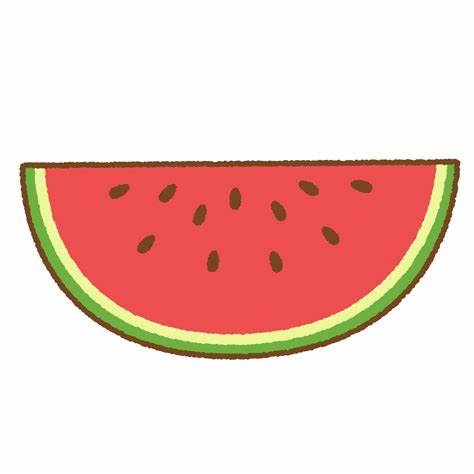
憲法9条変えさせないよ
プロ野球好きのただのオジサンが、冗談で「巨人ファーストの会」の話を「SAMEJIMA TIMES」にコメント投稿したことがきっかけで、ひょんなことから「筆者同盟」に加わることに。「憲法9条を次世代に」という一民間人の視点で、立憲野党とそれを支持するなかまたちに、叱咤激励と斬新な提案を届けます。

