※この連載はSAMEJIMA TIMESの筆者同盟に参加するハンドルネーム「憲法9条変えさせないよ」さんが執筆しています。
※今日は連載100回記念。過去記事アクセス数ベスト10と、議員定数削減問題について論じています。
<目次>
1.連載100回を記念して
2.過去記事アクセス数ベスト10
3.トピックス①:高市政権誕生
4.トピックス②:議員定数削減問題
5.トピックス③:村山富市元総理逝去
1.連載100回を記念して
2022年1月12日に掲載を始めた「立憲野党私設応援団 ~限界を乗り越えて、みんなで世直しを始めよう~」ですが、おかげさまで今回の記事で連載100回を迎えることとなりました。
私の拙い記事に4年近くお付き合いいただいたSAMEJIMA TIMES主筆の鮫島浩さんと、記事にアクセスして閲覧したりコメントを書いたりしていただいた読者のみなさまに、深く感謝申し上げます。
今回は、連載100回を振り返る意味で、過去記事アクセスランキングを見ていきます。
2.過去記事アクセス数ベスト10
前回までの99回の記事のうち、アクセス数ベスト10にランクインした記事は、次の通りです。
立憲野党私設応援団過去記事アクセスランキング
| 順位 | 連載回 | 記事タイトル | 掲載日 |
| 第1位 | 第3回 | れいわ新選組への期待と不安【期待編】 | 2022年2月9日 |
| 第2位 | 第18回 | 長谷川ナイフ論争について考えてみる | 2022年9月7日 |
| 第3位 | 第4回 | れいわ新選組への期待と不安【不安編】 | 2022年2月23日 |
| 第4位 | 第16回 | 真夏の夜の夢「山本太郎内閣誕生す」 | 2022年8月10日 |
| 第5位 | 第42回 | 真夏の夜の夢2「れいわ民主党誕生す」 | 2023年8月9日 |
| 第6位 | 第40回 | れいわ新選組の衆院選戦略について考える | 2023年7月12日 |
| 第7位 | 第65回 | 蓮舫都知事誕生へ向けての提言 | 2024年6月26日 |
| 第8位 | 第1回 | 立憲野党応援宣言~庶民の声で世直しを~ | 2022年1月12日 |
| 第9位 | 第36回 | れいわ新選組への提言 | 2023年5月17日 |
| 第10位 | 第20回 | 長谷川ナイフ論争について再び考えてみる | 2022年10月5日 |
いくつかのカテゴリーに分類しながら、それぞれの記事について振り返っていきましょう。
第1回:立憲野党応援宣言~庶民の声で世直しを~(2022年1月12日掲載)
まず、連載第1回の「立憲野党応援宣言~庶民の声で世直しを~」(2022年1月12日掲載)が、第8位にランクインしています。
連載第1回の記事で、私は「2025政権奪取プラン」というタイムスケジュールを提示しました。
次期衆議院選挙が任期満了に近いものになると仮定して、「2025政権奪取プラン」というタイムスケジュールを提示したいと思います。
2022年7月参議院選挙:自公与党過半数割れの実現(衆参ねじれ国会)
2025年7月参議院選挙:立憲野党過半数確保の実現(政権交代にリーチ)
2025年10月衆議院選挙:立憲野党過半数確保の実現(政権交代)
私の「立憲野党私設応援団 ~限界を乗り越えて、みんなで世直しを始めよう~」の連載は、2週間で1本のペースとなる予定ですので、約4年でおよそ100本の原稿を執筆する計算になります。
世の中には「100日後に○○する~」というシリーズが数多くありますが、私が原稿を100本執筆する間に「政権交代」が実現し、「立憲野党」が「立憲与党」になって、私の連載が「大団円」を迎える、というのが現時点での私の構想です。
政治的なタイムスケジュールはだいぶ違いますが、衆議院でも参議院でも「自公与党過半数割れ」という状況が生まれたのは、私が期待していた通りの展開でした。
2025年秋の臨時国会の首班指名選挙、立憲民主党幹事長の安住淳さんは、与野党入り乱れての事前の多数派工作の政局で、「どんなに世の中から批判されようと何だろうと、あと48票死に物狂いで集めるためだったら、何でもやらせて貰います」と高らかに宣言しました。
しかし、実際の結果は、衆議院で決選投票に持ち込むことすらできず、1回目の投票で自民党総裁の高市早苗さんに過半数獲得を許す惨敗。
高市早苗さんが過半数を獲得したのは事前の多数派工作で日本維新の会が自民党側に付いたことによるものですが、立憲民主党に「あと48票死に物狂いで集める」という意志が本当にあったなら、首班指名選挙の第1回投票で「斉藤鉄夫」と書くか「玉木雄一郎」と書くかして野党側の票を積み上げる努力をすべきで、立憲民主党は懲りずに「野田佳彦」の名前を書き、やる気のなさを満天下に晒しました。
決選投票に持ち込まれた参議院のほうでも、2回目の投票で共産党にさえ「野田佳彦」の名前を書いてもらえない不人気ぶりで惨敗。
小川淳也さんが立憲民主党の幹事長を務めていた2024年秋の特別国会では、衆議院での決選投票の際に立憲民主党だけはなく共産党にも「野田佳彦」の名前を書いてもらい、今回よりも自民党の首班候補(当時は石破茂さん)に迫ることができていました。
安住淳さんは、確かに弁は立ちますが、野党第一党の幹事長としてテレビに出まくって立憲民主党の存在感をアピールして、立憲民主党の支持率を押し上げる仕事をしただけで、「野党をまとめて政権交代を進める」という仕事は全くできませんでした。
その点では、誠実な小川淳也さんが幹事長を務めていた時の方が、多少なりとも「野党をまとめる」という仕事ができていました。
第65回:蓮舫都知事誕生へ向けての提言(2024年6月26日掲載)
次に、連載第65回の「蓮舫都知事誕生へ向けての提言」(2024年6月26日掲載)が、第7位にランクインしています。
ベスト10にランクインしている記事のほとんどがれいわ新選組に関するものとなっている中で、この記事は例外的に立憲民主党に関する記事になっています。
この時の都知事選では、日本全国のたくさんの人々が蓮舫さんのためにプラカードを持って街頭に立ち、リベラル界隈は大いに盛り上がりました。
しかし私は、「選挙戦で野田佳彦元総理が蓮舫さんの応援演説に立つなら、結果として小池百合子さんが都知事再選を果たしてしまうのではないか」という懸念を持っていました。
2020年の東京都知事選でも選挙戦終盤で野田佳彦元総理が宇都宮健児さんの応援演説を行っていて、その時にはtwitterで「あぁ、これで宇都宮健児は10万票減らしたな」という誰かのツイートが流れてきました。
そのツイートを見て、私は「いくら野田さんに人気がないといっても、それは言い過ぎだろう」と思ったのですが、実際には次のような結果となりました。
宇都宮健児さん東京都知事選挙得票推移
2012年(平成24年):968,960票
2014年(平成26年):982,594票
2020年(令和2年):844,151票
10万票どころか、なんと、138,443票も票を減らしていたのです!
2012年と2014年は共産党と社民党などが宇都宮健児さんを応援してこの獲得票数だったのですが、2020年の選挙では独自候補を擁立できない立憲民主党がこれに抱きついてきて、(形式的には支援体制が拡充したはずなのに)結果として宇都宮陣営は13万票以上も得票を減らしてしまいました。
これは「立憲民主党の党としての人気のなさ」によるものなのか、「野田佳彦さん個人の人気のなさ」によるものなのか、判然としないところもありますが、北海道で池田真紀さんが初めて「野党共闘」で選挙戦を戦った時から私はずっと「野党共闘」をウォッチし続けていますので、少なくとも私の中では「野田佳彦さんが出てくると、ろくなことがない」という印象を非常に強く持っています。
実際の選挙戦では、野田佳彦元総理と枝野幸男元官房長官が延々と「立憲土俵入り」の応援演説を繰り返し、蓮舫さんは2位どころか、石丸伸二さんにも敗れて3位に沈む大惨敗でした。
私もこの4年間で記事を100回書いてきたわけですが、いろいろあっても、結局のところ「野田佳彦さんが出てくると、ろくなことがない」という結論に至ってしまうという感想を持たざるを得ません。
第40回:れいわ新選組の衆院選戦略について考える(2023年7月12日掲載)
さて、アクセス数ランキング第9位には連載第36回「れいわ新選組への提言」(2023年5月17日掲載)が、第6位には連載第40回「れいわ新選組の衆院選戦略について考える」(2023年7月12日掲載)が、それぞれランクインしています。
れいわ新選組の選挙戦略を考えるにあたり、民主党が政権を獲るまでの歴史を振り返ったうえで、その推移をれいわ新選組に当てはめてみたいと思います。
民主党衆院選獲得議席推移
第41回衆議院選挙(1996年): 52議席
第42回衆議院選挙(2000年):127議席
第43回衆議院選挙(2003年):177議席
第44回衆議院選挙(2005年):113議席
第45回衆議院選挙(2009年):308議席(政権交代)
第46回衆議院選挙(2012年): 57議席(下野)
第47回衆議院選挙(2014年): 73議席
主要野党衆院選獲得議席(抜粋)
| 衆院選 | 立憲民主党 | 希望の党 | 国民民主党 | 日本維新の会 | 日本共産党 |
| 第48回(2017年) | 55議席 | 50議席 | ― | 11議席 | 12議席 |
| 第49回(2021年) | 96議席 | ― | 11議席 | 41議席 | 10議席 |
れいわ新選組が今後議席倍増や3倍増・4倍増を繰り返していくと仮定して、目標数値を書き出してみます。
れいわ新選組衆院選獲得議席実績および目標
第49回衆議院選挙(2021年):3議席(社民超え)
第50 回衆議院選挙(未定):6議席~12議席(国民、共産超え)
第51回衆議院選挙(未定):20議席~50議席(公明超え)
第52回衆議院選挙(未定):60議席~100議席(立憲、維新超え)
第53回衆議院選挙(未定):240議席~300議席(自民超え)
かなり楽観的な仮定をおいたとしても、れいわ新選組が衆議院で単独過半数を獲るためには、最低でもこれから4回~5回程度の衆院選を経る必要があるという計算になります。
まっくろ助
これ―イカダで太平洋渡るようなプロジェクトなんですよ
あなたも一緒にどうですか
これは前回の衆院選の1年以上前に書いた記事ですが、2024年の衆院選で、れいわ新選組は「共産超え」と「3議席から9議席へ議席3倍増」を果たすことができており、「イカダで太平洋を渡るプロジェクト」は、現時点では割と順調に進んでいるというふうに言うことができるのではないかと思います。
第18回:長谷川ナイフ論争について考えてみる(2022年9月7日掲載)
第20回:長谷川ナイフ論争について再び考えてみる(2022年10月5日掲載)
アクセス数ランキング第2位には連載第18回「長谷川ナイフ論争について考えてみる」(2022年9月7日掲載)が、第10位には連載第20回「長谷川ナイフ論争について再び考えてみる」(2022年10月5日掲載)がそれぞれランクインしています。
twitter上では、鮫島さんの司会による長谷川ういこさんとDr.ナイフさんの対談の実現を心待ちにする声があがっています。
これは、まだ人々の間に「積極財政」の考え方が浸透していない時期の記事でした。
その後の実際の政治の動きとしては、2024年の衆院選で「積極財政」の政策を掲げる国民民主党とれいわ新選組が躍進し、2025年の参院選でも「積極財政」の政策を掲げる国民民主党と参政党が大きく議席を伸ばすという状況が生まれています。
ちなみに、10月21日に発足した高市早苗内閣も「積極財政」を掲げていますが、高市政権の「積極財政」はその多くが「防衛費の拡大」に振り向けられるようで、庶民の暮らしはほとんど良くならずに、アメリカの軍産複合体を潤すだけの結果となりそうな雲行きです。
第16回:真夏の夜の夢「山本太郎内閣誕生す」(2022年8月10日掲載)
第42回:真夏の夜の夢2「れいわ民主党誕生す」(2023年8月9日掲載)
アクセス数ランキング第4位には連載第16回「真夏の夜の夢『山本太郎内閣誕生す』」(2022年8月10日掲載)が、第5位には連載第42回「真夏の夜の夢2『れいわ民主党誕生す』」(2023年8月9日掲載)が、それぞれランクインしています。
いずれも私が書いた政治小説ですが、「山本太郎内閣誕生す」では、架空の「2025年衆議院解散総選挙」の選挙結果を次のように設定しています。
立憲民主党:171議席
自由民主党:170議席
れいわ新選組:35議席
公明党:34議席
日本共産党:20議席
国民民主党:11議席
日本維新の会:11議席
NHK党:1議席
参政党:1議席
社会民主党:1議席
無所属:10議席
私が書いた小説では、野党第一党に立憲民主党、野党第二党にれいわ新選組という状況の下で、れいわ新選組が与党入りして、自民・公明・れいわの連立政権で山本太郎総理が誕生するというストーリーになっていました。
2025年の現実の衆議院の議席配分は、野党第一党に立憲民主党、野党第二党に日本維新の会という状況で、公明党が連立離脱して、日本維新の会が「閣外協力」の形で自民党と連立政権合意書を結び、高市早苗総理が誕生することとなりました。
このことが示唆しているのは、「自民党も立憲民主党も衆議院で単独過半数の議席を持たない状況では、どの政党が野党第二党の位置にいるのかによって、政治の全体の方向性が大きく変わってくる」ということです。
従って、「れいわ新選組が議席を伸ばして、なんとか野党第二党のところまで規模を拡大できれば、世の中が良くなっていくのではないか」という希望を持つことができます。
しかし、逆の面に注目するなら、「参政党が議席を伸ばして、もし野党第二党のところまで規模を拡大するなら、これまで以上に世の中が大変な状況になっていくのではないか」という恐怖を感じることになります。
そういう意味では、次期衆院選の選挙結果がどうなるかが、極めて重要になってきます。
第3回:れいわ新選組への期待と不安【期待編】(2022年2月9日掲載)
第4回:れいわ新選組への期待と不安【不安編】(2022年2月23日掲載)
さて、過去記事アクセス数ランキング、堂々第1位には連載第3回「れいわ新選組への期待と不安【期待編】」(2022年2月9日掲載)が、第3位には連載第4回「れいわ新選組への期待と不安【不安編】」(2022年2月23日掲載)がランクインしました。
やはりSAMEJIMA TIMESの読者のみなさまは、れいわ新選組の話に一番関心が高いようです。
今回の「連載100回記念・過去記事アクセスランキング」は、「れいわ新選組への期待と不安【期待編】」の結びを引用として、議論の締めとしたいと思います。
庶民が少しずつお金を持ち寄って「れいわ新選組」を支えていったとして、「山本太郎総理」が誕生するのは一体いつのことになるのか?
「れいわ新選組」がこれから順調に党勢を拡大していったとして、「山本太郎総理」が誕生するのは、今から10年後か15年後のことになるのではないかと私は想像しています。
1993年に非自民連立政権を樹立した「日本新党」は結党から1年余りで「細川護熙総理」を誕生させましたが、これは中選挙区制時代の話で、小選挙区制になってからは、「民主党」が「鳩山由紀夫総理」を誕生させるまでに13年かかっています。
これくらいの時間がかかることを覚悟しておくべきなのだろうと私は考えています。
仮に10年~15年の時間がかかったとしても、もし「れいわ新選組」が自力で政権を獲ることになるならば、救われる人々がたくさんいると期待しています。
それは、「ロスジェネ世代の老後」に間に合うからです。
今後20年~30年のスパンで見た日本の課題が何かと言えば、それは「ロスジェネの老後をどうするか」ということが一番大きな要素になると考えています。
もし、今から10年~15年の時間がかかったとしても、「何があっても心配するな。そんな国をあなたと作りたい。」という「山本太郎総理」が誕生するならば、「ロスジェネの老後」は救われます。
「ロスジェネ世代」の中には生活に汲々として貯蓄ゼロという人も少なくないと思いますが、そうした貯蓄ゼロの人が今から毎年100万円貯金して、これから20年で2,000万円の老後資金を貯めるなどというのは、非現実的だと思います。
しかし、「れいわ新選組」への少額の寄付ならば、何とかやれるのではないでしょうか。
そうした少額の寄付をみんなで持ち寄って、あまたいる世襲議員やエスタブリッシュメントを押しのけて「山本太郎」を「ロスジェネ世代の代表選手」として「総理大臣」の立場で「首相官邸」に送り込むことができたなら、それは本当に「ロスジェネ世代の逆襲」あるいは「ロスジェネを見捨てた社会へのリベンジ」になるのではないかと思います。
誤解のないように言っておきますと、私はなにも「れいわ新選組」に対して「ロスジェネを優遇する政策を進めろ」と言っているわけではなく、「ロスジェネを含む全ての人々が安心して暮らせる国を作ることで、結果として困窮するロスジェネの老後を救うことができる」と主張したいということです。
ロスジェネ世代は若い時代に苦労をし、今も辛酸をなめている人が少なくありませんが、人生の最終コーナーを回った段階で「生きてて良かった」と思える暮らしができ、若い頃に一度あきらめた夢に再びチャレンジしたり、趣味に没頭できるような時間を過ごしたりすることができれば、自らの人生を肯定的な感情で振り返りながらゴールまで走り抜けることができるのではないかと思います。
SAMEJIMA TIMES主筆の鮫島浩さんは「<右の維新>vs<左のれいわ>が日本政界の新しい対立軸だ」と述べられていますが、ロスジェネが国に見捨てられ続けるのか、あるいは、「何があっても心配するな。そんな国をあなたと作りたい。」という「山本太郎総理」を誕生させて、ロスジェネが自らの手でロスジェネを救う国を作ることができるのか、それを決めるのは、「この国のオーナー」である「あなた」次第です。
3.トピックス①:高市政権誕生
2025年10月21日、臨時国会の首班指名選挙で自民党総裁の高市早苗さんが総理大臣に指名され、憲政史上初の女性総理が誕生しました。
さまざまな先人たちが「ガラスの天井」に挑んで跳ね返されてきた中で、総理大臣の座に昇り詰めた高市早苗さんに、まずはお祝いの言葉を述べたいと思います。
高市早苗さんは、特に政治家の家に生まれたわけでもなく、ご自身の才覚と力量だけでこの地位に昇り詰めた「叩き上げ」の人ですので、その高市さんが日本史上初の女性総理になったことは、後に続こうとする人たちにとって、大いに希望になると思います。
G7の国の中で、アメリカだけは女性大統領がまだ誕生していません。
2016年のアメリカ大統領選挙に出馬したヒラリー・クリントンさんも、2024年のアメリカ大統領選挙に出馬したカマラ・ハリスさんも、現大統領のドナルド・トランプさんに敗れ、アメリカ史上初の女性大統領の座を逃しました。
そうした意味からすれば、日本がアメリカよりも先に女性総理を誕生させたことは、日本人として誇りに思ってもよいのではないでしょうか。
4.トピックス②:議員定数削減問題
自民党と日本維新の会が連立政権合意書を結んで連立政権が誕生(ただし、維新からは閣僚は出さず、閣外協力のみ)したことに伴い、国会において、議員定数削減問題が政治課題として急浮上してきました。
1993年に発足した非自民連立政権の細川護熙内閣による「政治改革」で小選挙区比例代表並立制が導入された時、小選挙区が300議席、比例区が200議席の計500議席だった衆議院の定数は、これまで30年の間に徐々に削減されてきました。
衆議院定数の変遷(小選挙区比例代表並立制導入以後)
| 1994年改革 | 2000年改革 | 2013年改革 | 2016年改革 | |
| 小選挙区定数 | 300議席 | 300議席 | 295議席 | 289議席 |
| 比例区定数 | 200議席 | 180議席 | 180議席 | 176議席 |
| 衆議院定数合計 | 500議席 | 480議席 | 475議席 | 465議席 |
日本維新の会の提案は、ここからさらに50議席定数を削減し、しかも比例区の定数を50議席削減するという、かなり荒っぽい提案です。
これに対して、主に小規模政党の政治家から、議員定数削減反対の声があがっています。
チームみらいの安野貴博さんが言われていることは、政治学者が発するコメントであれば100点満点なのだと思いますが、政治家の発言ということを考慮すれば、国民感情からズレた発言だというふうに感じてしまいます。
民間企業であれば、経費削減のために人員を減らして少人数で現場を回しているケースはザラにあります。
また、家庭においても、どうやって食費を抑えようかとか、おこずかいを減らすしかないかなぁとか、家計のやり繰りに汲々としているところが多いと思います。
「我々も苦しい思いをしているのだから、政治家も自分の身を切って国民と苦労を共にすべきだ」と考える国民は少なくないでしょう。
また、「議員定数が多ければ多いほど国民の意見を十分に反映することができ、議員定数が少なければ少ないほど国民の意見が反映されなくなる」というものの見方は、必ずしも正しくないと私は考えます。
仮にいま逆に議員定数を増加し、小選挙区を324議席、比例区を176議席で衆議院の議員定数を500議席に回復させたとした場合には、そのことによって国民の意見を十分に反映させることができるようになるでしょうか?
いま一番考えなければならないことは、「議員定数を増やすか減らすか」ではなく、「小選挙区と比例区の議席配分をどのようにするか」ということだと思います。
維新が提案している「比例のみ50議席削減」の案のほかに、私が提案したい「小選挙区40議席削減、比例区10議席削減」の案を比較検討してみましょう。
衆議院定数50議席削減2案比較
| 現 状 | 比例のみ50削減 | 小選挙区40比例10削減 | |
| 小選挙区定数 | 289議席 | 289議席 | 249議席 |
| 比例区定数 | 176議席 | 126議席 | 166議席 |
| 衆議院定数合計 | 465議席 | 415議席 | 415議席 |
維新が提案している「比例のみ50議席削減」の案の場合には、1994年当初の「小選挙区300、比例区200」の時と比較すると、小選挙区の議席は約3.7%しか削減されていないのに対し、比例区の議席は37%と10倍以上のボリュームで大幅に削減されてしまいます。
小選挙区と比例区の議席配分は、1994年当初「6:4」だったものが、維新の削減案実施後は「7:3」へとすっかり変貌してしまっています。
私が提案したい「小選挙区40議席削減、比例区10議席削減」の案であれば、全体で50議席削減した後も、小選挙区と比例区の議席配分を「6:4」に保つことができます。
小選挙区制は死票が多くなりやすい選挙制度ですので、幅広い民意を議会に反映させるためには、比例区の定員を十分に確保して、少数政党が当選者を出すことができるような全体の制度設計にしておく必要があります。
たとえ10議席であっても、比例区の議席を削減してしまうと、少数政党を国会から排除することにつながってしまうのではないかという懸念を持つ方もおられるかもしれません。
そうしたことを懸念するのであれば、比例区のブロック割を見直すという方法もあります。
比例区ブロック割変更(案)
| 現行比例ブロック | 定数 | 新比例ブロック(案) | 定数(案) |
| 北海道ブロック | 8議席 | 東日本ブロック | 20議席 |
| 東北ブロック | 13議席 | ||
| 北関東ブロック | 20議席 | 関東ブロック | 56議席 |
| 南関東ブロック | 22議席 | ||
| 東京ブロック | 17議席 | ||
| 北陸信越ブロック | 10議席 | 中部ブロック | 29議席 |
| 東海ブロック | 21議席 | ||
| 近畿ブロック | 28議席 | 関西ブロック | 26議席 |
| 中国ブロック | 11議席 | 西日本ブロック | 35議席 |
| 四国ブロック | 6議席 | ||
| 九州ブロック | 20議席 | ||
| 比例区合計 | 176議席 | 比例区合計 | 166議席 |
北海道ブロックと東北ブロックを統合して「東日本ブロック」(仮称)に、北関東ブロックと南関東ブロックと東京ブロックを統合して「関東ブロック」(仮称)に、北陸信越ブロックと東海ブロックを統合して「中部ブロック」(仮称)に、近畿ブロックを名称変更して「関西ブロック」(仮称)に、中部ブロックと四国ブロックと九州ブロックを統合して「西日本ブロック」(仮称)に衆議院の比例ブロックを再編した場合、「関西ブロック」(仮称)のエリア以外のエリアではブロックごとの定数が増加することになります。
特に「関東ブロック」(仮称)は一つのブロックで56議席の定数を有することになるため、現在政党要件を得ている小規模政党以外に、国政に議席を持っていない政治団体にも新たな議席獲得のチャンスが生まれてきます。
このような方向で選挙制度の改革を行うなら、衆議院の議員定数削減を行ったとしても、かえって議会に対する民意の反映状況をより適正な状況に変更できる可能性があるのではないでしょうか。
国会で議員定数削減に関する議論が進んでいけば、国民の関心も自然とそのことに集まってきます。
そこで、NHKの日曜討論などのテレビ番組で議論になった時に、維新がこれまでに大阪府議会で行ってきた「議員定数削減」が、「選挙区の1人区化」を誘発し、意図的か、意図せざる結果かにかかわらず、死票を多く出してしまう選挙制度に換骨奪胎するものであったことを全国の視聴者に広く知らせるべきです。
維新が大阪府議会で行った「複数区を1人区化する議員定数削減」は、「死票を多く出して民意を切り捨てる選挙制度改悪」に他ならず、いま維新が提案している「比例50議席削減による衆議院の議員定数削減」もまた、「死票を多く出して民意を切り捨てる選挙制度改悪」にしかなりません。
そのことを世論喚起し、衆議院では「小選挙区と比例区の議席配分を適正化する議員定数削減」を図り、大阪府議会に関しても「1人区になってしまった選挙区を合区して複数区化する選挙制度再改革」の必要性を訴えていくなら、維新の提案を逆に利用して、自民と維新を追い込んでいくことができるのではないでしょうか。
5.トピックス③:村山富市元総理逝去
第81代内閣総理大臣を務めた村山富市さんが、10月17日に大分市内の病院で老衰のため101歳で逝去されました。
哀悼の意を表しますとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
社会党委員長に就任した時から「社会党最後の委員長」と呼ばれ、政治的にはほとんど無名だった村山富市さんは、テレビ番組「進め!電波少年」でタレントの松村邦洋さんにアポなしで眉毛を切られてから急にツキが回ってきて、あれよあれよという間に国会で首班指名を受け、第81代内閣総理大臣に就任しました。
戦後50年の節目の時期に総理大臣の座にあった村山富市さんは、1995年8月15日に、戦後50年「村山談話」を発表します。
当時新人議員だった高市早苗さんは「勝手に代表して謝ってもらっちゃ困る」と村山談話を非難しましたが、村山富市総理の跡を継いだ橋本龍太郎総理も、その後の小泉純一郎総理も、安倍晋三総理も、そして高市早苗さんの一つ前の総理大臣の石破茂総理も、歴代の総理大臣が「村山談話を踏襲する」もしくは「村山談話を引き継ぐ」という姿勢を明らかにしています。
村山富市さんは亡くなりましたが、村山談話は永遠に残ります。
村山富市さん、本当にありがとうございました。
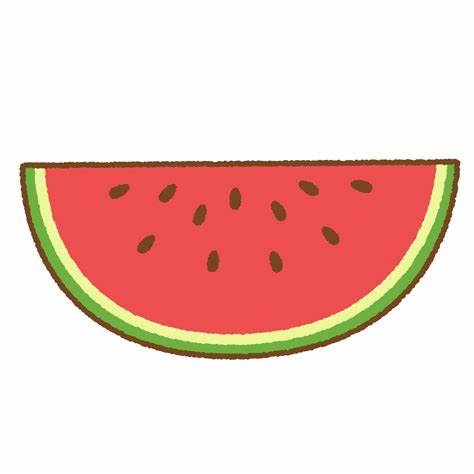
憲法9条変えさせないよ
プロ野球好きのただのオジサンが、冗談で「巨人ファーストの会」の話を「SAMEJIMA TIMES」にコメント投稿したことがきっかけで、ひょんなことから「筆者同盟」に加わることに。「憲法9条を次世代に」という一民間人の視点で、立憲野党とそれを支持するなかまたちに、叱咤激励と斬新な提案を届けます。

